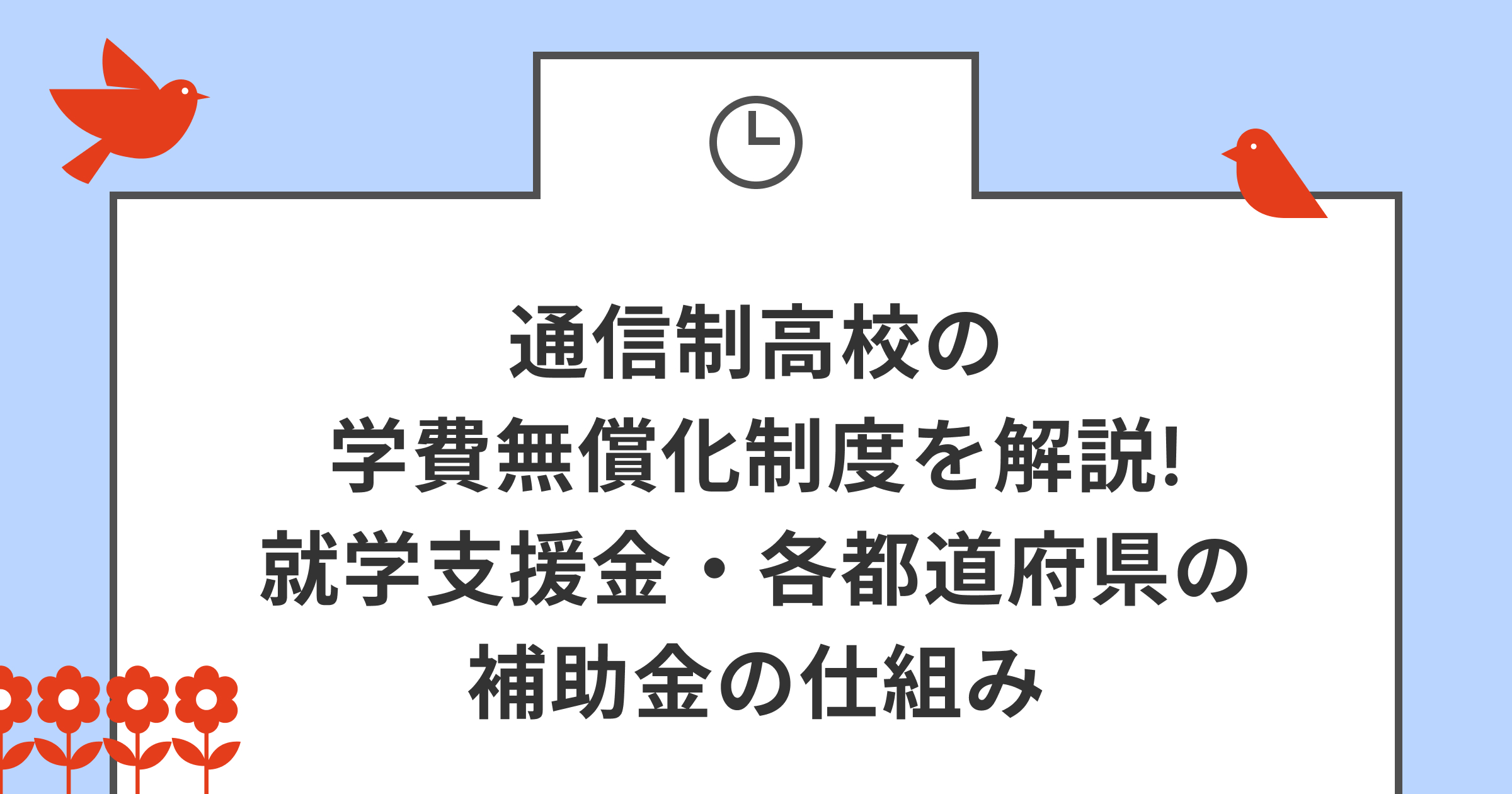「通信制高校の学費は、本当に無償になるのだろうか?」
「就学支援金という制度は耳にするけれど、手続きが複雑そうで不安…」
「結局のところ、入学から卒業までにいくら準備すれば良いのか、具体的な金額が知りたい」
お子様の新しい学びの選択肢として通信制高校を検討されている中で、やはり一番気がかりなのは費用のことではないでしょうか。
「無償化」という言葉はとても魅力的ですが、その詳しい内容やご家庭に当てはまるのかが分からず、不安を感じられる方は多いです。
そこで、この記事では、通信制高校の学費が無償化される中心的な制度である国の「高等学校等就学支援金」から、お住まいの地域が独自に設けている補助金制度まで、専門用語をできるだけ使わずに、一つひとつ丁寧に解説します。
この記事を読み終える頃には、ご家庭の状況に合わせてどの制度が利用でき、実際にどのくらいの費用を見込んでおけば良いのか、明確なイメージが掴めるようになっているはずです。
お子様にとって最適な一歩を踏み出すためのガイドとしてご活用ください。(2025年8月現在)
通信制高校の学費無償化制度とは?
通信制高校の学費を実質的に無償化できる制度は、主に国と都道府県がそれぞれ設けている支援制度の組み合わせで成り立っています。
- 国の制度: 全国の高校生を対象とした「高等学校等就学支援金制度」
- 都道府県の制度: お住まいの地域が独自に上乗せする「補助金・助成金制度」
- 対象費用: どちらの制度も基本的には「授業料」が対象
これらの制度を賢く活用することで、学費の負担を大幅に軽減できる可能性があります。
それでは、制度の全体像から、対象となる費用・ならない費用について、詳しく見ていきましょう。
無償化制度の全体像
通信制高校の学費負担を軽くするための制度は、国が主体となる「高等学校等就学支援金制度」が基本です。
そして、その国の制度に加えて、各都道府県が独自の補助金や助成金制度を設けて、さらに手厚い支援を行っている場合があります。
つまり、国の制度と都道府県の制度、この2つの支援を組み合わせることによって、授業料が実質的に無償化されるケースも少なくありません。
例えば、東京都や大阪府などでは、国の支援金と都・府の補助金を合わせることで、所得制限が緩和されたり、手厚い支援が受けられたりする仕組みが整えられています。
重要なのは、お住まいの地域の制度がどうなっているかを確認することです。
国の制度と地域の制度の両方を視野に入れることが、学費の負担を最大限に抑えるための鍵となります。
通信制高校で無償化できる費用・できない費用
通信制高校の学費が無償化される、と聞いたときに最も注意すべき点は、無償化の対象となる費用が主に「授業料」に限定されるという事実です。
無償化の対象となるのは、学校の授業を受けるために必要な「授業料」です。
通信制高校は単位制が多いため、1単位あたりの授業料に就学支援金が適用される形で計算されるのが一般的です。
一方で、以下のような費用は無償化の対象外となり、原則として自己負担となることを覚えておく必要があります。
通信制高校、サポート校の情報を集めるうえで、必ず確認いただきたいのが、この「授業料以外の費用」についてです。授業料以外にどんな費用がかかるかは学校により仕組みが異なり、設備費、システム費、サポート費などがかかる場合が多いです。そのため、あくまで学校別の費用を把握する場合には、学校別にかかる費用の一覧を必ず確認(もしくは問い合わせ)するようにしてください。
高等学校等就学支援金(国の制度)の仕組み
通信制高校の学費を支える最も基本的な制度が、国の「高等学校等就学支援金」です。
この制度について正しく理解することが、学費無償化への第一歩となります。
このセクションでは、就学支援金制度について、以下の点を詳しく解説していきます。
- 制度の基本的な考え方
- 支援を受けられる人の条件
- 申請から支給までの具体的な流れ
- 通信制高校における支給額の計算方法
- ご家庭の年収によってどう支給額が変わるのか
- 2025年時点での最新情報と注意点
就学支援金制度の基本的な仕組み
高等学校等就学支援金制度は、国がご家庭に代わって高校の授業料を学校に直接支払う、返済が不要な給付型の支援制度です。
この制度の目的は、ご家庭の教育費負担を軽減し、生徒が経済的な理由で進学を諦めることがないようにすることにあります。
最大の特長は、支援金が保護者の口座に振り込まれるのではなく、国から直接、生徒が在籍する高校へ支払われる点です。
この仕組みにより、ご家庭では授業料の支払いを一時的に立て替える必要がありません。
つまり、原則ご家庭の現金の持ち出しなしで授業料の支援が受けられるという、非常にありがたい制度設計になっているのです。
受給条件・受給資格
高等学校等就学支援金を受け取るためには、いくつかの条件を満たす必要があります。
まず、最も重要なのが「世帯年収」の要件です。
2025年度まで、国の実施する就学支援金制度においては、世帯年収目安約「910万円」が1つの基準となり、この額を超える場合は就学支援金を受けることができませんでした。しかし、現在この条件は緩和され、世帯年収によらず就学支援金の適用が受けられるようになっており、2026年度以降はさらに拡充された制度を国で検討をしています。
次に、生徒本人の要件です。
日本国内に住所があり、高等学校等に在学していることが必要です。
ただし、高校をすでに卒業したことがある生徒や、在学期間が通算で48ヶ月(定時制・通信制の場合)を超えている生徒は、原則として対象外となります。
この2つの条件に当てはまれば、国公私立を問わず、通信制高校に通う多くの生徒が支援の対象となります。
申請方法と手続きの流れ
就学支援金の申請は、基本的に入学後の定められた期間に、在学する高校を通じて行います。
申請のタイミングは、新入生の場合は4月頃、転入学生の場合は転籍後2〜3ヶ月後に学校から案内があるのが一般的です。
申請には、主に以下の書類が必要となります。
- 受給資格認定申請書: 学校から配布されます。
- マイナンバーカードの写しまたはマイナンバーが記載された住民票など: 保護者(親権者)全員分が必要です。
近年、手続きの利便性を高めるために、文部科学省が運営するオンライン申請システム「e-Shien」を導入する学校が増えています。
e-Shienを利用すれば、スマートフォンやパソコンから24時間いつでも申請手続きを進めることができ、書類を学校に持参する手間が省けます。
【担当アドバイス】書類準備のコツ
申請でつまずきやすいのが、マイナンバー関連書類の準備です。
特に、ご両親が親権者の場合は、お二方それぞれのマイナンバーを確認できる書類が必要になります。
学校からの案内に気づいた時点で、早めに必要書類を確認し、不備がないかチェックしておくことが、スムーズな手続きの秘訣です。
もしご不明な点があれば、遠慮なく学校の事務室に問い合わせてみましょう。
参考:文部科学省:e-Shien(高等学校等就学支援金オンライン申請システム)
支給までの流れ
申請手続きが完了してから、実際に就学支援金が支給される(授業料に充当される)までには、いくつかのステップがあります。
この流れの中で、保護者が直接お金のやり取りをすることはありません。
ただし、認定結果が通知されるまでは授業料の支払いが一時的に保留されたり、一度納入した後に還付されたりと、学校によって認定までの授業料の取り扱いが異なるため、入学時に学校の事務室へ確認しておくと安心です。
通信制高校の場合の支給額の計算方法
通信制高校の就学支援金の支給額は、一般的な全日制高校とは少し異なり、「単位制」で計算されるのが特徴です。
通信制高校の授業料は、1年間で履修する単位数に応じて決まることが多いため、支援金もその単位数に基づいて支給されます。
具体的には、「1単位あたりの支給額 × 履修単位数」で計算されます。
この制度には上限が設けられています。
支援の対象となるのは、年間で最大30単位まで、高校在学期間を通じて通算で74単位までです。
74単位は、高校卒業に必要な単位数ですので、ほとんどの生徒が必要な単位を修得するまで支援を受けられる計算になります。
また、支援を受けられる期間は、通信制高校の場合、最大で48ヶ月(4年間)と定められています。
自分のペースで学習を進める通信制の特性に配慮した、柔軟な支援期間の設定がされている点も、安心材料の一つと言えるでしょう。
参考:文部科学省:高等学校等就学支援金の支給(単位制)について
世帯年収による支給額の違い【一目でわかる早見表付き】
就学支援金の支給額は、授業料の全額ではなく、世帯年収に応じて段階的に設定されています。
私立の通信制高校に通う場合を例に、具体的な支給額を見ていきましょう。
※実際の支給額は、学校の授業料(1単位あたり)が上限となります。例えば、授業料が1単位10,000円の学校の場合、支給額も10,000円となります。
表を見ていただくと分かる通り、最も手厚い支援が受けられるのは、世帯年収の目安が約590万円(共働きの場合660万円)未満のご家庭です。
この場合、私立通信制高校の授業料が上限額の範囲内であれば、実質的に授業料が無料になる可能性が高まります。
ご自身の世帯年収がどの区分に当てはまるかを確認することが、学費計算の第一歩です。
参考:私立高校授業料実質無償化
【2025年最新】制度の変更点と注意事項
高等学校等就学支援金制度は、社会情勢に合わせて見直しが行われることがあります。
2025年時点での主な動向と、改めて確認しておきたい注意点をまとめました。
まず、2025年に国の就学支援金の制度は強化され、従来の年収目安910万円未満の世帯にのみ適用だった「高等学校等就学支援金」制度に加え、年収目安910万円以上の家庭にも「高校生等臨時支援金」制度が実装されたことで、世帯年収に関わらず学費減免の措置が受けられるようになりました。
2026年度にはそもそもの所得制限の撤廃や私立高校等の加算額の引き上げも含めたいわゆる「高校授業料の無償化」を別途検討中になっていますので、さらに制度が拡充される可能性があります。
手続き面では、先ほども触れたオンライン申請システム「e-Shien」の導入が全国で進んでいます。
ご自身やお子様が入学を検討している学校がe-Shienに対応しているかどうか、事前に確認しておくと、手続きのイメージがしやすくなります。
最後に、非常に重要な注意点として、通信制高校と連携して生徒の学習や生活をサポートする「サポート校」の学費は、就学支援金の対象外であるという事実です。
サポート校の利用を検討している場合は、通信制高校の授業料とは別に、サポート校の費用が自己負担となることを必ず理解しておく必要があります。
「社会で生きていける力」を。
- 入学前不登校経験者8割。
入学後登校率89% - ぷよぷよ、モンスト開発者、
日本一になった起業家
から直接学べる - docomo、Lotte、Mixiなど
大企業と連携したプロジェクト型学習

各地域の補助金・助成金(都道府県の制度)の仕組み
国の就学支援金に加えて、お住まいの都道府県が独自に設けている補助金や助成金制度を活用することで、さらに学費の負担を軽減できる場合があります。
都道府県独自の支援制度について、以下の点をご紹介します。
- どのような仕組みで支援が行われるのか
- 申請窓口はどこになるのか
都道府県独自の補助金制度とは
都道府県が設けている補助金制度は、国の就学支援金だけではカバーしきれない学費負担を、さらに軽くすることを目的としています。
多くの場合、国の就学支援金制度に「上乗せ」する形で支給されるのが特徴です。
支援の内容は、地域によって大きく異なります。
例えば、国の制度では世帯年収に応じて国の制度以上の支援が受けられたり、入学金の補助制度を設けたり、あるいは国の支援金と合わせて授業料が完全に無償になるよう差額を補助したりと、実に様々です。
ご家庭にとって最も手厚い支援を受けるためには、国の制度だけでなく、お住まいの都道府県や市区町村にどのような制度があるのかを、必ず確認することが重要になります。
申請窓口と手続きの流れ
都道府県独自の補助金の申請窓口や手続き方法は、国の就学支援金とは異なる場合があるため注意が必要です。
国の就学支援金は、在学する学校を通じて申請するのが一般的ですが、都道府県の補助金は、学校を通じて申請する場合と、保護者が直接都道府県の担当窓口(教育委員会など)に申請する場合の両方のパターンがあります。
申請時期も、4月〜7月頃に集中することが多いですが、自治体によって締め切りが異なります。
「国の制度とは別に申請が必要だったことを知らなかった」という事態を避けるためにも、入学を決めた段階で、学校の事務室や都道府県のホームページで確認しておくことを強くお勧めします。
主要都道府県の補助金制度【2025年最新版】
主要な都道府県の補助金制度について、2025年現在の情報に基づきご紹介します。
お住まいの地域にどのような特色があるのか、ぜひ参考にしてください。
東京都:私立高校授業料実質無償化
東京都では、国の就学支援金と都独自の「私立高等学校等授業料軽減助成金」を組み合わせることで、所得制限を大幅に緩和し、授業料を実質無償化する制度を設けています。
大きな特徴は、年収帯に関わらず支援金が上乗せされるということです。
この制度により、東京都にお住まいで通信制に通われる方は、国の制度とあわせて、学校の授業料を上限額とし年間最大49万円まで助成を受けることができます。
申請窓口と手続きの流れ
申請は、例年6月下旬から7月頃にかけて、在学する学校を通じて行われます。
国の就学支援金の申請とは別に、東京都への申請手続きが必要となります。
申請書類は学校から配布され、保護者が記入した後、学校に提出するのが一般的な流れです。
支給までの流れ
申請後、東京都による審査が行われ、認定されると、助成金が学校へ直接支払われます。
保護者への結果通知は、通常12月〜1月頃となります。
それまでの授業料の取り扱い(一旦納入するか、支払いが猶予されるか)は学校によって異なるため、事前に確認が必要です。
参考:東京都私学財団:私立高等学校等授業料軽減助成金事業
大阪府:所得制限なしの無償化制度
大阪府の「私立高等学校等授業料支援補助金」は、全国でも特に手厚い制度として知られています。
最大の特徴は、保護者の所得制限を設けていない点です。
保護者が大阪府在住で、生徒が大阪府内の私立高校等に在学していれば、全ての世帯が授業料無償化の対象となります。
- ただし、無償となるのは標準授業料(年間63万円)までという上限があり、それを超える部分や、授業料以外の費用は自己負担となります。(令和8年度以降、金額上限、学校の縛りなく、全世帯が授業料全額無償化になります。)
申請窓口と手続きの流れ
申請手続きは、在学している学校を通じて行います。
毎年6月頃に学校から案内があり、オンラインで申請手続きを進めるのが基本です。
国の就学支援金と同様に、保護者のマイナンバーなどを利用して所得情報を連携させる仕組みになっています。
支給までの流れ
無償化制度の対象者については、国の就学支援金及び大阪府の授業料支援補助金を合わせて授業料が無償となるように支援されますが、学校によっては一旦授業料を納める必要がある場合があります。また、授業料が標準授業料額(全日制:63万円、通信制:1単位あたり12,030円)を超える学校については、所得によって納付額が発生する場合があります。納付が困難な事情がある場合は学校へご相談ください。
国の就学支援金と大阪府の授業料支援制度両方の申請が必要です。学校からの案内に従って必ず手続きを行ってください。
オンラインで申請後、大阪府で審査が行われます。
審査結果は学校を通じて通知され、補助金は府から直接学校へ支払われます。
授業料の取り扱いは学校ごとに定められているため、入学時の説明会などで確認しておきましょう。
参考:大阪府:私立高等学校等授業料支援補助金
埼玉県:父母負担軽減事業補助金
埼玉県では、国の就学支援金に上乗せする形で、「私立学校父母負担軽減事業補助金」を設けています。
この制度は、世帯の所得に応じて段階的に補助額が設定されており、特に生活保護世帯や年収が低い世帯に対して手厚い支援を行っているのが特徴です。
国の就学支援金と合わせることで、授業料の大部分がカバーされるケースが多くあります。
ただし、補助額は学校の授業料が上限となります。
申請窓口と手続きの流れ
申請は、在学している学校を通じて行います。
通常、6月〜7月頃に学校から申請書類が配布されますので、必要事項を記入し、所得を証明する書類(課税証明書など)を添付して学校に提出します。
支給までの流れ
学校が取りまとめて県に申請し、審査が行われます。
審査の結果、支給が決定すると、補助金は県から直接学校へ支払われ、授業料に充当されます。
保護者へは、学校を通じて結果が通知されます。
参考:埼玉県:私立学校の父母負担軽減事業について
愛知県:授業料軽減補助金
愛知県には、私立高校に通う生徒の保護者の経済的負担を軽減するため、「愛知県私立高等学校等授業料軽減補助金」という制度があります。
この制度も、国の就学支援金に上乗せする形で、世帯の所得状況に応じて補助が行われます。
国の就学支援金と県の補助金を合わせることで、年収約720万円未満の世帯では授業料負担が大幅に軽減されるよう設計されています。
申請窓口と手続きの流れ
申請は、在学する学校を通じて行います。
毎年6月頃に、学校から申請の案内と書類が配布されます。
保護者は、申請書に必要事項を記入し、市町村が発行する所得課税証明書などを添付して、学校の定める期限までに提出する必要があります。
支給までの流れ
提出された申請書に基づき、県が審査を行います。
支給が決定されると、補助金は学校に直接振り込まれ、後期授業料などから差し引かれる形で還元されるのが一般的です。
結果の通知は、通常、年度の後半になります。
参考:愛知県:私立高等学校授業料軽減補助について
神奈川県:学費補助金
神奈川県では、私立高等学校等に通う生徒向けに「学費補助金」制度を設けています。
この制度は、「授業料に対する補助」と、全国でも珍しい「入学金に対する補助」の二本立てになっているのが大きな特徴です。
授業料補助は、国の就学支援金を受給していてもなお負担が残る場合に、世帯の所得に応じて上乗せで支給されます。
年収約750万円未満の世帯が主な対象です。
入学金補助は、年収約750万円未満の世帯を対象に、一律で10万円が補助されるため、入学時の初期費用を抑えたいご家庭にとっては非常に助かる制度です。
申請窓口と手続きの流れ
申請は、授業料補助と入学金補助で時期が異なります。
入学金補助は、入学後の早い時期(4月〜5月頃)に学校を通じて申請します。
授業料補助は、例年6月〜7月頃に、同じく学校を通じて申請するのが一般的です。
いずれも、所得証明書類などが必要となります。
支給までの流れ
申請後、県による審査が行われ、支給が決定します。
他の都道府県と同じく、支給が決定されると、補助金は学校に直接振り込まれ、後期授業料などから差し引かれる形で還元されます。県から保護者への振込はありません。
(保護者口座へ振り込まれる支援制度であれば給付金)
各校で授業料の軽減方法・時期が異なりますので、詳細は学校にご確認ください。
参考:神奈川県:私立高等学校等生徒学費補助金
その他の学費支援制度
授業料の支援だけでなく、それ以外の教育費の負担を軽くするための制度も存在します。
ここでは、知っておくと役立つその他の学費支援制度についてご紹介します。
高校生等奨学給付金(授業料以外の支援)
高校生等奨学給付金は、授業料以外の教育費の負担を軽減するための制度です。
教科書費、教材費、学用品費、通学用品費、修学旅行費など、高校生活で必要となる様々な費用を支援してくれます。
この制度の対象となるのは、生活保護を受けている世帯や、住民税所得割が非課税の世帯です。
返済は不要で、給付額は世帯の状況や子の人数によって異なりますが、年間で約3万円から14万円程度が給付されます。
申請は、お住まいの都道府県に対して行い、多くの場合、学校を通じて手続きをします。
参考:文部科学省:高校生等奨学給付金
母子家庭・父子家庭が使える追加支援
母子家庭(シングルマザー)や父子家庭(シングルファザー)の経済的負担を軽減するため、地方自治体が独自の支援制度を設けている場合があります。
代表的なものに「母子父子寡婦福祉資金貸付金制度」があります。
この制度の中には、高校や大学への進学に必要な資金を無利子または低金利で借りられる「修学資金」が含まれています。
これは貸付金制度のため返済が必要ですが、一般的な教育ローンに比べて有利な条件で借り入れが可能です。
また、自治体によっては独自の給付金や貸付制度を設けていることもあります。
お住まいの市区町村の役所の「子育て支援課」などの窓口に問い合わせてみることで、利用できる制度が見つかるかもしれません。
参考:母子父子寡婦福祉資金貸付金制度 | 内閣府男女共同参画局
民間の奨学金・教育ローン
国の制度や自治体の制度だけでは学費のすべてを賄うのが難しい場合には、民間の団体が提供する奨学金や、金融機関の教育ローンを利用するという選択肢もあります。
民間の奨学金には、返済不要の「給付型」と、返済が必要な「貸与型」があります。
交通遺児育英会やあしなが育英会など、特定の条件を満たす生徒を対象としたものから、成績優秀者や特定の分野に興味を持つ生徒を対象としたものまで様々です。
教育ローンは、日本政策金融公庫が扱う「国の教育ローン」が有名で、比較的低い金利で借り入れが可能です。
民間の銀行などが扱う教育ローンは、国のローンに比べて金利がやや高めですが、手続きが迅速などのメリットがあります。
安易な借り入れは将来の負担になるため、利用は慎重に検討する必要があります。
「社会で生きていける力」を。
- 入学前不登校経験者8割。
入学後登校率89% - ぷよぷよ、モンスト開発者、
日本一になった起業家
から直接学べる - docomo、Lotte、Mixiなど
大企業と連携したプロジェクト型学習

通信制高校の実質負担額をシミュレーション
ここまで様々な制度を見てきましたが、実際にどのくらいの費用がかかるのか、具体的なイメージを持つことが大切です。
ここでは、いくつかのパターンに分けて、年間の実質負担額をシミュレーションしてみましょう。
※世帯年収約590万円未満で、国の就学支援金(私立上限)と、お住まいの地域の補助金を満額利用できると仮定します。
公立通信制高校の場合
公立の通信制高校は、もともとの授業料が非常に安価に設定されているのが特徴です。
就学支援金を利用することで、授業料はほぼ無償となります。
そのため、年間の実質的な負担は教材費などの諸費用のみとなり、非常に経済的です。
私立通信制高校の場合
私立の通信制高校は、サポート体制が手厚い分、公立に比べて学費は高めですが、支援制度の恩恵も大きくなります。
国の就学支援金や都道府県の補助金を最大限活用することで、授業料部分は実質0円になる可能性があります。
負担額は入学金や施設費、教材費が中心となります。
私立通信制高校+サポート校の場合
通信制高校と同時にサポート校に通う場合のシミュレーションです。
ここでは、私たちHR高等学院のようなサポート校を利用するケースを例に見てみましょう。
このケースで最も重要な点は、提携している私立通信制高校の授業料には就学支援金が適用される一方で、サポート校であるHR高等学院の学費は補助の対象外となり、自己負担となる点です。
サポート校の費用は、公的な支援の対象外であることを、必ず念頭に置いておく必要があります。
【担当アドバイス】費用対効果の考え方
サポート校に通うと、確かに費用負担は大きくなります。
しかし、その費用がお子様の未来にとってどのような価値を持つのか、という「費用対効果」の視点で考えることが非常に重要です。
例えば、HR高等学院では、日本を代表する大企業であるdocomo、LOTTE、CHINTAI、mixiなど名だたる企業と組んで提供する企業連携PBL(Project Based Learning)や、起業家の成田修造さんやReHacQプロデューサーの高橋弘樹さんなどのトップランナー講師から双方向で受けられる講義、将来の夢を見つけるためのキャリア教育、海外進学含め希望の進路を実現するための大学受験対策など、通信制高校だけではカバーしきれない多角的なサポートを提供しています。
「費用はかかっても、手厚いサポートのおかげで無事に高校を卒業し、希望の将来を歩めた」という結果に繋がるのであれば、それはお子様の人生にとって非常に価値のある投資と言えます。
ご家庭の経済状況と、お子様が必要としているサポートの内容をじっくりと見極めて高校3年間の貴重な時間をどのように過ごすのかを検討いただくことをおすすめします!
「どのような通信制高校・サポート校を選べばいいか分からない…」「子どもの今とこれからに深く悩んでいる…」という方はぜひHR高等学院のオープンキャンパスや説明会にいらしてください!その際は「記事を見た」と言っていただければ、私(HR高等学院 運営責任者 恒弘 大輔)が対応させていただきます。
そもそも通信制高校に入学・転入するかどうかも悩んでいるという方も歓迎です。どんな学生もキャリアを輝かせる可能性に満ちていると私たちは信じています。ぜひ「日本で1番、自由で面白い学校」を目指すHR高等学院を見に来ていただけたらうれしいです。
よくある質問
ここでは、通信制高校の学費無償化に関して、保護者の皆様から特によくいただくご質問にお答えします。
都道府県をまたいで通学する場合の補助金は?
都道府県独自の補助金は、原則として「保護者の住所地」がある都道府県の制度が適用されます。
例えば、埼玉県にお住まいの方が、東京都にある通信制高校に通う場合、適用されるのは埼玉県の「父母負担軽減事業補助金」です。
東京都の「授業料軽減助成金」は対象外となります。
生徒が通う学校の所在地ではなく、保護者の居住地が基準になると覚えておきましょう。
ただし、東京都は他の多くの自治体とは異なり、都内在住の生徒が都外の私立高校に通う場合でも、都の授業料軽減助成金が支援の対象となります。これは、東京都が「都内・都外の私立高校等」を対象校としているためです。大阪府も同様に、府外の私立通信制高校で、大阪府が指定する「就学支援推進校」であれば補助対象となります。これらのケースは、生徒の通学先が他の都道府県にある場合でも、保護者の居住地が制度提供元の都道府県であれば支援を受けられるという特徴的な例です。
したがって、基本原則としては保護者の居住地が基準となりますが、東京都や大阪府のように、自身の住民が県外の指定校に通う場合でも補助対象とする特別な制度を持つ自治体も存在するという点が重要です。
留年したら支援金はどうなる?
高等学校等就学支援金が支給される期間には上限があります。
通信制高校の場合、最大で48ヶ月(4年間)です。
この期間を超えて在学する場合、例えば、卒業までに5年かかったとすると、最後の1年分は就学支援金の対象外となり、授業料は全額自己負担となります。
決められた期間内に卒業を目指すことが、経済的な負担を抑える上でも重要です。
休学する場合は、事前に学校を通じて支給停止の届け出を提出することで、休学期間中は支給が停止され、支給期間のカウントも停止させることが可能です。これにより、休学が原因で卒業が延びた場合でも、期間上限に達して支援が打ち切られるのを防ぐことができます。
サポート校の学費は補助対象?
いいえ、残念ながらサポート校の学費は、国の就学支援金や都道府県の補助金の対象外です。
これらの制度は、あくまで学校教育法で定められた「高等学校」の授業料を対象としています。
サポート校は、法的には学習塾や予備校と同じ「私塾」の扱いですので、学費は自己負担となります。
この点は、資金計画を立てる上で非常に重要なポイントですので、必ず押さえておいてください。
ただし、一部の都道府県では、「通信制高校サポート校等就学支援事業」のように、独自の制度でサポート校に関する費用を一部の対象者に支援している場合もあります。
参考:通信制高校サポート校等就学支援事業補助金/長野県
大人の学び直しでも無償化できる?
高等学校等就学支援金制度は、基本的に「高校を卒業したことがない人」を対象としています。
そのため、一度高校を卒業した社会人の方が、学び直しのために通信制高校に入学した場合は、残念ながら就学支援金の対象にはなりません。
ただし、高校を中退した方が改めて高卒資格取得を目指す場合は、支援の対象となる可能性があります。
その場合も、過去の在学期間と合わせて通算48ヶ月まで、という上限が適用されます。
ただし、高校を中退した方が改めて高卒資格取得を目指す場合は、支援の対象となる可能性があります。彼らは「高等学校等を卒業又は修了していない」という条件を満たすためです。
一部の都道府県では、高校を中途退学した後に再度学び直す方を対象とした「学び直し支援金」のような独自の補助金制度も存在します(例:東京都や埼玉県の「私立高等学校等学び直し支援金」)。
その場合も、過去の在学期間と合わせて通算48ヶ月まで、という上限が適用されます。通信制高校の場合、高等学校等就学支援金の支給期間の上限は最大48ヶ月(4年間)と定められています。この期間を超えて在学する場合、その分の授業料は全額自己負担となります。また、支給対象となる単位数も卒業に必要な74単位まで、年間30単位が上限です。
HR高等学院 運営責任者からのアドバイス
ここまで、通信制高校の学費無償化制度について詳しく解説してまいりました。
多くの制度があり、少し複雑に感じられたかもしれません。
様々な支援制度を調べて、家計の負担を少しでも軽くすることは、非常に大切なことです。
しかし、私たちが日々生徒さんや保護者の皆様と接する中で、一番大切にしていただきたいと感じているのは、「その教育環境が、本当にお子様に合っているのか」という視点です。
どれだけ学費が安くても、お子様が安心して通えなかったり、学習への意欲が湧かなかったりしては、元も子もありません。
反対に、多少の費用がかかったとしても、その場所がお子様にとって「居場所」となり、自信を取り戻し、次のステップへと羽ばたいていくための大きな力になるのであれば、それは何物にも代えがたい価値のある投資となるはずです。
サポート校は、通信制高校生の学習支援だけでなく、メンタルサポートや人間関係の構築支援、生活リズムの維持など、多様な側面で生徒を支える役割を担っています。
これらのサポートは、生徒が「安心して勉学に打ち込める」ための重要な要素であり、「居場所」となり「自信と次のステップへと導く」力となります。
サポート校の費用は自己負担となるにもかかわらず、多くの生徒がサポート校を利用しているのは、その支援が学業の継続や精神的な安定、将来の自立に不可欠であると認識されているためです。生徒の個々のニーズに合わせた柔軟なカリキュラムや手厚いサポート体制は、生徒の学習意欲を引き出し、確かな進路形成を支援する可能性があります。
HR高等学院では、費用に関するご不安や疑問にも、一つひとつ丁寧にお答えしています。
「うちの場合は、どの制度が使えるの?」「結局、3年間で総額いくらくらいになるの?」といった、個別具体的なご相談も大歓迎です。
何よりもまず、お子様ご自身に、HR高等学院の雰囲気を感じていただくことが大切だと考えています。
オンラインで気軽に参加できる学校説明会や、実際のキャンパスの様子が分かる授業見学に、ぜひ一度足を運んでみませんか。
この記事が、お子様の未来を考える上での一助となれば、これほど嬉しいことはありません。
皆様の次の一歩を、心から応援しています。