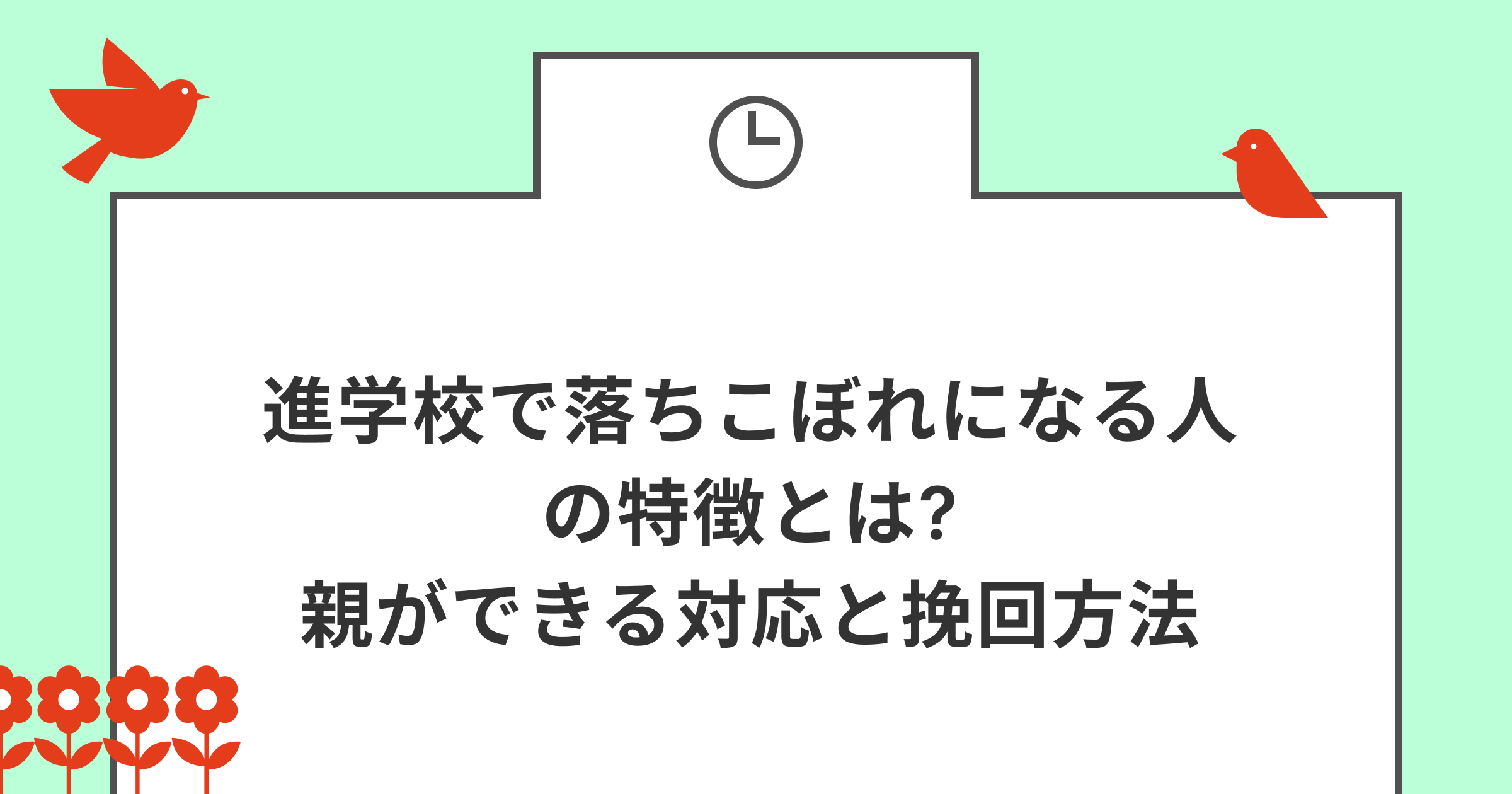「進学校に入学したけど、授業についていけない」「進路が不安だけど、どうすればよいか分からない」と悩んでいませんか?
高い目標を持って進学校に入学したはずなのに、思うように成績が上がらず、自信を失ってしまうのはとてもつらいことです。状況を改善するためには、まず自身を客観視するのが大切です。
本記事では、進学校で落ちこぼれになる人の特徴・原因や落ちこぼれになった人の末路を解説します。進学校で落ちこぼれたと感じる時の挽回の方法も解説するので、ぜひ最後までご覧ください。
進学校で落ちこぼれになる人の特徴・原因
進学校で落ちこぼれになる人の特徴・原因は、以下のとおりです。
- 進学校の勉強についていけない
- 結果が出ないためやる気がなくなっている
- 周りと比較して劣等感を抱いてしまう
- 部活や遊びなどの学業以外に熱中してしまう
- 「いつでも挽回できる」という根拠のない自信がある
- 大学受験の志望校が決まっていない
進学校で成績が振るわなかったり、授業についていけなくなったりする学生には、いくつかの共通した特徴や原因が存在します。ここでは、特徴・原因を詳しく解説するので参考にしてください。
進学校の勉強についていけない
進学校の授業は進度が速く、取り扱う内容も高度かつ広範囲です。そのため、中学時代に努力せずとも好成績を収めていた学生が、学習習慣を改善できず、落ちこぼれてしまうケースが少なくありません。
特に、数学や理科などの積み上げ型の科目では、一度理解できない単元が出てくると、その後の授業内容もどんどん分からなくなり、学習意欲自体が低下してしまいがちです。
結果が出ないためやる気がなくなっている
テストの点数やクラス内での順位が思うように上がらないと、勉強へのモチベーションを失ってしまいます。努力が結果に結びつかない経験が重なると、徐々に勉強時間が減っていき、さらに成績が下がるという負のスパイラルに陥ってしまうケースもあります。
また、基礎からコツコツと学び直すことに対して、プライドが邪魔をして抵抗感を覚えてしまう学生も少なくありません。
周りと比較して劣等感を抱いてしまう
進学校は周囲の学力レベルが高いため、自分と他者を比較して劣等感を抱きやすい環境にあります。中学時代にトップクラスの成績だった学生が進学校に入学した途端、平均以下の立場になることも決して珍しくありません。
劣等感が芽生えると、授業中に積極的に発言できなくなったり、先生や友人に質問するのをためらったりするなど、学習に対して消極的になる場合もあります。
部活や遊びなどの学業以外に熱中してしまう
進学校でなかなか結果が出ない状況が続くと、自己肯定感を得るために、学業以外の活動に熱中してしまうケースもよく見られます。
例えば、部活動に過度に時間を費やしたり、放課後や休日に遊びの時間を増やしたりして、一時的な達成感や癒しを求めがちです。
また、学業以外の活動に没頭するあまり睡眠不足に陥り、授業中の集中力低下や課題の遅れなど、二次的な問題が生じる場合もあります。
「いつでも挽回できる」という根拠のない自信がある
「テスト前に勉強すれば大丈夫だろう」「いつでも挽回できるはずだ」と安易な思い込みから、日々の学習をおろそかにしてしまい、進学校の落ちこぼれになるケースも見受けられます。
また、落ちこぼれてしまった際に、学習の遅れを短期間の詰め込みで取り戻そうとする学生もいます。しかし、進学校で求められる学習量は中学時代とは比較にならないほど多いため、継続的かつ計画的な学習習慣がなければ、成績を向上させられないでしょう。
大学受験の志望校が決まっていない
「大学に進学する」と漠然とした目標を持っているだけで、具体的にどの大学・学部を目指すのかが定まっていないと、モチベーションは維持できません。
また、親や学校の期待に応えるため、あるいは周りの雰囲気に流されているなど、本心で納得しないまま無理に勉強を続けている場合も同様です。
自分自身の将来の展望と学習内容とが結びつかなければ、学習への主体性や意欲が上がりにくい状況に陥ってしまいます。
進学校で落ちこぼれになった人の末路
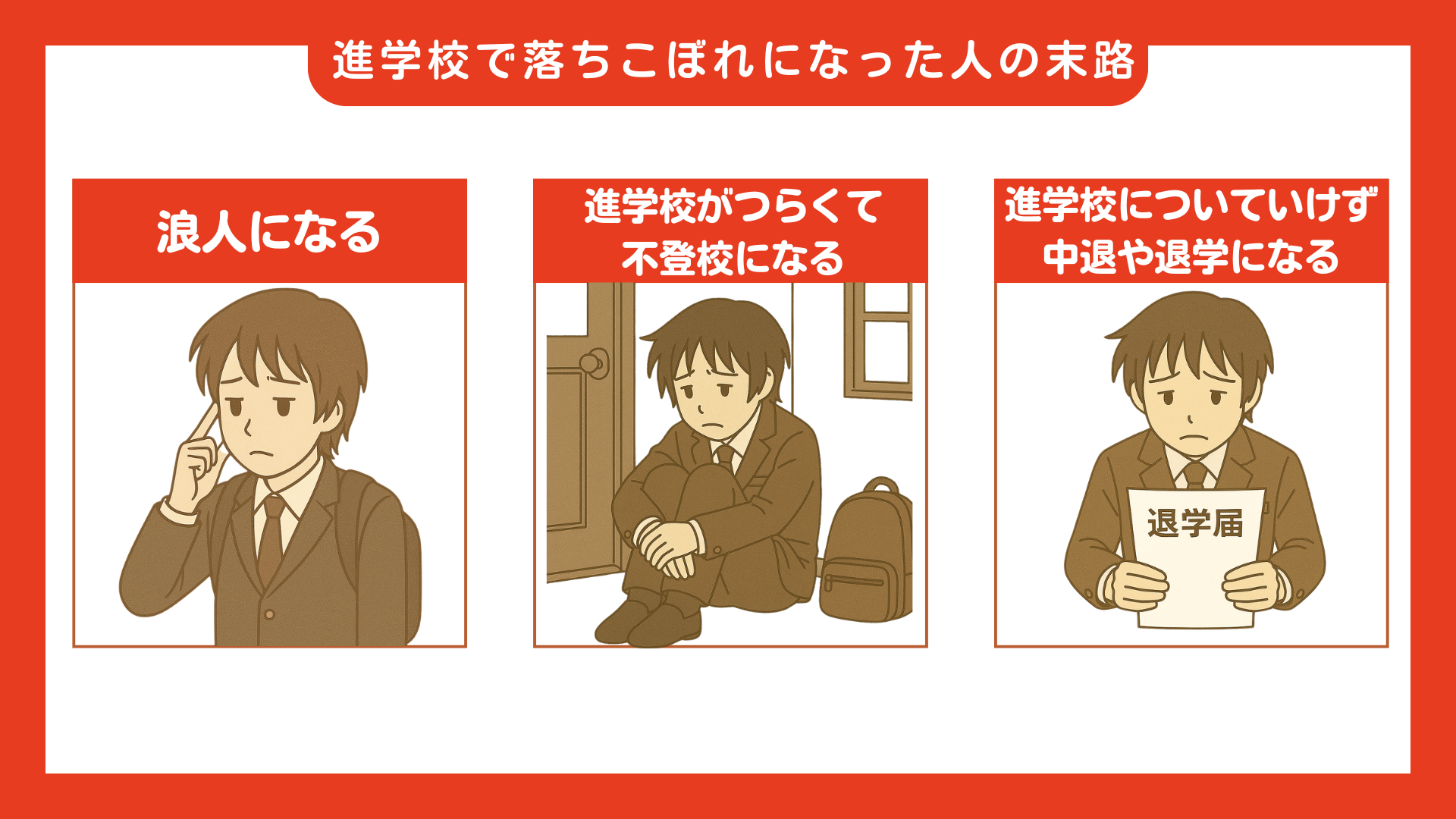
進学校で落ちこぼれになった人の末路は、以下のとおりです。
- 浪人する
- 進学校がつらくて不登校になる
- 進学校についていけず中退や退学になる
進学校で落ちこぼれになった場合、必ずしも悲観的な未来が待っているわけではありませんが、どのような状況になり得るのかを理解しておくのは大切です。
浪人する
進学校在学中に十分な学力を身につけられなかったものの、当初掲げていた志望校への進学を諦めきれず、浪人生活を選択する学生は少なくありません。
浪人生活自体が悪いわけではありませんが、高校時代の学習習慣や勉強方法の問題点を改善しないままでは、期待する結果を得られない可能性が高まります。
また、浪人生活中の経済的な負担や先の見えない不安、精神的なプレッシャーを乗り越えて目標を達成するのは決して簡単なことではないでしょう。
進学校がつらくて不登校になる
勉強についていけず成績の低迷が続くと、学校へ行くこと自体が苦痛になり、不登校になってしまうケースもあります。
朝起きられない、気分が優れないなどの身体的な症状が現れ始めたのち、適応障害やうつ病に発展してしまう場合もあります。
不登校状態が長期化すると学習の遅れが一層深刻になるだけでなく、人間関係が希薄になったり、社会性の発達が遅れたりする可能性も否定できません。
進学校についていけず中退や退学になる
成績不振で留年の可能性が高まったり、不登校で出席日数が不足したりして、最終的に高校を退学してしまうケースもあります。高校中退の経験は心理的なダメージが大きく、のちの人生に悪影響を与えてしまう可能性も考えられます。
別の高校に転入・編入するのも一つの選択肢ですが、全日制高校への転入・編入はハードルが高いのが一般的です。
なお、文部科学省の調査では、高校を中途退学した理由として「学業の不振」を挙げた学生は全体の6.6%とされています。
参考:文部科学省|令和3年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果
「社会で生きていける力」を。
- 入学前不登校経験者8割。
入学後登校率89% - ぷよぷよ、モンスト開発者、
日本一になった起業家
から直接学べる - docomo、Lotte、Mixiなど
大企業と連携したプロジェクト型学習

進学校で落ちこぼれたと感じる時の挽回の方法
進学校で落ちこぼれたと感じる時の挽回の方法は、以下のとおりです。
- 苦手分野を克服する
- 受験勉強に一点集中する
- 教員やスクールカウンセラーに相談する
- 外部の塾や家庭教師などを活用する
進学校で落ちこぼれても適切な対策と努力を続ければ、状況を好転させることは十分可能です。ここでは、具体的な挽回方法をいくつか紹介します。
苦手分野を克服する
まずは、どの科目のどの分野が理解できていないのかを正確に分析するのが大切です。苦手分野が特定できたら、基礎的な内容に立ち返って、焦らずにじっくりと学び直しましょう。
例えば、英語が苦手なのであれば、基本的な英単語や英文法のルールを徹底的に復習し、徐々に長文読解や英作文などの応用的な学習に進んでいくアプローチが効果的です。
基礎学習をおろそかにしたままでは、いくら応用問題に取り組んでも成績向上は望めません。
受験勉強に一点集中する
もし、部活動や趣味、アルバイトなど学業以外の活動に多くの時間を費やしているのであれば、それらを一時的に中断して、学習時間を確保することを検討しましょう。
特に、高校2年生以降は大学受験を見据え、志望校合格に必要な科目の選択と各科目への時間配分を意識した学習計画を立てる必要があります。
「志望校に合格するためには、どの科目をどのレベルまで上げる必要があるのか」「どのような参考書や問題集を何冊程度こなす必要があるのか」などを明確にした上で、受験勉強に集中しましょう。
教員やスクールカウンセラーに相談する
自分一人で悩みを抱え込まず、積極的に周囲の大人に相談する姿勢も大切です。学校の先生は生徒の成績向上をサポートしてきた経験が豊富なため、各学生の状況に合わせた的確な学習アドバイスをしてくれるはずです。
また、学習面だけでなく精神的な負担を感じている場合は、スクールカウンセラーに相談することも検討しましょう。メンタルの専門家であるスクールカウンセラーに相談すれば、悩みや不安に寄り添いながら、問題解決に向けた手助けをしてくれます。
外部の塾や家庭教師などを活用する
学校の授業だけではどうしても理解が難しい場合や、より個別化された学習サポートが必要だと感じる場合は、塾や家庭教師などを活用するのも効果的です。
個別指導塾やマンツーマン指導の家庭教師であれば、自分の学力レベルや理解度、目標に合わせて指導を受けられるため、苦手な部分を集中的に克服したり、得意な部分をさらに伸ばしたりできます。
集団指導の塾でもレベル別にクラスが編成されているため、状況に合った環境で学習を進められるでしょう。
「進学校で落ちこぼれている」と親が感じた時のNGな対応
「進学校で落ちこぼれている」と親が感じた時のNGな対応は、以下のとおりです。
- 落ちこぼれたことを責める
- 親が何かしようと積極的に動く
子どもが進学校で思うように成績が上がらない場合、親として心配になるのは当然のことですが、対応を誤ると状況を悪化させてしまうかもしれません。ここでは、親が避けるべきNGな対応を解説します。
落ちこぼれたことを責める
進学校で子どもの成績が下がったときは「なぜもっと勉強しないのか」「このままではあなたの将来が心配だ」と、感情的に責めてしまいがちです。しかし、一方的に責めるような態度は、子どもの自己肯定感を低下させ、勉強へのモチベーションを奪ってしまう原因になりかねません。
また、「あなたならできるはずだ」といった言葉も過度なプレッシャーを与え、子どもが期待に応えられない自分を責めてしまうきっかけになるため、避けるべきです。
親が何かしようと積極的に動く
子どもの成績が下がると親としては焦りを感じるため、「すぐに塾に通わせなければ」「スケジュールを細かく管理しよう」など、積極的に介入してしまいがちです。しかし、子どもの意思や気持ちを無視した一方的な行動は、かえって反発を招き、状況を悪化させる可能性があります。
特に、思春期は自律性や自己決定の欲求が強まる時期であり、親の過干渉な言動は「自分を信頼してもらえていない」「自分のことは自分で決めたいのに」と不信感やフラストレーションの増加につながります。そのため、まずは子どもの気持ちに寄り添い、本人の考えを聞いた上で改善策を講じる姿勢が必要です。
「進学校で落ちこぼれている」と親が感じた時にすべき対応
「進学校で落ちこぼれている」と親が感じた時にすべき対応は、以下のとおりです。
- 現状の学力を知り、目標を一緒に考える
- 勉強ができる環境を整える
- 頼まれごとや相談を受けるまで見守る
- 普段のコミュニケーションを増やす
- 子どもの味方になって信じる
- 進学校へのこだわりを無くし新しい選択肢を模索しておく
子どもが進学校で落ちこぼれてしまった場合は、焦らずに一つひとつ問題を解決していく意識が必要です。ここでは、状況を好転させるために親御さんが取るべき対応を詳しく解説します。
現状の学力を知り、目標を一緒に考える
テストの点数や成績の順位など表面的な結果だけを見るのではなく、具体的にどの科目のどの分野でつまずいているのか、子どもと一緒に考えましょう。その後、現状の学力から少しずつステップアップできるよう、現実的な学習目標を設定してください。
ただし、高すぎる目標は挫折感を増幅させる可能性があるため避けるべきです。また、子どもが本当に興味を持っている分野や、将来どのような道に進みたいのかなどについて話し合い、内発的なモチベーションを引き出すのもよいでしょう。
勉強ができる環境を整える
子どもが勉強に集中できる環境を整えるのも大切です。例えば、落ち着いて勉強に取り組める学習スペースを確保したり、必要な参考書や問題集を揃えたりして、子どもの学習効率を高めてあげましょう。
また、スマートフォンやゲーム機など勉強の妨げになり得るものの使用ルールは、一方的に禁止するのではなく、子どもと話し合った上で決めることを推奨します。
あまりにも厳しすぎるルールを強制すると、反発を招き逆効果になる恐れがあるため、子どもの自主性を尊重しながら、合理的なルールづくりを心がけましょう。
頼まれごとや相談を受けるまで見守る
親が常に先回りしてすべての問題を解決してしまうのではなく、ときには辛抱強く見守る姿勢も必要です。子どもから「この問題の解き方が分からない」「こういう参考書が欲しい」など、具体的な相談や頼みごとを受けてから手を差し伸べるようにすると、子どもの主体性や問題解決能力を育めます。
また、「何か困ったことがあれば、いつでも相談してね」と定期的に声をかけ、子どもが気軽に相談できる雰囲気を作っておくのも大切です。
普段のコミュニケーションを増やす
学校での出来事や友人関係、興味のあることなど気軽に話し合えるよう、普段からコミュニケーションを増やしておくのも大切です。
進学校は成績や進路に対する不安や悩みを感じやすい場所です。親が日頃から子どもの話に耳を傾け、共感する姿勢を示しておけば、子どもは安心して自分の不安や悩みを打ち明けられるようになります。
子どもの味方になって信じる
親から信頼されることは、子どもにとって精神的な支えとなり、困難な状況を乗り越えていくための原動力を生み出します。また、成績の良し悪しにかかわらず、努力や成長の過程を認める姿勢を示すことが子どもの自己肯定感を育みます。
子どものポテンシャルを引き出すためには、小さな進歩でも積極的に褒め、失敗を責めるのではなく次への学びとして捉えてあげる意識が大切です。
進学校へのこだわりを無くし新しい選択肢を模索しておく
学校がどうしても合わない、あるいは耐え難い精神的負担となっている場合は、今の環境に固執するのではなく、環境を変える選択肢も持っておくべきです。
すべての学生が進学校の高い学習ペースや競争的な環境に適応できるわけではありません。また、一般的な全日制高校や通信制高校で才能が花開くケースも決して少なくありません。
親としてもっとも大切なのは「進学校を辞めること=失敗」という固定観念から脱却し、子どもが心身ともに健康で、能力を発揮できる学びの場を見つけてあげることです。
なお、高校を転校する際の手続きの仕方や流れを詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。
「社会で生きていける力」を。
- 入学前不登校経験者8割。
入学後登校率89% - ぷよぷよ、モンスト開発者、
日本一になった起業家
から直接学べる - docomo、Lotte、Mixiなど
大企業と連携したプロジェクト型学習

通信制高校サポート校「HR高等学院」をご紹介
Youtubeチャンネル HR高等学院の非常識な職員室より
出演者:山本将裕(株式会社RePlayce 代表取締役CEO)
:成田修造(起業家、エンジェル投資家)
学校での偏差値よりも、社会での可能性を - HR高等学院
HR高等学院は従来の詰め込み型の教育ではなく、「探究・越境・共創」を掲げた独自のカリキュラムを採用している通信制高校サポート校です。
企業と連携したプロジェクト型学習や専門ゼミ、各界の最前線を走る講師(トップランナー)などを通じて、以下の能力を養います。
- 課題解決力
- 論理的思考力
- コミュニケーション力
HR高等学院の名物授業、「トップランナーセッション」にて、登録者148万人『ReHacQ』のプロデューサー高橋弘樹さんを講師にお呼びした際の講義です。HR高等学院では、様々な業界の第一線で活躍されている社会人を講師に迎え、多様な生き方、キャリアの築き方を学生と一緒に考えたり、学生たちからの等身大の質問に答え直接対話を行う授業を日々行っています。
HR高等学院では自宅でのオンライン学習と校舎での通学学習を自由に組み合わせできるのが特徴です。
また、学生一人ひとりに寄り添う個別サポートが充実している点も本校の魅力です。
最後に
進学校で落ちこぼれてしまう可能性は誰にでもあります。落ちこぼれてしまったと感じる場合は、まず原因を正しく把握することから始めましょう。
一人で悩みを抱え込まずに、親や先生、スクールカウンセラーと協力しながら状況を改善していく意識が大切です。また、「進学校を辞めること=失敗」という固定観念は捨てて、環境を変える選択肢も持ち合わせておくべきです。
もし、「自分らしく学びたい」「将来の夢を見つけたい」という場合は、通信制高校サポート校への入学もご検討ください。通信制高校サポート校の「HR高等学院」では、学生一人ひとりの希望や個性に合わせた学習サポートやコーチングを提供しています。
HR高等学院は「日本でいちばん自由で面白い学校」を目指しています。
資料請求や授業見学、説明会など、いつでもお待ちしております!