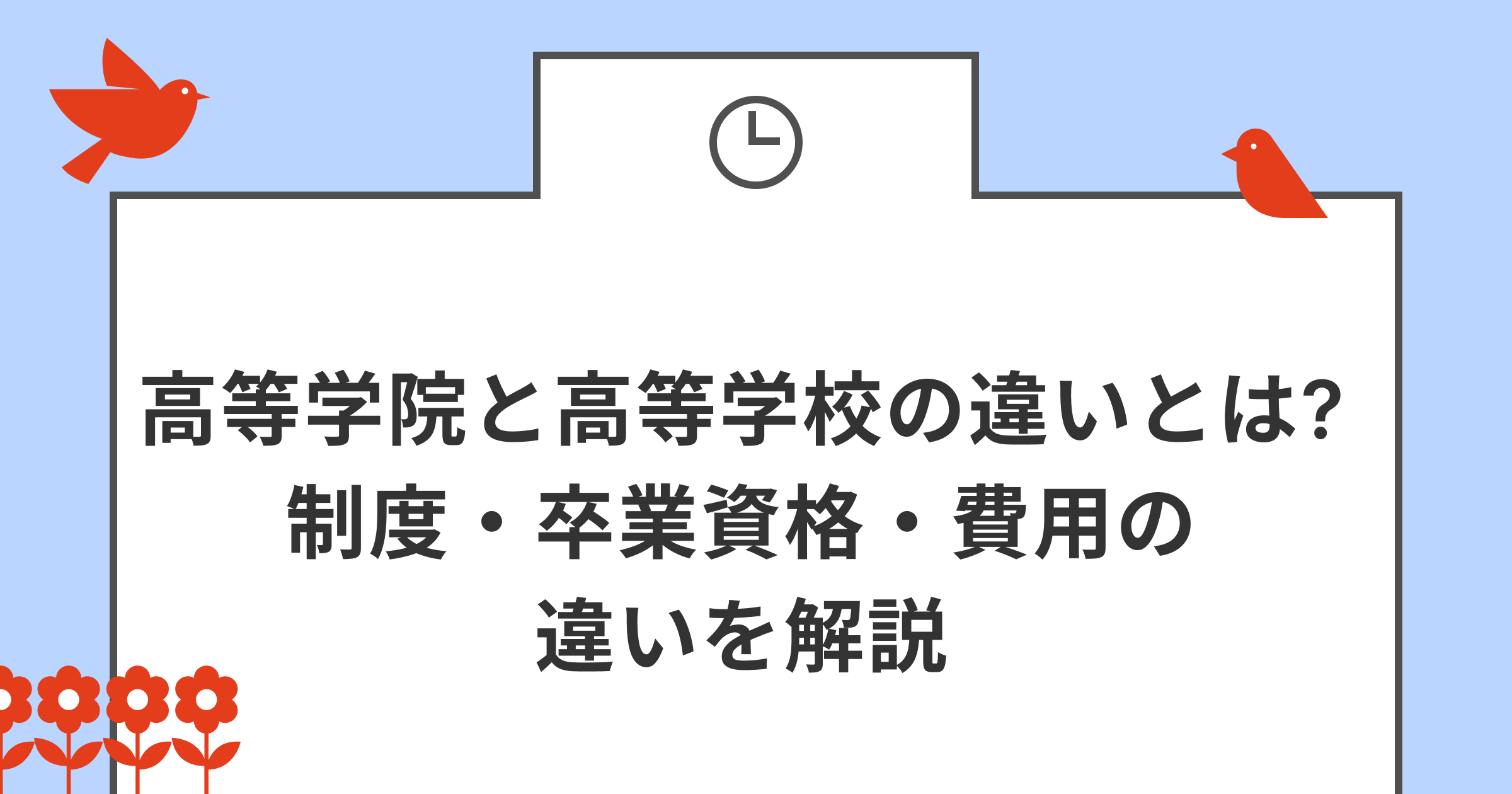高等学院と高等学校は、どちらも高校卒業を目指せる教育機関ですが、制度や運営母体、学び方に違いがあります。 「高等学院」とは、通信制高校と連携し、学生を支援する民間のサポート校に広く使われている名称です。
この記事では、高等学院と高等学校の卒業資格取得方法、費用、サポート体制などの違いをわかりやすく解説します。
「高等学院と高等学校の違いを知りたい」「自分や子どもに合う学校を選びたい」方に役立つ内容です。ぜひ、最適な進路選択の参考にしてください。
高等学院とは?通信制高校と連携する民間サポート校の名称
「高等学院」という言葉は、通信制高校と連携し、学生の学習や生活をサポートする民間教育機関で使われることが多い名称です。「高等学院」には以下の特徴があります。
- 通信制高校と連携して学生の学習・生活を支援する役割
- 「サポート校」とも呼ばれる民間の教育機関
- 通信制高校だけではカバーしきれない多様な課題をフォロー
通信制高校では、自分のペースで学べる一方、卒業率や進路決定率の低さ、社会性を育む機会の不足といった課題もあります。
高等学院では、自己管理が求められる学習計画のサポートや精神的なケア、あるいは社会で活躍するためのスキル習得まで、通信制高校だけでは対応しきれない面を補います。
高等学校(公立・私立高校)とは?
高等学校には全日制・定時制・通信制がありますが、ここでは一般的に広く知られる週5日登校の全日制高校の特徴をベースに解説します。
全日制高等学校の主な特徴は次の通りです。
- 文部科学省認可の正式な高等学校で公立・私立がある
- 高校卒業資格が取得できる
- 週5日登校し、時間割に沿って授業を受ける
- 学校行事や部活動が充実している
全日制高校では、学習だけでなく、友人や先生との関わりを通して協調性や社会性を身につけることも重視されます。
規則的な登校や集団生活を通じて、学力と社会性をバランスよく伸ばせる教育環境です。
「社会で生きていける力」を。
- 入学前不登校経験者8割。
入学後登校率89% - ぷよぷよ、モンスト開発者、
日本一になった起業家
から直接学べる - docomo、Lotte、Mixiなど
大企業と連携したプロジェクト型学習

高等学院と高等学校の違い
高等学院と高等学校の違いを以下の観点からわかりやすく解説します。
- 高校卒業資格の取得
- 運営体制
- 学費の違い
高校卒業資格の取得
高等学院に通う学生は、提携する通信制高校に在籍し、その通信制高校の卒業要件を満たすことで、卒業資格を取得します。
一方で、全日制高校に通う学生は、その高校に直接在籍し、学校が定める卒業要件を満たすことで、卒業資格を取得します。
運営体制
高等学院は主に学校法人や民間企業が運営しています。一方で、公立・私立の高等学校は自治体や教育委員会、私立学校法人によって運営されており、公的な管理体制のもとで教育活動が行われています。
学費
高等学院と全日制高等学校の学費の相場は以下です。
※国の就学支援金適用の場合
高等学院≒通信制高校連携のサポート校では、通信制高校の授業料は就学支援金の範囲内でほぼ無料となりますが、サポート校としての費用が別途必要なため、全日制高校より学費が高くなる傾向があります。
また、サポート校の学費は通学日数や学校の運営体制などにより大きく幅があります。
一方で、全日制高校は2026年度から就学支援金により授業料が公立・私立ともに実質無償化され、自己負担は教材費や制服代などの諸費用のみとなります。
高等学院のメリットとは?通信制高校と連携する支援機関の強み
ここでは、民間教育機関ならではの高等学院のメリットを詳しく紹介します。
- 自分のペースで学習ができる
- 進路サポートが充実している
- 不登校や登校拒否の学生のサポートがある
自分のペースで学習ができる
高等学院では、通学日数や学習の進度を自分で調整できます。オンライン授業やレポート提出を中心に学ぶことが可能です。
さらに、サポート校の専任スタッフが定期的に面談を行い、学習計画やモチベーションの維持を丁寧に支援するため、1人で通信制高校に通うよりも計画的に学習を進めやすくなっています。
進路サポートが充実している
高等学院も全日制の高等学校と同様に、大学進学や就職など、多様な進路の選択が可能です。個別の進路相談、大学の入試対策、就職活動の面接練習など、通常の通信制高校では手薄になりがちな部分をしっかりカバーします。
少人数制のため、1人1人の希望に合わせた細やかなサポートが受けられるのも大きなメリットです。
不登校や登校拒否の学生のサポートがある
体調不良や心理的な不安があっても、通学日数を柔軟に調整できるため、無理せず通学を続けられます。
加えて、カウンセラーや専門スタッフによるケアも充実しており、不登校経験のある学生も安心して学べる環境が整っています。
高等学校=通信制高校のメリット
高等学校の中でも、通信制高校は柔軟な学び方ができる選択肢です。ここでは、通信制高校のメリットを紹介します。
- 将来の選択肢が増える
- 学校生活を楽しむことができる
- 社会性や協調性を養える
将来の選択肢が増える
通信制高校を卒業すれば高校卒業資格が得られるため、大学や専門学校への進学や就職など、全日制の高等学校と同じ進路が選べます。
また、働きながらや、資格取得と並行して学びたい人にとっても、無理のないスケジュールで卒業を目指せる点は大きな強みです。
学校生活を楽しむことができる
多くの通信制高校では、スクーリングやイベント、部活動などを通じて、仲間と交流できる場も用意されています。 登校日数は少ないながらも、学生同士のつながりや学校行事を通じて、高校生活らしい経験をすることも可能です。
社会性や協調性を養える
グループワークやオンラインでの対面授業を通じて、社会性や協調性を身につける機会も設けられています。
特に、定期的な登校を取り入れている学校では、コミュニケーション力や対人スキルなど、社会に出るうえで必要な力を自然に身につけることができます。
高等学院=民間の教育施設だからこそできる新しい教育
全日制高校の多くは、学校教育法に基づく教育スタイルを採用しており、大きな変化が生まれにくいのが現状です。一方で、民間が運営する高等学院は、法的な制約が少ない分、柔軟かつスピーディに教育内容をアップデートできる強みがあります。
社会の急速な変化に対応し、AI・グローバル化・キャリア教育などの最先端の学びを積極的に取り入れられるのは、民間ならではのメリットです。
実際、こうした柔軟な教育のニーズは年々高まり、通信制高校に通う学生数の増加とともに、それを支えるサポート校の重要性も増しています。
現在では全国に多くのサポート校が存在しますが、その中でも特に独創的な教育方針で注目を集めているのが、2025年4月に開校した「HR高等学院」です。
HR高等学院では、探究的な学びや現代的教養に力を入れています。設立者の山本将裕氏は、中高生向けキャリア探究サービス「はたらく部」を手がけてきた人物で、そのノウハウを活かして教育を展開しています。
一例として、開校初日の入学式では、学校とHR高生が対決する構図でミッション形式のイベントが行われました。最初は人前で話すことをためらっていた学生たちが、数時間後には自分のアイデアを堂々と発表したり、保護者や友人に積極的に話しかけたりするなど、たった一日でも大きな変化が見られました。
また、起業家や市長、人気YouTubeチャンネルのプロデューサーなどと対話できる「トップランナーとの対話型学習」も魅力の一つです。
最近では、人気YouTubeチャンネル「ReHacQ」のプロデューサー・高橋弘樹氏を招いた授業が行われました。学生の質問に対して想定外の返答や、価値観を揺さぶる話があり、リアルな社会の視点に触れる貴重な機会となりました。
こちらがその時の様子です。
このようなリアルな学びをさらに深めるために設計されているのが、独自のカリキュラムです。ビジネスやテクノロジー、デザイン、ソーシャル、グローバルの5つの領域から、自分の興味に応じて学びを選択できるため、個性や得意を活かし、主体的に学習を深めることが可能です。
このように、HR高等学院では1人1人の個性を起点に、社会とつながりながら学ぶ仕組みを数多く整えています。
教科書だけにとらわれない「生きた学び」と、自分の未来を自ら切り開く力を育む独創的な教育環境は、他の通信制高校やサポート校とは一線を画しています。
「社会で生きていける力」を。
- 入学前不登校経験者8割。
入学後登校率89% - ぷよぷよ、モンスト開発者、
日本一になった起業家
から直接学べる - docomo、Lotte、Mixiなど
大企業と連携したプロジェクト型学習

通信制高校サポート校「HR高等学院」をご紹介
HR高等学院は、通信制高校と提携し、学生の学びや生活を支援する民間のサポート校として運営されています。連携高校の卒業要件を満たすことで、高校卒業資格が取得できます。
・学生主体の学びを実現
・学力や出席日数を問わない入学選考
・オンラインのみや週5通学まで選べる自由な学習スタイル
・実社会を生き抜く力を養う企業と連携した授業
・学びの伴走者による手厚い学習サポート
・多様な進路対応
全日制の高等学校のように毎日登校するスタイルではなく、自宅からのオンライン学習や、週1回〜5回までの通学スタイルを自由に選べるのが大きな特徴です。
入学選考では過去の出席状況や学力は問われないため、これまでの経歴に関係なく誰でも新しい一歩を踏み出せます。
学習内容にも独自性があり、企業と連携したプロジェクトや専門ゼミを通じて、実社会と直結する体験型の学びが得られます。たとえば「企業連携PBL」では、MIXIやロッテなどの大手企業と商品開発に取り組み、社会で役立つ実践力を身につけていきます。
さらに、1人1人に「キャリア探究コーチ」が担当としてつき、月2回の個別面談を行います。勉強の悩みだけでなく、進路や生活面の不安にも丁寧に寄り添い、学びの伴走者として支えてくれる存在です。
進路の選択肢も幅広く、国内外の大学進学、就職、起業といったそれぞれの目標に応じたサポート体制が充実しています。特に、世界大学ランキング上位校への推薦枠もあるため海外の大学への進学も十分に可能です。
専任の進路サポーターが進路選択から受験対策まで1人1人手厚く支援します。
進路や学びを「決められる」のではなく「自分で選べる」。その実感と自由がここにはあります。
ぜひ体験会に参加して他のサポート校との違いや実際の雰囲気を体感してください。まずは一歩踏み出してみることが大切です。
学校概要の詳しい説明や学生のインタビューは、以下の動画でも紹介していますのでぜひご覧ください。
最後に
高等学院と高等学校には、教育の目的や方法、サポート体制において大きな違いがあります。高等学院は、通信制高校と連携しながら、学生1人1人の個性や状況に合わせた柔軟な学びを実現できる点が大きな魅力です。
HR高等学院のような通信制高校サポート校では、不登校経験があったり、学校に馴染めなかったりした学生でも、自分のペースで学び直し、多様な進路選択が可能です。
現代は、高等学校という枠にとらわれず自分に合った学び方を選ぶ時代です。この記事を通じて、高等学院≒通信制高校連携の民間教育施設という新しい選択肢を知り、興味を持たれた方は、ぜひ各校の授業見学や説明会に参加してみてください。