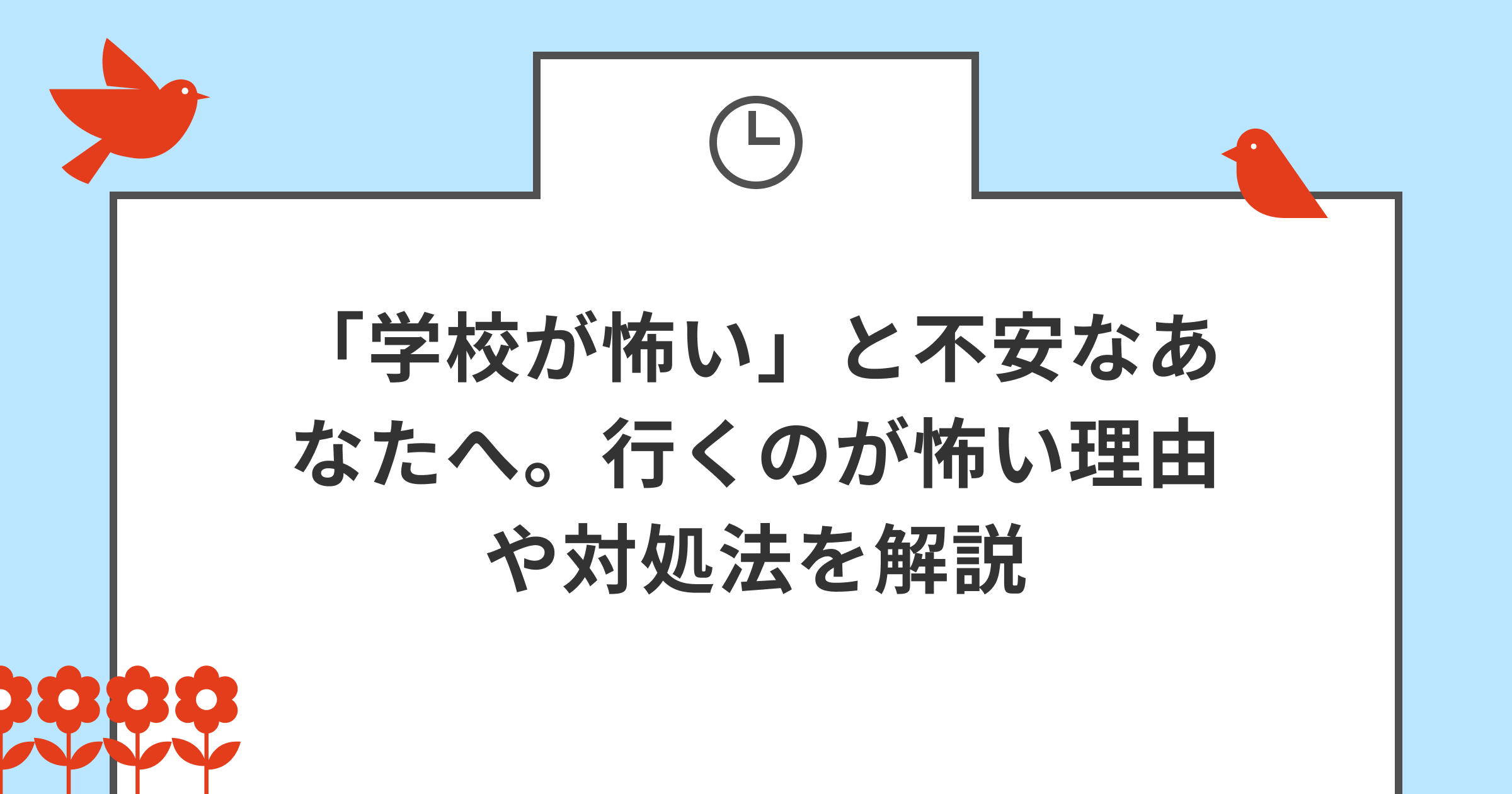「学校に行くのが怖い」「教室に入るのが怖い」と一人で悩んでいませんか?
もし、学校生活に対して不安や辛さを感じているのであれば、その気持ちを放置しておくべきではありません。学校が怖いと感じる理由を明確にできれば、状況を改善できる可能性は十分にあります。
本記事では、学校が怖いと感じる理由と対処法を詳しく解説します。学校が怖いと言われた時にすべき親の対応も紹介するので、ぜひ最後までご覧ください。
「学校が怖い」と感じるのは悪いことではない
「学校が怖い」と感じるのは、決して恥ずかしいことでも、心が弱いわけでもありません。
文部科学省が令和5年に実施した調査によると、高校の不登校生徒数は68,770人にも上るとされています。つまり、学校に対して違和感を覚えたり、不安を感じたりするのは、誰にでも起こりうることです。
大切なのは自身の感情を否定せず、なぜそう感じるのかを理解することです。原因を明確にした上で対処すれば、辛い状況を変えられる可能性は十分にあります。
参考:文部科学省 令和5年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果の概要
「学校が怖い」を放置しておくのは良くない
学校への恐怖心を抱えたまま登校を続けるのは、心身に大きな負担を与えます。無理に登校を続けていると、授業に集中できないだけでなく、人間関係もうまくいかず、ますます学校が怖い場所になってしまいます。
また、不登校になり家に引きこもる生活が長引くと、学習の遅れが生じたり、社会性を身につける機会が失われたりもするでしょう。
学校が怖いと感じている場合は思い詰めるのではなく、環境の調整や転校など、さまざまな解決策が存在すると知っておくべきです。
「社会で生きていける力」を。
- 入学前不登校経験者8割。
入学後登校率89% - ぷよぷよ、モンスト開発者、
日本一になった起業家
から直接学べる - docomo、Lotte、Mixiなど
大企業と連携したプロジェクト型学習

「学校に行くのが怖い」「教室に入るのが怖い」と感じる理由
「学校に行くのが怖い」「教室に入るのが怖い」と感じる理由の例は、以下のとおりです。
- 勉強・授業についていけない
- 教室やクラスメイトにうまく馴染めていない
- 友人や先輩との関係がうまくいっていない
- 先生との相性が悪い
- 親子関係がうまくいっていない
- 学校の規則やルールなどの環境が合っていない
- 発達障害などの可能性がある
学校が怖いと感じる理由は、人それぞれです。また、人間関係の悩みや成績に対する不安など、複数の要因が絡み合っているケースも少なくありません。具体的な対処法を見つけ出すためには、まず自分が学校を怖いと感じる理由を特定するのが大切です。
勉強・授業についていけない
授業の内容が難しくて理解できない、テストの点数が思うように上がらないなど、学業に対する不安が学校への恐怖感につながっている場合も珍しくありません。
真面目で向上心の強い学生ほど、学業不振に対して強いストレスを感じやすく、周囲の評価を気にし過ぎる傾向があります。勉強・授業についていけない状況が続くと「自分はこの学校にいるべきではない」と疎外感を感じてしまう場合もあります。
教室やクラスメイトにうまく馴染めていない
進級や転校などで環境が大きく変わったタイミングで、教室の雰囲気やクラスメイトの輪に馴染めない場合も、学校が怖いと感じてしまいがちです。
また、クラスの中に個性の強い生徒やグループが存在する場合、その場の空気に圧倒されてしまい、自分らしさを出せず委縮してしまうケースもあります。
文部科学省の調査によると、不登校の原因のうち「いじめを除く友人関係をめぐる問題」が約1割を占めています。
参考:文部科学省 | 令和3年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果
友人や先輩との関係がうまくいっていない
人間関係のトラブルが原因で、学校が怖くなっている学生も少なくありません。近年では、スマートフォンやSNSの普及などにより、以前とは違った形で人間関係のトラブルが生じるケースも増えています。
また、一度人間関係のトラブルを経験すると、たとえ問題が解決しても「また同じようなことが起きたらどうしよう」と恐怖心やトラウマにとらわれてしまう可能性もあります。
先生との相性が悪い
先生との相性が悪いことも、学校が怖いと感じる原因になり得ます。例えば、特定の先生から厳しい言葉で叱責されたり、高圧的な態度で接されたりすると、先生に対してだけでなく学校生活全般に不安や恐怖を抱いてしまうでしょう。
また、先生との相性が悪いと質問や相談がしにくいため、成績が落ちてしまい、学業へのモチベーションが低下してしまう恐れもあります。
親子関係がうまくいっていない
親からの過度な期待やプレッシャー、学業成績に関する厳しい要求は、学生に大きなストレスを与える可能性があります。「良い成績を取らなければならない」「失敗は許されない」などのメッセージを受け続けると、学校に対して恐怖や不安を感じるようになるでしょう。
また、親が過干渉の場合、子どもが精神的に自立する機会を奪ってしまいます。逆に、親子関係が希薄過ぎて悩みを相談できない場合も、子どもは悩みを一人で抱え込み、学校に対して恐怖を感じてしまうでしょう。
学校の規則やルールなどの環境が合っていない
学校の厳格な規則や集団行動重視の文化、画一的な教育方法が、大きなストレスになっているケースもあります。「みんなと同じでなければならない」という同調圧力に対して苦痛を感じる学生も少なくありません。
また、感覚過敏の特性を持つ生徒の場合、教室の刺激(広い空間、話し声、照明の明るさなど)が多すぎるのがストレスになることもあります。環境に起因する問題は個人の努力だけでは解決しにくいため、さらに状況を悪化させてしまいがちです。
発達障害などの可能性がある
発達障害の特性を持つ学生は、通常の学校環境に適応するのが難しい傾向があります。例えば、ADHD(注意欠如・多動症)の学生は長時間座っていたり、集中力を維持したりするのが困難なため、従来の授業スタイルになじめないことがあります。
また、ASD(自閉スペクトラム症)の特性がある場合は、暗黙のルールが理解できずに、人間関係やコミュニケーションに苦手意識を持ってしまいがちです。
発達障害の特性を持つ学生が適切な支援を受けられないまま学校生活を送ると、日々のストレスが蓄積し、学校そのものが怖い場所になってしまうでしょう。
教室に入るのが怖い場合はどうしたらいい?
教室に入るのが怖い場合に取るべき行動は、以下のとおりです。
- 安心できるルーティンを作る
- 保健室などの教室以外の場所から慣れる
もし、教室に入るのが怖いと感じているなら、無理に登校しなくても大丈夫です。大切なのは、短期間で状況を改善しようと焦るのではなく、自身のペースで少しずつ学校に対する恐怖心を和らげていくことです。
ここでは、教室に入るのが怖い場合に取るべき行動を詳しく解説します。
安心できるルーティンを作る
毎朝の準備から登校までの流れを一定にすると、日々の行動に予測可能性が生まれ、漠然とした不安を軽減できます。
例えば、以下の行動を細かく計画し、毎日繰り返してルーティン化するのがおすすめです。
- 朝起きる時間
- 朝食の内容
- 家を出る時間
- 学校までの道のり
- 学校に着いてから最初にする行動(特定の先生に挨拶をする、保健室に立ち寄るなど)
登校前に深呼吸や軽いストレッチ、マインドフルネスなどのリラクゼーション技法を取り入れるのも、不安を軽減するのに役立ちます。
また、小さなことから成功体験を積み重ねていけば、徐々に自信がつき、学校に対する恐怖心は和らいでいくでしょう。
保健室などの教室以外の場所から慣れる
多くの学校では、メンタルが不安定になっている学生のために、別室登校の制度を整えています。どうしても教室に入るのが怖いと感じる場合は、無理に教室へ行こうとせず、保健室や相談室、図書室など比較的安心できる場所から学校に慣れていくのもよいでしょう。
保健室では養護教諭が、相談室ではスクールカウンセラーが、各学生の状況に合わせたサポートを提供してくれるので安心です。また、別室登校を続けるうちに、同じような悩み・境遇を持つ学生と仲良くなれる可能性もあります。
「学校が怖い」と感じる気持ちを和らげる対処法
「学校が怖い」と感じる気持ちを和らげる対処法は、以下のとおりです。
- 学校が怖い理由を一緒に考える
- 一人で抱え込まないようにサポートする
- 学校以外の落ち着く居場所を探す
学校が怖いと感じる気持ちは、さまざまな要因が絡み合って生じます。恐怖感を少しずつ和らげていくには、固定概念にとらわれずに、多角的なアプローチを心がけるべきです。
また、自分一人で悩みを抱え込まず、親や先生たちと協力しながら、状況を改善していく意識を持つのも大切です。ここでは、学校に対する恐怖感を和らげる方法を解説します。
学校が怖い理由を一緒に考える
学校が怖いと感じる気持ちに向き合うためには、まずその理由を明確にするのが大切です。ただし、メンタルが弱っているときに、原因を言語化するのが難しい場合も多いため、親子で一緒に考えましょう。
「学校のどんな場面で不安を感じやすいか」「どんな状況になったら学校に行けそうか」と一つひとつ確認していけば、問題の核心に近づけます。
また、日記をつけたり、絵を描いたりなど、非言語的な方法で感情を表現するのもおすすめです。言葉にできない気持ちでも別の形で表現すると、問題を客観的に把握できる可能性があります。
一人で抱え込まないようにサポートする
学校が怖いと感じる気持ちは、一人で抱え込んでいるとますます大きくなり、精神的な負担が増してしまいます。
一方、信頼できる人に話を聞いてもらうと気持ちが楽になるだけでなく、客観的な視点から新たな気づきや解決策が見えてくることもあります。家族はもちろんのこと、担任の先生や養護教諭、スクールカウンセラーの中から、話しやすいと感じる大人に、自分の素直な気持ちを打ち明けましょう。
また、同じような悩みを抱える学生が集まるコミュニティに参加して、情報交換をしたり励まし合ったりするのもおすすめです。
学校以外の落ち着く居場所を探す
学校が怖いと感じる場合は無理に登校するのではなく、自分が心から安心できる居場所を確保するのがよいでしょう。学校以外に安心できる居場所を確保できると、精神的な余裕が生まれ、結果的に学校に対する恐怖心が軽減される可能性があります。
例えば、自分のペースで学習できるフリースクールや、自治体が運営する教育支援センター(適応指導教室)などが選択肢として挙げられます。また、自分の趣味や特技を活かせる習い事やボランティア活動への参加も、自己肯定感を高めるきっかけになるのでおすすめです。
なお、HR高等学院では学生一人ひとりの個性を尊重し、安心して学べる環境を提供しています。「学校が怖い」「学校以外の居場所を見つけたい」と考えている方は、以下よりお気軽にお問い合わせください。
徹底した個別サポートが、 可能性を引き出す。 - HR高等学院
「社会で生きていける力」を。
- 入学前不登校経験者8割。
入学後登校率89% - ぷよぷよ、モンスト開発者、
日本一になった起業家
から直接学べる - docomo、Lotte、Mixiなど
大企業と連携したプロジェクト型学習

学校が怖いと言われた時にするべきではない親の対応
学校が怖いと言われた時にするべきではない親の対応は、以下のとおりです。
- 子どもの話を聞かない
- 親が勝手に判断する
- 学校が怖い理由を問い詰める
- 何もせずに見守る
子どもから「学校が怖い」と打ち明けられたとき、どのように対応すればよいか戸惑ってしまうこともあるでしょう。また、よかれと思って取った対応が、かえって子どもの心を傷つけ、状況を悪化させてしまう場合もあります。
ここでは、子どもから相談された際に、親がするべきではない対応を詳しく解説します。
子どもの話を聞かない
子どもが勇気を出して「学校が怖い」と打ち明けてくれたにもかかわらず、「気にしすぎだよ」「みんな頑張って学校に行っているんだから」と、子どもの気持ちを軽視したり、否定したりする言葉は避けるべきです。このような対応は、子どもに「自分の気持ちは理解してもらえないんだ」と深い孤独感や絶望感を与えてしまいます。
また、子どもが話している途中で、自身の考えや解決策を一方的に押しつけるのもよくありません。思春期の子どもは自分の複雑な気持ちを整理し、言葉にするのに時間がかかる場合が多いため、途中で話を遮られてしまうと心を閉ざしてしまう可能性があります。
親が勝手に判断する
「うちの子は内気な性格だから、きっと新しいクラスに馴染めないんだろう」「昔から繊細な子だったから、ちょっとしたことで傷つきやすいんだ」などと勝手に判断するのはやめましょう。親自身の経験や価値観に基づく憶測で、本人の意見を聞かずに対策を講じてしまうと状況は悪化します。
学校を怖いと感じる理由は人それぞれであり、さまざまな原因が複雑に絡み合っていることが少なくありません。まずは、思い込みや先入観は捨てた上で子どもの言葉に耳を傾け、何に困っているのか、どう感じているのかを丁寧にヒアリングするのが大切です。
学校が怖い理由を問い詰める
「どうして学校が怖いの?」「何があったの?」と繰り返し質問すると、子どもは追い詰められた気持ちになり、心を閉ざしてしまう可能性があります。また、理由がはっきりしない場合や、子ども自身がうまく言語化できない場合は、質問攻めにすると余計にストレスを与えてしまいます。
原因を特定するのは大切ですが、話したくない時は無理に聞き出そうとせず、「話したい時はいつでも聞くよ」と伝えて、子どものペースを尊重してあげましょう。
そのほか、「そんなことで学校に行けないなんておかしい」「そんな理由で休むなんて甘えている」などの批判的な言葉を投げかけることも、子どもの自己肯定感を著しく低下させるので避けるべきです。
何もせずに見守る
「そのうち解決するだろう」「本人の問題だから親は見守るしかない」と、具体的な対策を講じずに、ただ見守るだけのアプローチも危険です。子どもの自主性を尊重するのは大切ですが、学校に対する恐怖感・不安感が自然に解消されるケースはあまり多くありません。
また、状況が悪化して不登校になると、生活リズムの乱れや学習の遅れ、社会性の喪失など二次的な問題が生じる可能性が高まります。
親が積極的に情報を集めながら解決策を模索する姿勢を示すことが、子どもに「自分は一人ではないんだ」と安心感を与えます。
学校が怖いと言われた時にすべき親の対応
学校が怖いと言われた時にすべき親の対応は、以下のとおりです。
- 学校が怖い気持ちを受け入れてあげる
- 子どもの頑張りを褒めてあげる
- 一緒に対処法を考える
- 専門機関やカウンセラーに相談する
「学校が怖い」と打ち明けられた際、親は冷静かつ温かく子どもに寄り添うのが何よりも大切です。パニックになったり、感情的に叱責したりするのではなく、子どもの気持ちを尊重しながら、問題解決に向けて行動しましょう。
ここでは、子どもから相談された際に、親がするべき対応を詳しく解説します。
学校が怖い気持ちを受け入れてあげる
子どもが学校への恐怖心を訴えてきたときは、気持ちを否定せず、ありのまま受け止めてあげるのが大切です。「そう感じているんだね」「怖いと感じるのは恥ずかしいことじゃないよ」と、子どもの感情に寄り添い、共感する姿勢を示しましょう。
頭ごなしに叱ったり、原因を追求したりするのは避け、まずは子どもが安心して気持ちを話せるような雰囲気作りを心がけてください。親の役割は子どもの感情を矯正するのではなく、気持ちに向き合いながらサポートすることです。
子どもの頑張りを褒めてあげる
子どもが学校に対して強い不安を抱えながらも、前向きな行動や努力を見せた時には、頑張りを認めて心から褒めてあげるのが大切です。校門まで行けた、保健室に入れた、一時間だけでも授業に参加できたなど小さな一歩であっても、行動したことを認めてあげましょう。
頑張りをきちんと認めてあげれば、子どもの自己肯定感は少しずつ回復します。また、結果だけでなく、そこに至るまでのプロセスを評価してあげるのも効果的です。
一緒に対処法を考える
学校への恐怖感をなくしていくためには、親子で一緒に対処法を考えていくのも重要です。まずは「今どうしたら少しでも気持ちが楽になるか」といった短期的な対策から始め、徐々に長期的な解決策について話し合いましょう。
また、「登校時の不安が強い場合は、起床時間を早めに設定してメンタルを整える時間を作る」「学校までの道のりが不安なのであれば親が一緒に登校する」など、できるだけ具体的な対策を立てる意識も大切です。
もし、現在の学校環境がどうしても合わないと感じる場合は、他の学校への転校・編入も視野に入れて話し合いましょう。高校を転校する際の手続きや流れを知りたい方は、こちらもあわせてご覧ください。
専門機関やカウンセラーに相談する
子どもが学校が怖いと感じる理由をうまく説明できない場合や、親子だけの話し合いで解決が望めない場合は、専門家・専門機関に相談しましょう。相談先の例は以下のとおりです。
- スクールカウンセラー
- 教育相談センター
- 教育支援センター
- 児童相談所
- 民間のカウンセリング機関
専門家・専門機関に相談すれば、子どもの心理状態や状況に応じた専門的なアドバイスを受けられます。また、必要に応じて医療機関を受診して、健康状態のチェックや発達特性に関する検査を行うことも検討しましょう。
なお、専門家・専門機関への相談は、ネガティブなものではなく、子どもの健やかな成長を支えるためのポジティブな行動としてとらえる意識も大切です。
参考:東京都教育委員会|不登校児童・生徒への効果的な支援事例について
参考:文部科学省|不登校に関する地元の相談窓口
通信制高校サポート校「HR高等学院」をご紹介
HR高等学院は従来の詰め込み型の教育ではなく、「探究・越境・共創」を掲げた独自のカリキュラムを採用している通信制高校サポート校です。
docomo、LOTTE、CHINTAI、mixiなど名だたる企業と連携したプロジェクト型学習や専門ゼミ、各界のトップランナーによるセッションなどを通じて、以下の能力を養います。
- 課題解決力
- 論理的思考力
- コミュニケーション力
HR高等学院ではハイブリッド型の学習環境が整えられており、完全オンラインから週5登校まで自宅でのオンライン学習と校舎での通学学習を自由に組み合わせできるのが特徴です。また、学生一人ひとりに寄り添う個別サポートが充実している点も本校の魅力です。
最後に
「学校が怖い」と感じるのは決して悪いことではありません。自分の気持ちを否定せず、まずは学校が怖いと感じている理由を整理することから始めましょう。恐怖感の原因は人それぞれですが、正しくアプローチすれば、きっと状況は改善できるはずです。
また、子どもが学校生活に悩んでいる場合、親は子どもに共感し素直な気持ちを尊重する姿勢を持つのが大切です。必要であれば専門家・専門機関の力を借りたり、医療機関を受診したりすることも検討しましょう。
大切なのは既存の価値観や周囲の考えに流されず、自分にあった学びの場を見つけることです。
もし、「自分らしく学びたい」「将来の夢を見つけたい」という場合は、通信制高校サポート校への入学も検討しましょう。通信制高校サポート校の「HR高等学院」は、「日本でいちばん自由で面白い学校」を目指しています。いつでも転入・編入を受け付け中です!ご興味持っていただけた方はまずは上記リンクよりHR高等学院のことを少しでも知っていただけますと嬉しいです!
説明会・オープンキャンパスはこちら!