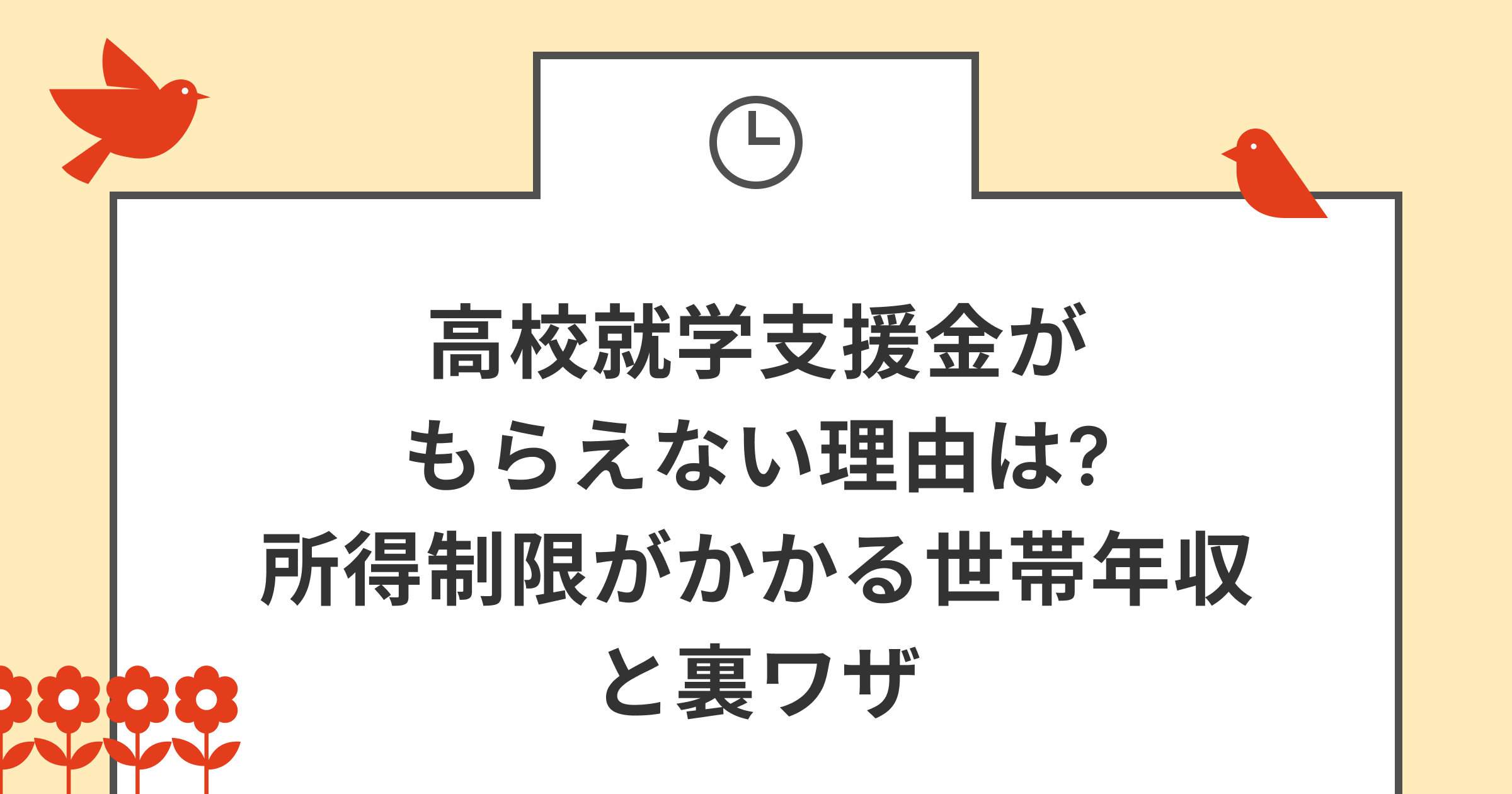「就学支援金が支給されなかった理由を知りたい」「収入や手続きなどの条件に問題はないか再度確認したい」とお悩みではありませんか?
高校進学を控えた子どもを持つ保護者にとって、教育費の負担は大きな関心事の一つです。
「高校就学支援金」は経済的な負担を軽減できる制度ですが、必ずしもすべての家庭が利用できるわけではありません。
本記事では、高校就学支援金の概要と高校就学支援金がもらえない理由、受給対象か確認する方法などを詳しく解説します。
高校就学支援金の所得制限を回避するための裏ワザや、高校就学支援金がもらえない場合に利用できる給付金も紹介するので、ぜひ最後までご覧ください。
本記事を参考にすれば、経済的な負担を軽くするヒントが得られるはずです。
そもそも高校就学支援金とはどんな制度?
高校就学支援金制度は、日本国内にある国公私立の高等学校に通う学生の授業料負担を軽減するための公的な制度です。
制度の目的は生徒の学ぶ意欲を応援し、家庭の経済状況にかかわらず、誰もが安心して教育を受けられるようにすることです。
支援金は生徒本人や保護者に直接現金が支給されるのではなく、学校側が代理で国から受領し、生徒が支払うべき授業料に充当する仕組みとなっています。
そのため、保護者が授業料を一旦全額支払ったり、還付手続きを行なったりする必要はありません。
また、高校就学支援金制度の支援金は給付型であり、将来返済する必要がないのが特徴です。
ただし、すべての世帯が無条件で支援金を受給できるわけではなく、いくつかの条件を満たす必要があります。
高校就学支援金がもらえない理由
高校就学支援金がもらえない理由は、以下のとおりです。
- 受給資格を満たしていない
- 所得制限を超えた
- 世帯収入が増えて年収が上がった
- 高校就学支援金の申請をしなかった
高校就学支援金が支給されない場合、いくつかの理由が考えられます。
一般的なのは所得制限を超えているケースですが、それ以外にも受給資格そのものを満たしていなかったり、必要な申請手続きを行っていなかったりする場合もあります。
また、一度受給資格を得た後でも世帯収入が増えると、対象外となる可能性もあります。ここでは、高校就学支援金がもらえない理由を4つ解説するので、参考にしてください。
高校就学支援金がもらえない理由を理解しておけば、事前に対策を講じたり、他の支援制度を検討したりするきっかけになるでしょう。
受給資格を満たしていない
高校就学支援金を受給するには、基本的な受給資格を満たしていなければなりません。まず、「日本国内に住所を有し、高等学校等に在学していること」が条件に挙げられます。
また、対象となる学校は、以下のように定められています。
- 全日制高等学校
- 定時制高等学校
- 通信制高等学校
- 中等教育学校の後期課程
- 高等専門学校の第1学年から第3学年
- 専修学校各課程
- 海上技術学校
- 特別支援学校の高等部
- 指定を受けた外国人学校
- 指定を受けたインターナショナルスクール
ただし、既に高等学校等を卒業したことがある学生や、高等学校等に在学した期間が通算で36か月(定時制・通信制課程の場合は48か月)を超えている学生は、原則として制度の対象外とされています。
所得制限を超えた
高校就学支援金制度には、所得制限が設けられています。そのため、世帯の所得が一定の基準額を超えている場合は支援金を受給できません。
所得制限の判定は、保護者の市町村民税の課税標準額と調整控除額を用いて行われます。
具体的には、「課税標準額×6%-調整控除額」の計算式で算出された金額が30万4,200円以上の場合は、支給対象外となります。この金額は、世帯年収910万円相当です。
共働き世帯の場合は両親の所得を合算して判定されるため、それぞれの年収が500万円程度でも制限を超える可能性があります。
また、不動産所得や株式売却益なども所得に含まれるため、給与以外の収入がある場合は注意が必要です。
世帯収入が増えて年収が上がった
就学支援金の受給資格は、毎年保護者等の所得状況に基づいて再審査が行われます。
高校入学時には所得制限の基準を満たしており、就学支援金を受給できていたとしても、後に世帯収入が増加して所得制限の基準額を超えてしまうと高校就学支援金はもらえません。
例えば、昇給や転職によって収入が増えたり、専業主婦(夫)だった配偶者が働き始めたりして、所得制限を超えてしまうケースが見受けられます。
また、上の子どもが独立して扶養家族の人数が減少し、結果として一人当たりの所得額が上がることで、所得制限に引っかかる場合もあります。
高校就学支援金の申請をしなかった
高校就学支援金は受給資格を満たしていても、自動的に支給されるわけではありません。保護者等が学校を通じて、申請手続きを行う必要があります。
高校入学時の説明会で申請に関する案内があるのが一般的で、指定された期限までに「受給資格認定申請書」や「マイナンバーカード(個人番号カード)の写し等」といった必要書類を学校に提出します。
申請手続きを行わなかった場合、あるいは提出が期限に間に合わなかった場合は、たとえ所得制限などの受給資格を満たしていても支援金は支給されません。
また、申請書類に記載漏れや誤りがあったり、必要な添付書類が不足していたりする場合も、支給されない可能性があります。
「社会で生きていける力」を。
- 入学前不登校経験者8割。
入学後登校率89% - ぷよぷよ、モンスト開発者、
日本一になった起業家
から直接学べる - docomo、Lotte、Mixiなど
大企業と連携したプロジェクト型学習

高校就学支援金の受給対象か確認する方法
高校就学支援金の受給対象となるかどうかを確認するには、まず所得状況を正確に把握するのが大切です。
文部科学省のwebサイトには、所得制限の目安となるモデル世帯の年収や、具体的な判定基準となる「保護者等の課税標準額(課税所得額)等」の算定方法が掲載されています。
公式に発表されている情報を参考にして、世帯の所得が基準の範囲内であるかを確認しましょう。
より具体的に確認したい場合は、市区町村が発行する「住民税課税証明書」を取得して、課税標準額や市町村民税の調整控除額を確認しましょう。
これらの情報を基に、文部科学省が示している計算式(市町村民税の課税標準額 × 6% - 市町村民税の調整控除の額)で判定基準額を算出してください。
算出した額が30万4,200円未満であれば、受給対象となる可能性が高まります。
高校就学支援金の所得制限を回避するための裏ワザ
高校就学支援金の所得制限を回避するための裏ワザは、以下のとおりです。
- 収入を減らす
- 経費や所得控除を増やす
- iDeCo(個人型確定拠出年金)などを活用する
高校就学支援金制度の所得制限は、保護者等の「課税所得額」で判定されます。
つまり、収入そのものではなく、収入から経費や各種控除を差し引いた後の金額が基準となるため、課税所得額を低く抑えれば所得制限をクリアできる可能性が高まります。
ここでは、高校就学支援金の所得制限を回避するための裏ワザを詳しく解説するので、参考にしてください。
収入を減らす
所得制限を回避するもっとも確実な方法は、世帯の合算収入を意図的に減らすことです。
例えば、共働きで所得制限をわずかに超えている場合は、パートタイム勤務の労働時間を調整したり、一時的に仕事量をセーブしたりすることで、基準額内に収められます。
ただし、世帯全体の収入が減少すると家計に影響を及ぼす可能性があるため、ライフプランを慎重に考慮した上で、実行するか否かを判断する必要があります。
安易な収入調整は推奨されませんが、状況によっては有効な手段となることを覚えておきましょう。
経費や所得控除を増やす
経費や所得控除を増やし、課税所得を下げることで受給資格を満たす方法もあります。課税所得額とは、総収入から必要経費や各種所得控除を差し引いた金額です。
給与所得者の場合は、年末調整や確定申告で申告できる所得控除を最大限に活用しましょう。代表的な所得控除には、以下のものが挙げられます。
- 生命保険料控除
- 医療費控除(年間10万円を超える医療費)
- 寄付金控除
これらの控除を漏れなく申告することで、課税所得額を圧縮可能です。自営業を営んでいる場合は、事業運営に直接関連する経費を正確に把握し、課税所得を下げられます。
iDeCo(個人型確定拠出年金)などを活用する
iDeCo(個人型確定拠出年金)は、老後資金の準備を目的とした私的年金制度ですが、掛金全額が所得控除(小規模企業共済等掛金控除)の対象となるため、課税所得の圧縮に期待できます。
iDeCoは月額5万5,000円(自営業者は6万8,000円)まで拠出可能です。夫婦でそれぞれ加入すれば、世帯で年間132万円の所得控除を活用できます。
iDeCoは将来の年金準備としての効果もあり、税制優遇を受けながら老後資金を積み立てられる点が魅力です。
また、運用益も非課税で、受取時にも一定の控除があるため、単純な所得制限回避以上のメリットが存在します。
ただし、60歳まで引き出せないという制約があるため、家計の状況を考慮した上で活用の可否や拠出額を検討しましょう。
通信制高校でも高校就学支援金はもらえる?
高校就学支援金制度は、学校教育法第1条に規定される高等学校に在籍する学生を対象にした制度です。つまり、通信制高校も高校就学支援金制度の対象に含まれています。
なお、通信制高校の授業料は単位制で、履修する単位数に応じて決定されるのが一般的です。そのため、就学支援金の支給額も、履修単位数に基づいて計算されます。
ただし、所得制限の基準については、全日制や定時制の高校と同様の基準が適用されます。
まずは、入学を希望する通信制高校の事務室や担当窓口に相談し、申請手続きや具体的な支給額の見込みについて確認してみるのがおすすめです。
「社会で生きていける力」を。
- 入学前不登校経験者8割。
入学後登校率89% - ぷよぷよ、モンスト開発者、
日本一になった起業家
から直接学べる - docomo、Lotte、Mixiなど
大企業と連携したプロジェクト型学習

授業料以外での学校にかかる費用
授業料以外で学校にかかる費用は、以下のとおりです。
- 入学費
- 教材費
- 制服代
- 修学旅行や行事にかかる費用
- その他の費用
高校生活では、毎月の授業料の他にもさまざまな費用が必要です。
高校就学支援金は主に授業料に充当されるため、それ以外の費用については基本的に自己負担となることを理解しておく必要があります。
具体的にどのような費用がかかるのかを事前に把握して、より具体的な資金計画を立てておきましょう。ここでは、授業料以外で学校にかかる費用を詳しく解説します。
入学費
高校に入学する際は、まず入学金の支払いが必要です。公立高校の入学金は比較的安価で、5,550円〜5,650円に設定されています。
一方、私立高校の入学金は高額になる傾向があり、10万円〜90万円程度、場合によってはそれ以上かかることもあります。
入学金は、高校就学支援金制度の支援対象ではないため、全額自己負担しなければなりません。
また、入学手続きの際に一括での納入を求められることが多いため、事前にまとまった資金を用意しておく必要があります。
教材費
高等学校の授業では授業で使用する教科書のほかにも、補助教材として指定される問題集、資料集、参考書などが必要であり、これらの購入費用も自己負担しなければなりません。
教科書代は、生徒が履修する科目数や選択する科目によって異なりますが、年間でおおむね5万円〜7万円程度が目安です。
ただし、普通科以外の専門学科や芸術系の科目などを選択する場合は、専門的な教科書や画材、実習用具などが別途必要となるため、教材費がさらに高くなる可能性があります。
これらの教材費も、原則として高校就学支援金の対象外です。
なお、経済的に困難な家庭を対象とした「高校生等奨学給付金制度」では、教材費を含む授業料以外の教育費の一部が支援される場合があります。
制服代
文部科学省の「令和3年度子供の学習費調査」によると、制服代の平均費用は公立高校で2万6110円、私立で3万6086円とされています。
制服一式には、ブレザーやスカート・ズボン、シャツ、ネクタイ、靴下などが含まれ、季節に応じて夏服と冬服の両方を購入する必要があります。
また、体操服やジャージ、部活動用のユニフォームなども別途購入が必要です。
制服の購入時期は入学前の2月から3月にかけてが一般的で、採寸から納品まで時間がかかるため早めに手続きしておきましょう。
在学中にサイズ変更が必要になることもあるため、追加費用が生じる可能性も考慮しておかなければなりません。
修学旅行などの行事にかかる費用
高校生活を彩る重要な思い出となる修学旅行や、遠足、文化祭、体育祭といった学校行事への参加にも、一定の費用がかかります。
特に修学旅行は、行き先や宿泊日数、交通手段などによって変動するものの、高額な費用が必要になるケースも少なくありません。
日本修学旅行協会の「教育旅行年報 データブック2023」によると、修学旅行の費用は公立高校で6,738円〜17万1,090円、私立高校で1万1,980円〜28万円とされています。
なお、これら学校行事にかかる費用も、原則として高校就学支援金の対象とはなりません。
ただし、経済的な理由で修学旅行への参加が困難な学生を対象として、一部費用を補助する制度を設けている地方自治体も存在します。
また、PTA会費や後援会費などが、これらの行事費用の一部に充当される場合もあります。
出典:公益財団法人日本修学旅行協会|教育旅行年報 データブック2023
出典:Tokyoナビ|修学旅行費補助
その他の費用
先に挙げた入学金や教材費、制服代、行事費用のほかにも、高校生活ではさまざまな費用が生じます。例えば、PTA会費や生徒会費、学級費など学校に納める諸会費があります。
また、部活動に参加する場合は、部費や遠征費などが別途必要になるでしょう。通学にかかる交通費や、毎日の昼食代も考慮しなければなりません。
さらに、学習塾や予備校に通う場合は月謝、資格取得を目指す場合は受験料などの支払いが必要です。
これらの費用は学校の種類や生徒個人の活動内容、家庭の状況によって変動しますが、積み重なるとある程度の金額になることは理解しておくべきでしょう。
高校就学支援金がもらえない場合に利用できる給付金
高校就学支援金がもらえない場合に利用できる給付金は、以下のとおりです。
- 地方自治体独自の支援
- 高校生等奨学給付金
高校就学支援金の所得制限を超えてしまったり、その他の理由で受給できなかったりした場合でも、諦める必要はありません。
地方自治体や民間団体などが、経済的に困難な状況にある高校生を支援するために、さまざまな給付金制度や奨学金制度を設けています。
これらの制度を上手に活用することで、教育費の負担を軽減できる可能性があります。
ここでは、高校就学支援金がもらえない場合に利用できる給付金を2つ紹介するので、参考にしてください。
地方自治体独自の支援
多くの都道府県や市区町村では、国の高校就学支援金制度を補完する形で、独自の学費支援制度や奨学金制度を設けています。
国の就学支援金制度と併用できる場合も多く、所得制限の基準が国よりも緩やかに設定されていたり、授業料以外の教育費も支援対象となっていたりすることが少なくありません。
例えば、東京都では都内の私立高校に通う生徒を対象に「私立高等学校等授業料軽減助成金」を給付しています。
私立高等学校等授業料軽減助成金と就学支援金をあわせて利用することで、世帯年収によっては授業料が実質無料になる可能性もあります。
お住まいの都道府県や市区町村の教育委員会や役所のwebサイトで、どのような支援制度が提供されているのか、どのような条件で利用できるのかを詳しく確認してみましょう。
出典:東京都|所得制限なく私立高校等の授業料支援が受けられます
高校生等奨学給付金
文部科学省が実施する高校生等奨学給付金は、授業料以外の教育費負担を軽減するための制度であり、対象は生活保護受給世帯や住民税非課税世帯です。
授業料以外の教育費とは、以下の費用を指します。
- 教科書費
- 教材費
- 学用品費
- 通学用品費
- 教科外活動費
- 生徒会費
- PTA会費
- 入学学用品費
- 修学旅行費
- 通信費
具体的な給付額は、下表のとおりです。
なお、高校生等奨学給付金は返済不要で、高校就学支援金制度と併用することも可能です。
通信制高校サポート校「HR高等学院」をご紹介
ひと足先に、社会で学ぶ学校 - 大企業とのプロジェクトで実践的に学ぶ。-HR高等学院
HR高等学院は従来の詰め込み型の教育ではなく、「探究・越境・共創」を掲げた独自のカリキュラムを採用している通信制高校サポート校です。
企業と連携したプロジェクト型学習や専門ゼミ、各界のトップランナーによるセッションなどを通じて、以下の能力を養います。
- 課題解決力
- 論理的思考力
- コミュニケーション力
HR高等学院ではハイブリッド型の学習環境が整えられており、自宅でのオンライン学習と校舎での通学学習を自由に組み合わせできるのが特徴です。
また、学生一人ひとりに寄り添う個別サポートが充実している点も本校の魅力です。
最後に
高校就学支援金がもらえない理由は、受給資格の不適合や所得制限の超過が主な要因です。
世帯年収が910万円前後の家庭では、わずかな所得の差で受給の可否が決まるため、iDeCoや生命保険料控除などを活用した対策を積極的に行いましょう。
ただし、高校生活では授業料以外にもさまざまな費用が必要となります。就学支援金は主に授業料に充当されるため、その他の費用については別途準備が必要です。
就学支援金だけでなく、高校生等奨学給付金や地方自治体独自の支援制度も併せて活用すれば、教育費の負担をより軽減できます。
各種支援制度についてわからないことがあれば、学校や自治体の担当窓口に相談することをおすすめします。
なお、「自分らしく学びたい」「将来の夢を見つけたい」という方は、通信制高校サポート校への入学もご検討ください。
通信制高校サポート校の「HR高等学院」では、学生一人ひとりの希望や個性に合わせた学習サポートやコーチングを提供しています。