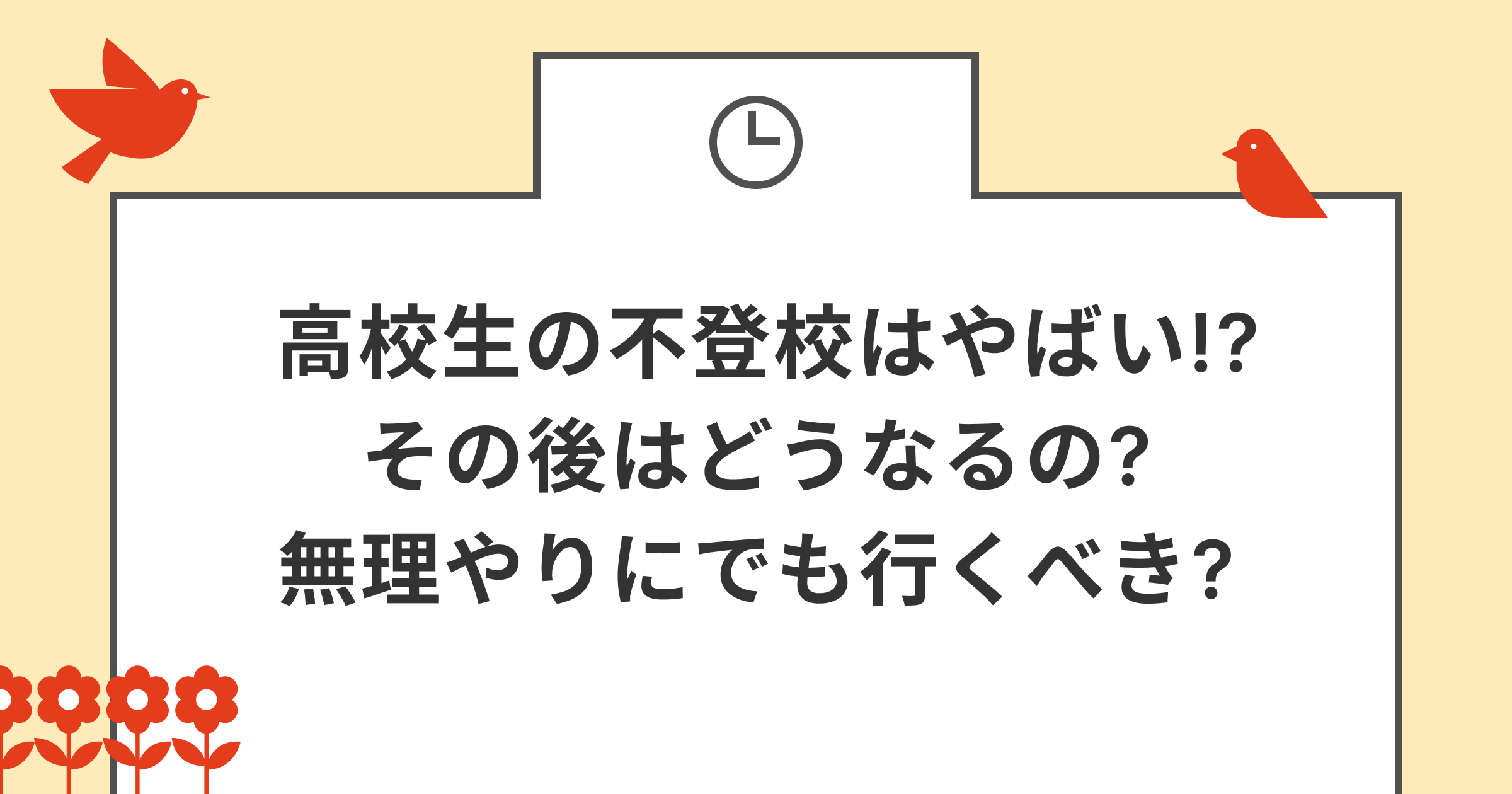不登校の高校生は「このままではやばい! 学校に行かなければ」と思いつつも登校できない自分に葛藤し苦しんでいることが多いはずです。
親の期待や自分の思いとの間で、強いプレッシャーや罪悪感を抱えることもあります。
一方で保護者も「このまま不登校が続いたらどうなるのか」「無理にでも学校へ行かせるべきか」と悩みを抱えます。
この記事では、高校生の不登校の実態や将来への影響、経験者の声、具体的な対応策を詳しく解説し、不登校でも選べる進路も紹介します。
高校生の不登校はやばい?
高校生が「不登校はやばい」と感じる主な理由は、出席日数や成績が基準に満たないと留年や中退のリスクがあるためです。中学校のように自動的に卒業できず、必要な単位や出席日数を自分でクリアしなければなりません。
さらに、進級や卒業ができないことで将来の進路が狭まる不安や、周囲の目、親の期待など精神的な負担も重なり「このままではやばい」と強く感じやすくなります。
【体験談】
"本格的にやばいです。不登校になりかけています。
今日は絶対学校に行こうと決めていたのに直前になると憂鬱になって本当に行く気が無くなってしまいます。
どうしたらいいんでしょうか?
(中略)
この気持ちはどうすれば治りますか?
今高校二年生なんですけど進学のこととかが心配です。欠席日数はどれくらい内申に影響してきますか?
最後に私は休んでもいいと思いますか?”
引用元:Yahoo!知恵袋「不登校|学校の悩み(2018年1月投稿)
不登校になりかけている状況のこの高校生は「学校に行かなければ」というプレッシャーと「行きたくない」という気持ちで深く葛藤しています。親の反応や進学への不安も重なって追い詰められている様子がうかがえます。
高校生の不登校の特徴
高校生の不登校には、中学生とは違う特徴があります。
- 進級や卒業、進路への焦りが強くなる
- 部活動やアルバイトなど、学校以外の場所に逃げ道を作りやすい
- 複数の要因が重なりやすい
中学と異なり義務教育ではないため、進級や卒業、将来への不安も大きくなりがちです。また、部活動やアルバイトなど、学校以外の場所に自分の居場所を見つけやすいのも特徴です。
また、高校生の不登校の背景には、いじめや成績不振、家庭環境、SNSトラブルなど多様な要因が複雑に絡み合っています。
「友達ができない」「入学前に描いていた学校生活と違う」などと悩み、高校入学直後や短期間のうちに不登校になるケースも少なくありません。
【体験談】
“わたしは中学1年生の頃不登校になり復帰するために中学2年生から別室で授業を受け(行けそうな授業は教室に行く)中学3年生からは月に1度くらいは休みつつも学校に通えるようになりました。 高校からはきちんと通いたいと思い遠くの私立高校を受け今年から通い始めました。遠くを希望した理由は不登校の時のわたしを知ってるひとがいて欲しくなかったというのが主な理由です。
ですが高校に入学して1週間、早くも学校を休んでしまいました。同じ高校に通っている子は同中の子が結構いるらしくわたしだけぼっち状態です。(中略)高校は家から1時間半ほどかけていくので朝は早く起きて人混みの中行かなければいけない。そういったこともあって学校に行くのがどんどんしんどくなっていってしまいました。
(中略)ですが両親が高いお金を出して入学させてくれた高校を退学なんてしたくありません。行かなきゃいけないこともわかってるんですけどどうしても行けません。今はまだ休んで一日目ですがきっとこの先も休んでしまうと思います。”
引用元:Yahoo!知恵袋「不登校|学校の悩み(2024年4月投稿)
この高校生は中学の不登校経験を乗り越えて進学したものの、入学後1週間で、新しい環境での孤立や通学の負担から登校が辛くなっています。先の不安や親への想いなどの葛藤を抱えている様子が伝わります。
高校生の不登校のデータ
実際にどのくらいの高校生が不登校になっているのか、最新のデータをもとに詳しく解説します。
下記は、2024年度と2025年度の不登校の高校生の人数です。
出典:文部科学省「令和5年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果の概要」
2024年度は不登校生徒数が過去最多を記録し、前年度からの増加率は13.5%でした。不登校率は2.4%で、これは「およそ42人に1人」が不登校という計算になります。
また、そのうち90日以上欠席した学生は全体の15.7%となっています。この現状から、高校生の不登校は決して珍しいことではないと言えるでしょう。
高校生の不登校が「やばい」理由
なぜ高校生の不登校が「やばい」と言われるのかその背景を解説します。
- 学校の授業についていけなくなるから
- 学校行事やイベントに参加できないから
- 留年の可能性があるから
- 高校を中退してしまうリスクがあるから
- 進学や就職に影響が出るかもしれないから
では、順に解説します。
学校の授業についていけなくなるから
高校の授業は小中学校より進度が速く内容も難しいため、数日休むだけでも遅れを取り戻すのが大変です。不登校になると授業についていけなくなり、劣等感や焦りからさらに登校意欲が低下する悪循環に陥りやすくなります。
学校行事やイベントに参加できないから
学校行事やイベントは、高校生活の大切な思い出を作り、仲間との絆を深める貴重な場です。不登校になるとこうした経験が得られず、孤立感や疎外感を強く感じることもあります。
また、学生時代の行事やイベントの思い出は大人になってからも心に残りやすく、話題に上ることも多いため、参加できなかったことを後悔してしまうかもしれません。
留年の可能性があるから
高校では出席日数や単位取得が厳しく管理されており、不登校が長引くと必要な単位が取れず留年につながります。
留年すると、一つ下の学年の学生と一緒に授業を受けることになるため、劣等感を感じたり、周囲の視線が気になったりするなど、精神的な負担が大きくなります。それがきっかけになり、さらに登校が難しくなる場合があります。
高校を中退してしまうリスクがあるから
令和5年度は不登校高校生のうち17.1%が中退しており、留年が決まったことをきっかけに中退を決断するケースも多くなっています。
中退をすると最終学歴は「中卒」となり、就職や進学など将来の選択肢が大きく制限されることがあります。また、友人や教師との交流や学校行事の経験を失うことで、孤立感や自己肯定感の低下にもつながりやすくなります。
出典:文部科学省「令和5年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果の概要」
【体験談】
この方は、不登校と高校中退により、社会的な交流の機会を逃したことを後悔しています。
進学や就職に影響が出るかもしれないから
総合型選抜や一般入試での大学受験では、出席日数は重視されない傾向のため、不登校であっても受験自体には大きな影響がないとされています。しかし実際には、不登校によって学力が志望校のレベルに届かず進学先が限られてしまう場合があります。
また、就職活動では高校から送られる調査書に出欠席日数が記載され、欠席が多い場合はその理由によって採用に不利になることがあるため注意が必要です。
「社会で生きていける力」を。
- 入学前不登校経験者8割。
入学後登校率89% - ぷよぷよ、モンスト開発者、
日本一になった起業家
から直接学べる - docomo、Lotte、Mixiなど
大企業と連携したプロジェクト型学習

高校生で不登校になると将来がやばい?
高校生で不登校になると、将来にさまざまな影響が及ぶ可能性があります。特に、学校生活で自然と育まれる力や、心の健康への影響が心配されています。
以下では、その中でも特に重要な2点について解説します。
コミュニケーション能力が育たない
学校は人間関係や協調性を学ぶ場でもあり、不登校になると友人や教師との関わりが減り、社会性やコミュニケーション能力を身につける機会が少なくなります。
そのため、社会に出たとき人間関係でつまずくリスクが高まります。社会では多様な人と協力する場面が多いため、高校時代にコミュニケーション力を養うことは大切です。
とはいえ、学校と社会で求められるコミュニケーション能力は異なります。コミュニケーション能力を鍛えられる「社会」は学校だけではありません。不登校でも社会と関わることを意識することが重要です。
引きこもりやうつ病になるリスクが高くなる
不登校になると社会との接点が減り、孤独感や将来への不安が強まり、ストレスが蓄積されやすくなります。
このような状態が続くと、うつ病や不安障害などの心の病を発症するリスクが高まります。さらに、悩みを一人で抱え込むことで、不登校や引きこもりの状態が長引きやすくなり、問題の解決が難しくなるため注意が必要です。
【体験談】
“私は高校生で躁鬱(双極性障害)と診断されました。
きっかけは2年前のダイエットと勉強です。
(中略)
よって1年前から引き篭もりになり不登校になりましたが、保健室登校などでなんとか退学にはなりませんでした。 もう少しで新学期が始まるのですが、
薬と休暇やカウンセリングのおかげで心身共にはかなり良くなってきたと思っています。
ですがお医者さんが「躁鬱病患者は本当は50%しか回復してないのに完全に回復したと思って以前の様に自分に厳しく張り切って仕事をして、また体調を崩して鬱になり…というのを繰り返して中々完治しない場合が多い」と言ったことがありました。
(中略)もしこれがきっかけでまた鬱になったらどうしようと不安で仕方ないです。”
引用元:Yahoo!知恵袋|学校の悩み(2024年4月投稿)
この高校生は双極性障害と診断され、不登校を経験しながらも保健室登校で退学にならずにすみました。しかし、治療により回復を感じつつも再発への不安を抱えています。
不登校でやばいと感じている高校生の対応
現在、不登校で不安や悩みを抱えている高校生に向けて、今できることを紹介します。無理のない範囲で、できることから行動してみましょう。
- 現状を整理する
- 生活リズムを整えておく
- 信頼できる大人や親に相談する
- 現在の学校以外の選択肢を考える
現状を整理する
まずは自分の今の状況を冷静に整理してみましょう。不登校になった理由やきっかけ、今の不安や悩みを、ただ考えるのでなく紙やスマホに書き出してみることがポイントです。
客観的に自分を見つめ直すことで「何がつらいのか」がはっきりし、また「どうしたら改善できそうか」も分かりやすくなります。
生活リズムを整えておく
不登校が続くと、どうしても生活リズムが乱れがちになります。夜更かしや昼夜逆転が続くと、体調だけでなく心の健康にも悪影響を及ぼします。まずは毎日同じ時間に起きる、朝ごはんを食べる、軽い運動をするなど、できるところから意識しましょう。
生活リズムが整うことで、体調や気分が安定しやすくなり、前向きな行動につながります。
信頼できる大人や親に相談する
一人で悩まず、周囲に相談することも大切です。悩みを共有すれば孤独感が和らぎ、前向きな気持ちになれるかもしれません。親に話しにくい場合は、教師やスクールカウンセラー、相談機関、SNSのコミュニティなど、話しやすい相手を探してみましょう。
相談することで思いがけない解決策や支援が得られることもあります。不登校の事例は増えており、多くの大人が親身に相談に乗ってくれます。
また、不登校を経験した人の進路や、克服した方法を知ることができるかもしれません。
現在の学校以外の選択肢を考える
どうしても登校が難しいと感じる場合は、無理に通い続ける必要はありません。今の学校に戻る以外にも進路の選択肢はあります。
現代は、通信制高校や定時制高校、サポート校、フリースクールなど、さまざまな学びの場が用意されています。これらの場所は、自分のペースで学習できる環境や、個別サポートが充実している場合がほとんどです。
不登校経験者も多く在籍しているため、同じ悩みを持つ仲間と出会えるかもしれません。転校や編入は大きな決断ですが、全日制だけにこだわらず、自分に合う環境を優先し最適な進路を検討することが大切です。
不登校の高校生への親の対応
高校生の子どもが不登校になったとき、親は大きな不安や戸惑いを感じるものです。ここでは、親ができる具体的な対応策について解説します。
- 学校を休んでもいいと伝える
- 学力が落ちないようにサポートする
- スクールカウンセラーや教師と連絡を取る
- 専門機関やサポート団体に相談する
- 通信制高校や定時制高校への編入を検討する
順に解説します。
学校を休んでもいいと伝える
不登校の子どもは、学校に行けないことに対して強いストレスや葛藤を抱えている場合が多く、精神的にも非常に繊細な状態です。「行かなければならない」というプレッシャーと「休みたい」という気持ちの間で悩み続け、心身ともに疲れ切っています。
無理に登校を促すのではなく、まずはしっかりと休息を取らせてあげることが大切です。「学校に行かなくても大丈夫」と伝えることで、子どもはプレッシャーから解放され、安心感を得られます。心が落ち着いて前向きな気持ちになれば、将来について冷静に話し合う機会も持てるでしょう。
学力が落ちないようにサポートする
不登校が続くと、学習の遅れから授業についていけなくなり、自信や登校意欲が低下しやすくなります。さらに、周囲との差を感じて「どうせ追いつけない」と思い、学習意欲も失いやすくなります。
こうした悪循環を防ぐには、学力が落ちないようにしっかりサポートすることが大切です。
子どもの気持ちや体調を最優先し、無理に勉強を押し付けず本人のペースで学べる環境を整えることが大切です。最近は、家庭教師やオンライン学習、通信教材など多様な学び方があるため、本人に合う方法を試し、自宅でも学習を継続しましょう。
スクールカウンセラーや教師と連絡を取る
学校との連携も重要なポイントです。担任の教師やスクールカウンセラーと定期的に連絡を取り、子どもの様子や今後の対応について情報を共有しましょう。学校側に現状を理解してもらうことで、保健室登校など柔軟な対応を受けられる場合もあります。
また、スクールカウンセラーは保護者からの相談も受け付けています。外部の支援機関を紹介してもらえることもあるので、気軽に相談してみることをおすすめします。
専門機関やサポート団体に相談する
不登校の問題は、家庭や学校だけで解決しようとすると、どうしても限界を感じてしまうことがあります。専門機関や支援団体の力を借りることをぜひ検討してみてください。
これらの機関には、不登校の子どもや家族をサポートしてきた経験豊富な専門家が在籍しており、心のケアや学習支援、安心できる居場所の提案など、さまざまな面から支援を受けることができます。
以下は、相談できる公的機関や民間の支援団体の一例です。
第三者の立場から状況を見てもらうことで、家庭内では気づきにくい課題や新たな解決策が見つかることもあります。
通信制高校や定時制高校への編入を検討する
今の学校に通い続けることが難しい場合、通信制高校や定時制高校への編入も有力な選択肢です。通信制高校は年間を通じて転入が可能な場合が多く、不登校経験者の受け入れにも理解があります。
登校頻度や学習スタイルも選べるため、体調や気持ちに合わせて無理なく学びを続けることができます。
環境を変えることで、不登校のきっかけとなった問題が解決することもあり、実際に通信制高校に転入して楽しく通えるようになったという高校生は多くいます。
保護者は情報の共有や手続きのサポートをしながら、子供に寄り添い一緒に進んでいくことが大切です。
【体験談】
上記は、通信制高校に通ったことが前向きな結果につながった例です。
このように、子どもに合った道を見つけることで状況が一転する場合もあります。
「社会で生きていける力」を。
- 入学前不登校経験者8割。
入学後登校率89% - ぷよぷよ、モンスト開発者、
日本一になった起業家
から直接学べる - docomo、Lotte、Mixiなど
大企業と連携したプロジェクト型学習

通信制高校サポート校「HR高等学院」をご紹介
HR高等学院は、2025年4月に開校した通信制高校サポート校です。卒業の条件を満たすことで、高校卒業資格を修得できます。
- 不登校経験があっても通いやすい柔軟な学習環境
- 学力や出席日数を問わない入学選考
- オンラインのみや週5通学まで選べる自由な学習スタイル
- 実社会を生き抜く力を養う企業と連携した授業
- 学びの伴走者による手厚い学習サポート
- 多様な進路対応
「このまま留年や中退になったらどうしよう」不登校になると誰もがそのような気持ちになるのは当然です。HR高等学院は、そんな悩みや迷いを抱える高校生や保護者の方にこそ、知ってほしい学校です。
転入にはこれまでの出席日数や成績は問われず、誰でも新しい一歩を踏み出すことができます。通学スタイルは完全オンラインから週5日の通学まで自由に選択可能なため、集団での授業が苦痛だったり、毎日通学する自信がない人でも安心して学び続けることができます。(※通学日数は半年ごとに変更可です。)
社会で活躍する大人たちが“伴走者”となって、学習や生活の悩みに寄り添ってくれるのも心強いポイントです。
また、カリキュラムは、全日制のような決まりきった教科書中心の一斉授業ではありません。たとえば、最新のAI技術やビジネス企画、動画編集、海外とつながるプロジェクトなど実践的でワクワクする学びが満載です。
docomo、LOTTE、CHINTAI、mixiなど名だたる企業と連携した授業を通して「自分らしく生きる力」や「将来に役立つスキル」も自然と身についていきます。
進路についても大学進学、就職、起業などの豊富な選択肢があります。国内の大学はもちろん、海外の有名大学への推薦枠も多数あり、世界を舞台に学ぶチャンスも豊富です。さらに、インターンシップや、起業を目指す学生へのサポートも充実しています。
「不登校だったから…」と自分を責める必要も進学や将来のキャリアをあきらめる必要はありません。
HR高等学院には、不登校の経験をした高校生も多くいます。まずは資料請求やオープンキャンパスや説明会に参加してみて、HR高等学院の雰囲気や他校との違いを感じてみてください!
HR高等学院は「日本でいちばん自由で面白い学校」を目指しています。
最後に
「不登校だからやばい」なんてことはありません。不登校を経験した人の中には、自分の好きなことを見つけて、生き生きと毎日を楽しんでいる人が多くいます。進路の選択肢も思っている以上に多くあります。
将来が閉ざされるわけでも人生が終わるわけでもなく、これからだって、何度でもやり直せるのです。
大切なのは、自分に向き合い、自分に合う道を見つけることです。少しずつ、ゆっくり前に進んでいきましょう。