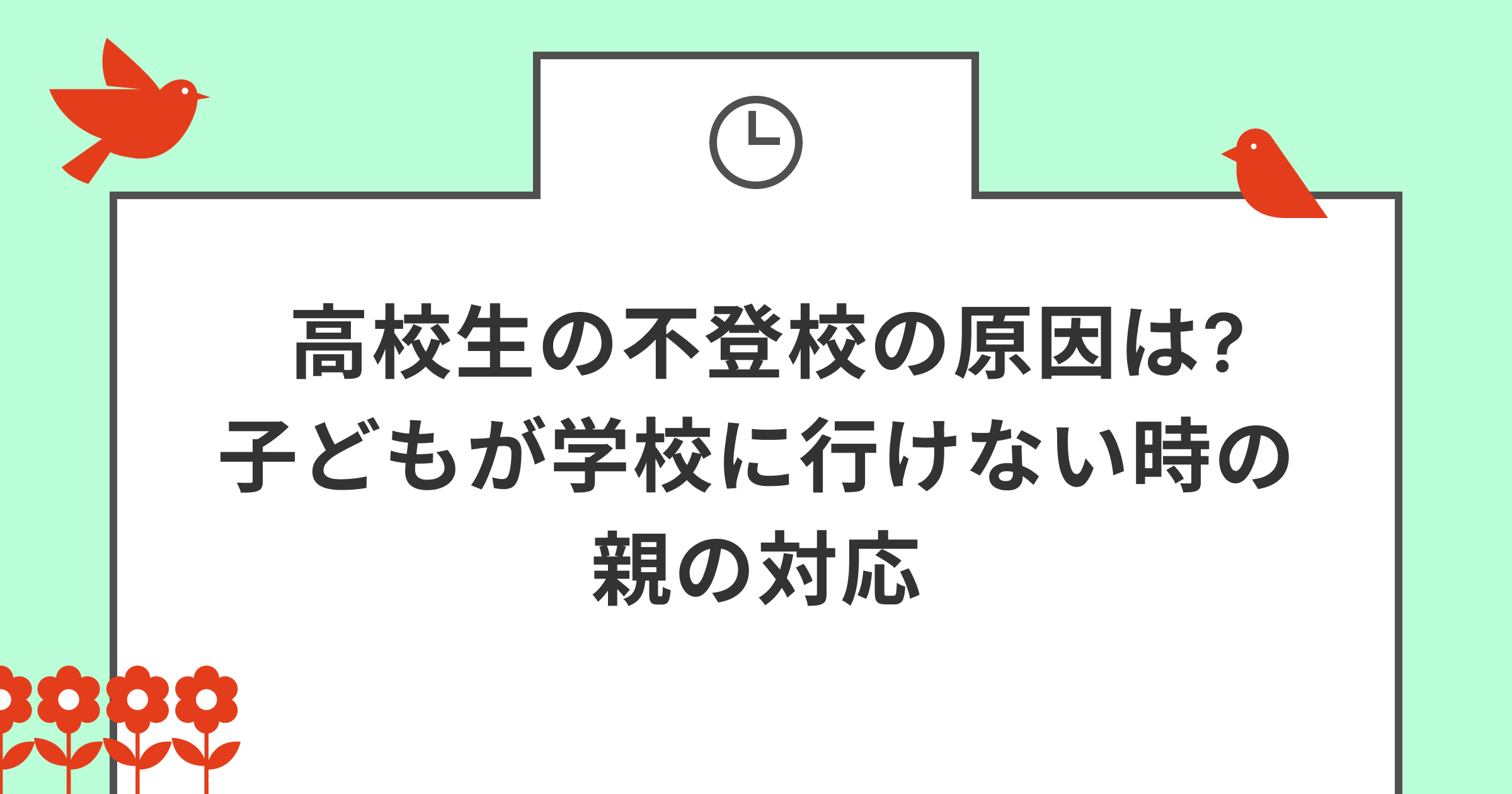高校生の子どもが不登校になり、原因や対応法が分からず悩みを抱える保護者は少なくありません。
文部科学省の調査でも、不登校の高校生は年々増加しています。一方で、「不登校は甘えではないのか」「大学受験はできるのか」など、葛藤や不安でいっぱいになり、本人も親も追い詰められてしまうケースが多いのが現状です。
この記事では、現代の高校生の不登校の実態や原因、親ができる具体的な対応方法、不登校でも目指せる進路などを分かりやすく解説します。
読むことで、今抱えている不安や悩みを少しでも和らげ、親子で前に進むきっかけになれば幸いです。
高校生の不登校の現状とは?
まずは不登校の定義や、実際にどれほどの高校生が不登校の状態にあるのかを見ていきましょう。
不登校の定義
文部科学省では不登校について、次のように定義しています。
“何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により、登校しないあるいはしたくともできない状況にあるために年間30日以上欠席した者のうち、病気や経済的な理由による者を除いた者”
この定義からも、不登校は「怠け」や「甘え」ではなく、さまざまな背景や理由があることが分かります。
不登校を「問題」と捉える前に、まずはその背景を理解することが大切です。
高校生の不登校の割合
文部科学省の令和4年度の調査によると、高等学校における不登校の生徒数は60,575人にのぼり、1,000人当たりの不登校生徒数は、20.4人となっています。これは過去最多を更新しており、年々増加傾向にあります。
また、そのうち90日以上欠席した生徒は、17.2%となっています。
中学生の不登校率よりは低いものの、高校生の場合は退学につながるケースもあるため、早めの対応がより重要とされています。
出典:文部科学省「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果の概要」
高校生と中学生の不登校の違い
中学生の不登校と比べて、高校生の場合は進路や将来に直結するため、保護者としても焦りや戸惑いを感じやすいでしょう。
中学校までは義務教育のため、たとえ出席日数が少なくても原則として進級や卒業が可能です。しかし、高校は義務教育でないため、出席日数や単位の取得が厳しく求められます。
欠席が続くと進級や卒業が難しくなり、留年や退学、転校という選択肢に向き合わなければならないこともあります。また、こうした進路の選択は本人の意思が大切なため、保護者が一方的に決めることができず、より難しさを感じやすいのが現実です。
「社会で生きていける力」を。
- 入学前不登校経験者8割。
入学後登校率89% - ぷよぷよ、モンスト開発者、
日本一になった起業家
から直接学べる - docomo、Lotte、Mixiなど
大企業と連携したプロジェクト型学習

高校生の不登校の原因
高校生が不登校になる背景には、さまざまな要因が関係しています。ここでは、特によく見られる主な原因について分かりやすく解説します。
- 無気力や理由のない不安
- いじめやクラスメイトとの人間関係
- 生活リズムの乱れや遊び・非行
- 受験や勉強のストレス
- 起立性調節障害
- 体調不良や適応障害
無気力や理由のない不安
高校生の不登校の主な理由として、「無気力・不安」が最も多く挙げられています。文部科学省の調査によると、「学校生活に対してやる気が出ない」と感じている生徒が32.8%にのぼります。
高校入学後の環境の変化や、受験や部活動を頑張りすぎて燃え尽き、やる気を失ってしまう場合があります。また、「理由はないけれど何となく行きたくない」というケースも多く見られます。
このように、無気力の背景には、自己肯定感の低下や将来への不安、心身の疲労など、さまざまな心理的・環境的要因が複雑に絡み合っていることが特徴です。
出典:令和5年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果の概要
いじめやクラスメイトとの人間関係
人間関係の悩みは不登校の原因として非常に多く挙げられます。高校生になると交友関係がさらに複雑になり、グループ内でのトラブルや孤立感に悩むことが多くなります。
特にいじめが解決されないまま続くと、心に深い傷が残り、強い不安や絶望感から体調を崩したり、引きこもってしまったりすることもあるでしょう。
また、担任や教科担当との関係がうまくいかないことから、学校に対して不信感やストレスを感じてしまうこともあります。こうした人間関係の悩みが重なることで、学校が楽しい場所ではなくなり、「行きたくない」と感じて不登校につながることも少なくありません。
生活リズムの乱れや遊び・非行
近年のスマートフォンやインターネットの普及により、夜更かしやゲーム、SNSに没頭する生活が習慣化し、生活リズムが乱れるケースが多く見られます。
また、交友関係が広がることで、悪影響を受けやすくなるケースもあります。たとえば、ゲームセンターやカラオケで深夜まで遊ぶような生活が続くと、昼夜が逆転し登校が難しくなるでしょう。
こうした悪循環が続くとさらに生活リズムが乱れ、不登校や非行といった問題につながる恐れがあります。
受験や勉強のストレス
高校生は、進路選択や将来について真剣に考え始める時期です。大学受験や勉強に対するプレッシャーで、いつも追い詰められていると感じるケースも少なくありません。
特に、進学校に入学したことで成績が思うように伸びない場合や、周囲と比較して劣等感を抱くと、自己否定的な感情が強まります。
このようなストレスが積み重なると、学校生活への意欲を失ってしまいます。
起立性調節障害
起立性調節障害は、立ち上がるとめまいや立ちくらみ、強い倦怠感などが現れる自律神経の不調による病気です。思春期に発症することが多く、特に朝に症状が強く出るため登校が難しくなることがあります。
見た目には健康に見えるため周囲から理解されにくい傾向があり、誤解につながることも少なくありません。そのため、症状がみられる場合は、早めに専門医を受診し、正しい診断と適切な治療を受けることが大切です。
体調不良や適応障害
高校生になると、進路や受験のプレッシャー、友人関係の悩み、自分自身への迷いなど、さまざまな心理的負担が多くなります。
これらのストレスが原因となり、適応障害や、はっきりとした病名がつかない体調不良(不眠・食欲不振・頭痛・腹痛など)として症状が現れることがあります。
病院で医学的な異常が見られない場合、つい無理に登校をさせてしまいがちですが、負担が重なり症状が悪化することもあるため注意が必要です。
適応障害の治療には、休養や環境の調整、カウンセリング、必要に応じた医療的サポートを組み合わせることが大切です。学校を一時的に離れるだけでなく、通学時間や課題の負担を見直すなど、学校と連携しながら対応していくことが求められます。
出典:りんかい月島クリニック「学生のための適応障害の治し方|症状と原因から対処法まで徹底解説」
不登校の高校生への初期対応と親がやるべき対処法
高校生の子どもが不登校になった時の初期の段階での対応方法を紹介します。
- 不登校の高校生への初期対応
- 学校を休むことを責めない
- スクールカウンセラーや先生に相談する
- 不登校支援をしている専門機関に相談する
- 高校の転校(転入)・編入を検討する
不登校の高校生への初期対応
不登校が始まったばかりの時期は、子どもの心身は不安定です。まずは子どもの気持ちに寄り添い、話を無理に聞き出そうとせず、安心して過ごせる家庭環境を整えることが大切です。
また、学校との連絡を保ちながら、子どもが通えなくなった背景や欠席日数、単位の状況などを確認し、今後の対応について学校と一緒に考えていくことも重要なポイントです。
学校を休むことを責めない
不登校の子どもは、「学校に行けない自分」に対して強い罪悪感を抱えていることが多いです。「登校させなければ」と焦るあまり責めたり、理由を問いただしたりすると、かえって心の負担を大きくしてしまいます。
休むことを否定せず、「今はしっかり休んでいい」「それほど深刻に考えなくても大丈夫」といった声かけをすることで、子どもは安心し少しずつ自分の気持ちを話せるようになります。
スクールカウンセラーや先生に相談する
学校は子どもにとって最も身近な存在であり、日々の様子をよく理解しています。そのため、担任の先生やスクールカウンセラーとこまめに連絡を取り相談することも大切です。
担任は、家庭では見せない子どもの一面を知っていることも多く、進路についても具体的なアドバイスをもらえることがあります。
また、心のケアやストレス対処の専門家として配置されているスクールカウンセラーは、子どもだけでなく保護者の相談にも応じています。外部の支援機関を紹介してもらえることもあるので、気軽に相談してみることをおすすめします。
不登校支援をしている専門機関に相談する
専門機関には、さまざまな不登校のケースに対応してきた経験豊富な専門家がいます。
これらの機関では、子どもの心のケアや対応方法、学習支援、家庭外で安心できる居場所の提案など、幅広い支援を受けることができます。
以下は、相談できる公的機関や民間の支援団体の一例です。
第三者の立場から状況を客観的に見てもらうことで、家庭内では気づきにくい課題や改善策が明らかになることもあります。
不登校は一人で解決できる問題ではありません。一人で抱え込みすぎず、周囲の力を借りることも大切です。
高校の転校(転入)・編入を検討する
学校生活への復帰は、必ずしも元の学校に戻ることだけが選択肢ではありません。人間関係など学校環境に原因がある場合は、たとえ学校に戻っても根本的な問題が解決せず、再び不登校になってしまうこともあります。
転校や編入で環境を変えることで、不登校のきっかけとなった問題が解決することもあります。ただし、全日制高校や定時制高校の場合は入学できる時期が決まっているため、転校や編入のタイミングには注意が必要です。
一方で、通信制高校では、年間を通じて転入や編入を受け入れている学校も多く、時期の融通が利きやすいのが特徴です。
登校頻度や学習スタイルを選べ、毎日の通学が必須でない学校も多くあります。全日制だけにこだわらず、自分に合う環境を優先し最適な進路を検討することが大切です。
高校の不登校による単位への影響
高校で不登校が続いた場合、単位はどうなるのかが気になる方も多いでしょう。
高校での単位取得には、主に「出席日数」と「成績」の2つの条件を満たす必要があります。これらの要件をクリアできない場合、留年する可能性があります。
- 多くの学校では授業の3分の2以上の出席が必要
- 各科目で一定の評価の取得が必要
多くの全日制高校では、年間の授業日数のうち、実際に出席した日数が3分の2以上であることが求められます。たとえば、年間授業日数が190日の場合、少なくとも約127日以上の出席が必要です。
したがって、63日以上の欠席があると、単位を取得できず進級や卒業が難しくなる可能性があります 。
また、定期テストや課題の提出などによる成績評価も重要です。一般的には、各科目で5段階評価の「2」以上を取得することが求められます。
不登校が続くと、定期テストを受けなかったり、課題の提出ができなかったりすることで成績面でも単位取得が難しくなります。その結果、留年や中退につながるケースも少なくありません。
不登校の状態が続く場合は、早めに学校や支援機関に相談し、今後の進路や学習方法を一緒に考えることが大切です。
「社会で生きていける力」を。
- 入学前不登校経験者8割。
入学後登校率89% - ぷよぷよ、モンスト開発者、
日本一になった起業家
から直接学べる - docomo、Lotte、Mixiなど
大企業と連携したプロジェクト型学習

不登校の高校生の進路
高校で不登校になったとしても、進路の選択肢は複数あります。ここでは、不登校の高校生でも目指せる進学の方法について紹介します。
学校復帰をして卒業する
不登校から再び学校生活に戻り、卒業を目指すことができれば、それが理想的な形です。復帰を考える際は、まず心身の状態を整えることが大切です。焦らず、自分のペースで登校を再開できるよう、学校や家族と相談しながら少しずつ前に進んでいきましょう。
教室での授業が難しい場合は、別室での学習や個別対応など、学校側に対応を相談することもできます。しかし、やはり学校への復帰が難しいと感じた場合は無理をせず、転校や通信制高校への転入など、次の選択肢を前向きに検討してみてください。
大切なのは、自分に合った方法で無理なく卒業を目指すことです。
大学・短大・専門学校へ進学する
たとえ不登校が続いて単位が取れず、高校を中退してしまったとしても、進学の道が閉ざされるわけではありません。「高等学校卒業程度認定試験(高卒認定)」に合格すれば、大学や専門学校の受験にチャレンジすることができます。
高卒認定試験は、年度末までに16歳以上であれば、高校に通っていなくても受験できます。試験は年に2回(8月と11月)実施されているので、自分のペースで準備できるのも魅力です。
合格すれば、「高校卒業と同等以上の学力がある」と認められ、進学や、高卒以上が条件の資格試験など、さまざまな道が開けます。
高等学校卒業程度認定試験については、下記の文部科学省公式ページに詳細が掲載されていますので、興味がある場合は調べてみましょう。
出典:文部科学省「高等学校卒業程度認定試験(旧大学入学資格検定)」
就職
就職を目指すという選択肢もあります。たとえば、不登校の状態でも、学校や保護者の許可があればアルバイトやインターンシップを通じて社会経験を積むことができます。また、高校を中退した後に就職を目指すことも可能です。
ただし、中卒のままだと応募できる仕事が限られることがあります。「高等学校卒業程度認定試験(高卒認定)」に合格すれば、高卒と同等の資格として幅広い職種に応募できるようになり、就職先の選択肢が広がります。
就職活動を進める際は、ハローワークや若者サポートステーションなどの支援機関を活用しながら、自分に合った働き方や職場を見つけていくことが大切です。
不登校の高校生には通信制高校がおすすめ
不登校の高校生にとって、通信制高校への転入や編入はおすすめの選択肢の一つです。ここでは、通信制高校と全日制高校との違いなどの概要や、不登校経験者に向いている理由を説明します。
通信制高校の基本情報
- 通学スタイルが多様
- 転入・編入の時期が柔軟
- 卒業には在籍年数と単位修得が必要
- 卒業により高卒資格が取得可能
- 年齢や背景が多様な学生が在籍
- 専門コースや特色あるプログラムも充実
通信制高校には、全日制とは異なる特徴があります。最大の違いは「単位制」を採用している点です。全日制の「学年制」では、決められた単位を取得しないと進級できず留年もありますが、通信制では学年の区切りがないため、「留年」という概念もありません。
卒業には、通算3年以上の在籍期間と74単位以上の修得が必要です。なお、この在籍期間には、前の高校での在籍期間も合算できます。卒業後は、全日制と同じ高等学校卒業資格が取得可能です。
通信制高校には、中学卒業直後の学生だけでなく、社会人や転入・編入で入学する学生も多く在籍しています。そのため、年齢や背景が異なる人同士で交流できる点も魅力です。近年はeスポーツ、アート、プログラミング、美容など、専門コースや特色あるプログラムも増えています。
こうした柔軟な受け入れ体制が評価され、通信制高校の学校数や生徒数は年々増加傾向です。文部科学省の令和6年度調査によると、全国で303校、生徒数は290,087人と過去最多を記録しています。今や高校生全体の約11人に1人が選ぶ時代となりました。
このように、通信制高校は、さまざまな背景を持つ学生のニーズに応える教育環境が整っています。
通信制高校が不登校の高校生に向いている理由
「学校に行くのがつらい」「クラスに馴染めない」そんな悩みを抱える高校生にとって、通信制高校は新たな選択肢となります。通信制高校が不登校経験のある高校生に向いている理由は、次の通りです。
- 入学条件が厳しくないため入学しやすい
- 登校日数や学習スタイルを選べる
- 不登校経験者も多く通学している
- サポート体制が充実している
- 転入・編入の受け入れ実績が豊富
- 自分の興味や目標に合わせて学べる
通信制高校の入学選考は、面接や作文、書類審査が中心で筆記試験は実施しない学校がほとんどです。また、高校での出席日数に関しては原則問われません。出席日数より意欲や目標を重視するため、不登校の場合でも入学しやすい環境です。
また、登校日数や学習方法を自分で選べるため、「体調が不安定」「人間関係が苦手」といった悩みがあっても、自分のペースで無理なく学ぶことができます。
不登校の経験を持つ学生が多く在籍しているため、同じ経験をした仲間と悩みを分かち合いやすいです。さらに、カウンセラーや経験豊富な教員が寄り添い、学習や生活面での不安にもきめ細かく対応しており、安心して学校生活を送ることができます。
授業内容も全日制とは異なり、基礎学力のサポートだけでなく、進学や資格取得を目指すコースや専門分野など、自分の興味や将来の目標に合わせた多彩なプログラムが用意されています。「自分に合う学び方」を見つけやすい環境が整っていることも、通信制高校ならではの大きな魅力です。
不登校の経験があっても「環境を変えて学びたい」と思ったとき、通信制高校はその気持ちをしっかり受け止めてくれる場所です。
通信制高校サポート校「HR高等学院」をご紹介
HR高等学院は、不登校経験のある高校生の「もう一度学びたい」という気持ちに寄り添う通信制高校サポート校です。2025年4月に新設され、自由な学習スタイルと実践的な教育が注目を集めています。
- 不登校経験があっても通いやすい柔軟な学習環境
- 学力や出席日数を問わない入学選考
- オンラインのみや週5通学まで選べる自由な学習スタイル
- 実社会を生き抜く力を養う企業と連携した授業
- 学びの伴走者による手厚い学習サポート
- 海外大学推薦枠を含む多様な進路対応
HR高等学院は、今通っている高校からの転入や、高校中退をしてからの編入にも柔軟に対応しています。入学時に出席状況は問われず筆記試験も行わないため、不登校経験があっても新たなスタートを切ることが可能です。
HR高等学院は不登校の経験がある学生でも生き生きと学べる環境が整っています。
通学スタイルは完全オンラインから週5日の通学まで自由に選択できるため、ライフスタイルや体調に合わせて自分のペースで学習を進められます。
さらに、先生ではなく実社会で活躍する大人が「伴走者」として寄り添い、学びを支える独自の教育体制を取り入れています。受け身の学習ではなく、自分で考え行動する力を自然と身につけられる環境が整えられています。
また、カリキュラムは、全日制のような決まりきった教科書中心の一斉授業ではありません。たとえば、最新のAI技術やビジネス企画、動画編集、海外とつながるプロジェクトなど実践的でワクワクする学びが満載です。
企業とのコラボ授業や現役の専門家によるワークショップもあり、学校で得た知識を社会で即戦力として活かせます。
進路についても大学進学、就職、起業などの豊富な選択肢があります。国内の大学進学はもちろん、海外の有名大学への推薦枠も多数あり、世界を舞台に学ぶチャンスも豊富です。さらに、インターンシップや、起業を目指す学生へのサポートも充実しています。
専門スタッフが一人ひとりに寄り添い、希望に合った進路を一緒に見つけていきます。「通信制だから大学進学や就職が難しいのでは」と進路をあきらめる必要はありません。
HR高等学院の特色ある教育や学生への手厚いサポートは、教育専門メディア「東洋経済education」でも大きく取り上げられています。記事内では、ホームページ上に掲載されていない、学生のリアルな声や学校開設の秘話などが詳しく紹介されていますのでぜひご覧ください。
出典:東洋経済education(企業や起業家と連携、興味を探究してキャリアにつなげる「通信制サポート校」ができた訳)
「今の高校が合わない」「不登校で悩んでいる」そのような方を、HR高等学院は全力で応援します。まずは資料請求や授業見学、あるいは説明会に参加して、全日制高校や他の通信制高校との違いを体感してみてください。
学校概要の詳しい説明や学生のインタビューは、以下の動画でも紹介していますのでぜひご覧ください。
最後に
この記事では、現代の高校生の不登校の実態や原因、不登校の子どもに対して親ができる具体的な対応方法、不登校でも目指せる進路を具体的に解説しました。
不登校は決して特別なことではなく、誰にでも起こりうることです。大切なのは、子どもを否定するのではなく、「どうすれば安心して過ごせるか」「どんな学び方や進路が合っているのか」を一緒に考えていくことです。
また、親だけで悩みを抱え込まず、学校や専門機関など周囲の力を借りることで、新しい選択肢が見えてくることもあります。
高校生という時期は、将来への不安が大きくなりがちですが、今は進路選択の幅も広がり、どんな状況からでも自分の道を切り拓くことができる時代です。
子どものペースを受け入れ、必要なサポートを取り入れながら、少しずつ前へ進んでいきましょう。