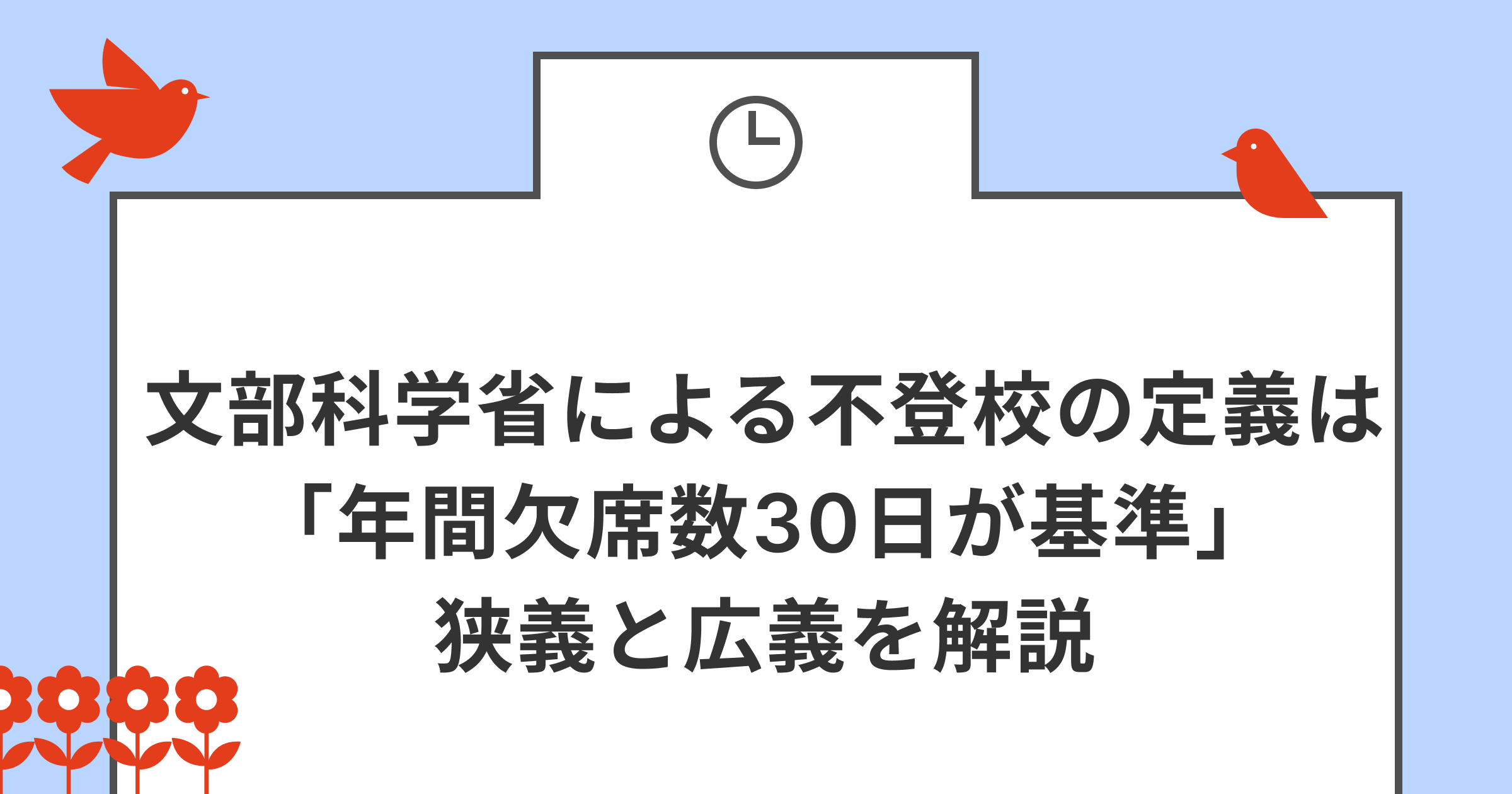学校を休みがちな方の中には、「自分は不登校に該当するのだろうか」と不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
「不登校」という言葉はよく耳にするものの、正確な定義や基準については、意外と知られていません。
不安を解消して前向きに行動していくためにも、まずは不登校の定義を正しく理解しておきましょう。
本記事では、不登校の定義や登校拒否との違い、不登校になる理由などを詳しく解説します。
子どもが不登校になってしまった場合の対応も紹介するので、ぜひ最後までご覧ください。本記事を参考にすれば、不安が軽くなり、取るべき行動が見えてくるはずです。
不登校の定義は?
不登校の定義を以下の項目に沿って解説します。
- 不登校は年間欠席数が30日以上?
- 文部科学省が定義する不登校の基準
- 法律上の不登校の定義
不登校という言葉は日常的によく使われますが、その正確な定義については意外と知られていません。
狭義の不登校は文部科学省が統計調査において使用している定義で、具体的な欠席日数の基準が設けられています。
一方、広義では、欠席日数にかかわらず登校しない・できない状況全般を指します。ここでは、不登校の定義を詳しく確認してみましょう。
不登校は年間欠席数が30日以上?
不登校の基準として多く用いられるのが、「年間欠席数30日以上」という数値です。
この数値は文部科学省が全国の児童生徒の実態を把握するために設定した統計上の基準で、教育政策や支援体制の整備にも活用されるものです。
なお、30日以上の欠席という基準は、単発的な欠席の合計ではなく、継続的に登校していない状態を示します。
また、不登校の日数が30日間に満たない場合でも、背景にある要因や状況によっては、不登校状態であると捉えられるケースもあります。
文部科学省が定義する不登校の基準
文部科学省が定義する不登校の基準は、以下のとおりです。
何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により、登校しないあるいはしたくともできない状況にあるため年間30日以上欠席したもののうち、病気や経済的な理由によるものを除いたもの
この定義からわかるように、文部科学省が示す不登校の基準は、単純に欠席日数だけで決まるものではありません。
欠席日数が30日以上であったとしても、病気治療のためや家庭の経済的な事情による長期欠席は、文部科学省の不登校の定義からは除外されます。
法律上の不登校の定義
法律における不登校の定義は、文部科学省の定義とは少し異なります。
「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律」では、不登校児童生徒を以下のように定義しています。
相当の期間学校を欠席する児童生徒であって、学校における集団の生活に関する心理的な負担その他の事由のために就学が困難である状況として文部科学大臣が定める状況にあると認められるもの
引用元:e-GOV法令検索|義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律
法律上の定義の大きな特徴は、欠席日数に関する具体的な基準が設けられていない点です。
心理的な負担を感じていたり、その他の理由で学校に通うことが難しかったりする場合には、年間の欠席日数が30日に満たなくても、不登校であると捉えられています。
狭義の不登校とは?
狭義の不登校とは、主に文部科学省が全国的な統計調査を実施する際に用いている定義を指します。
文部科学省の定義では、「年間30日以上の欠席」という明確な数値基準が設定されています。
数値基準が明確であれば、全国の不登校児童生徒の数を正確に把握し、増減を経年的に分析することが可能です。
例えば、2023年度に行われた調査では、小・中学校における不登校児童生徒数は346,482人に上り、在籍する児童生徒全体に占める割合は3.7%に達したと報告されています。
また、狭義の定義は、国や自治体が教育政策を立案したり、支援体制を整備したりする上で、とても重要な役割を果たしています。
全国で共通の基準を共有することで、地域が抱える課題を明確にして、より効果的な対策につなげているのです。
「社会で生きていける力」を。
- 入学前不登校経験者8割。
入学後登校率89% - ぷよぷよ、モンスト開発者、
日本一になった起業家
から直接学べる - docomo、Lotte、Mixiなど
大企業と連携したプロジェクト型学習

広義の不登校とは?
広義の不登校は、欠席日数や登校の状況などの表面的な事柄だけでなく、子どもの心身の状態や、取り巻く社会的な背景なども含めて総合的に判断されるものです。
例えば、完全に学校を休んではいないものの、週に数日しか登校できていない場合は、広義の不登校に含まれる可能性があります。
また、学校には行っているけれど教室に入れない、一日の大半を保健室で過ごしている、あるいは遅刻や早退を頻繁に繰り返しているなど、学校生活に対して何らかの不安や困難を感じている状況も同様です。
不登校と登校拒否の違い
不登校と登校拒否はしばしば混同されますが、意味が異なります。
不登校とは、心理的・身体的な理由で、30日間以上にわたり学校を欠席している状態、あるいはそれに準ずる状態を指します。
一方で、登校拒否とは、子ども自身がはっきりと「学校に行きたくない」という意思を示した上で、学校に行かない状態を指すのが一般的です。
登校拒否という言葉は、不登校が社会問題として認識される以前から使われてきました。
当時は、学校へ行かないのは本人の意志による行動であると捉えられる傾向があったようです。
現在では、学校へ行けない背景には、複雑な要因が絡み合っているとが理解されており、登校拒否という表現は必ずしも適切ではないとの意見も見受けられます。
準不登校とは?
準不登校に明確な定義はありませんが、一般的に欠席日数が15日以上30日未満の状態を指します。また、保健室登校、頻繁な遅刻や早退を繰り返す状態も含まれます。
準不登校は文部科学省が定義する不登校には該当しませんが、将来的に不登校に移行するリスクが高い状態です。
しかし、完全な不登校状態に移行する前に適切な支援を行うことで、学校生活に復帰できる可能性を高められます。
準不登校状態を解消するアプローチの例として、学校のスクールカウンセラーとの面談や家庭内での対話、学習環境の調整などが挙げられます。
「社会で生きていける力」を。
- 入学前不登校経験者8割。
入学後登校率89% - ぷよぷよ、モンスト開発者、
日本一になった起業家
から直接学べる - docomo、Lotte、Mixiなど
大企業と連携したプロジェクト型学習

不登校とひきこもりの違い
不登校とひきこもりは混同されがちですが、両者は異なる状態を指します。不登校は、主に学校を長期間欠席している状態を指し、その理由はさまざまです。
一方、ひきこもりは仕事や学校に行かず、6ヶ月以上自宅に閉じこもっている状態です。
不登校の学生であっても、家族との外出や習い事への参加、友人との交流などがあれば、ひきこもり状態ではありません。
なお、ひきこもりは「狭義のひきこもり」「準ひきこもり」「広義のひきこもり」の3種類に分類されます。それぞれの定義は下表のとおりです。
不登校が長期化すると、ひきこもり状態に移行するリスクがあるため、適切な支援により社会とのつながりを維持するのが大切です。
出典:厚生労働省|「ひきこもりや不登校」というサイン
出典:日本女子大学|「ひきこもり」について知っていますか?
不登校の現状
日本における不登校の現状は、深刻化の一途をたどっています。
2023年度の文部科学省調査によると、小・中学校における不登校児童生徒数は346,482人とされており、11年連続で増加し続けています。
前年度と比較すると、不登校児童生徒数は47,434人(15.9%)増加し、過去最多を記録しました。
また、在籍児童生徒に占める不登校の割合も、増加傾向にあります。小学校では21.4人(1000人当たり)、中学校では67.1人(1000人当たり)であり、特に中学生の不登校率が高い状況が続いています。
高等学校における不登校生徒数も68,770人となり、前年度から8,195人(13.5%)増加している状態です。
在籍生徒に占める割合は2.4%で、義務教育段階と比較すると低い数値ですが、それでも増加傾向にあることは間違いありません。
出典:文部科学省|令和5年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果の概要
子どもが不登校になる原因
子どもが不登校になる原因の例は、以下のとおりです。
- クラスメイトや友人とのトラブル
- 学校環境が合わない
- 担任教師や周りの大人と合わない
- 無気力でやる気が起きない
- 勉強がうまくいっていない
- 遊び・非行などの学校外でのトラブル
不登校の原因はさまざまです。また、複数の要因が複雑に絡み合って不登校に至るケースも少なくありません。
不登校状態を解消するには、表面的な症状だけでなく背景にある要因を理解し、包括的にサポートするのが大切です。ここでは、子どもが不登校になる原因を詳しく解説するので、参考にしてください。
クラスメイトや友人とのトラブル
クラスメイトや友人とのトラブルは、不登校の代表的な要因の一つです。
文部科学省の調査では、小中学校における不登校の原因のうち「いじめ被害を除く友人関係をめぐる問題」が13.3%、「いじめの被害」が1.3%の割合であると報告されています。
なお、友人関係のトラブルにはさまざまな形が存在します。
例えば、仲の良かった友人との些細な喧嘩をきっかけに関係が悪化したり、グループ内での立場の変化により居心地の悪さを感じたりするケースは少なくありません。
また、SNSを通じたコミュニケーションの問題や、学習能力・運動能力の差による劣等感なども友人関係に影響を与える可能性があります。
特に思春期の学生にとって、友人関係は自己アイデンティティの形成に大きく関わります。友人からの承認や所属感は心の安定には必要不可欠です。
出典:文部科学省|令和5年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果の概要
参考までに、弊校HR高等学院CEOの山本将裕と共同設立者の成田修造氏による「不登校と学校と社会で求められるコミュニケーションの違い」をテーマとしたYoutubeを紹介します。学校でのコミュニケーションは共通の目的がない中で不特定多数の人と話すことであり、自分の興味関心とずれがあったときに居心地の悪さを感じさせているのではないかと議論しており、大変興味深いです!こちらもぜひ視聴してみてください!
学校環境が合わない
学校の環境そのものが合わないと感じ、不登校になる学生も少なくありません。
例えば、校則が厳しすぎる、学校の教育方針に疑問を感じるなど、学校のルールや雰囲気が自分にあわず、登校意欲が削がれている場合があります。
また、学校行事が活発すぎて馴染めない学生や、大人数のクラスや騒がしい教室環境が苦手な学生もいるでしょう。
特に、発達障害の特性が強い学生にとっては、一般的な学校の環境が大きなストレスとなりえます。
文部科学省の調査では、不登校の小中学生のうち2.0%の学生から「学校のきまり等に関する相談があった」と報告されています。
出典:文部科学省|令和5年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果の概要
担任教師や周りの大人と合わない
学校環境や教師との関係における問題も、不登校につながりがちです。教師との関係における問題には、指導方法の違いや価値観の相違、コミュニケーションの不足などが挙げられます。
自分の学習スタイルや性格に合わない指導を受けると、学校への不信感や不安感が高まってしまいます。また、教師や保護者からの何気ない一言で、心に傷を負ってしまう学生も少なくありません。
文部科学省の調査では、小中学校における不登校の原因のうち「教職員との関係をめぐる問題」の割合が3.0%であると報告されています。
出典:文部科学省|令和5年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果の概要
無気力でやる気が起きない
不登校の原因でもっとも多いのが、学校生活に対する意欲の消失です。
文部科学省の調査によると、小中学校における不登校の理由のうち「学校生活に対してやる気が出ない」が全体の32.2%を占めています。
無気力状態は単なる怠けとして捉えられがちですが、実際にはさまざまな要因が複雑に絡み合った結果として現れるのが一般的です。
例えば、学習内容についていけない不安や家庭での過度なプレッシャーや期待、保護者や教師に関心を持ってもらえないことなどが、やる気の低下につながります。
また、生活リズムの乱れや睡眠不足、栄養不足などで、意欲や集中力が低下しているケースも少なくありません。
出典:文部科学省|令和5年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果の概要
勉強がうまくいっていない
学習面での問題から、不登校につながっているケースも多々見受けられます。
文部科学省の調査では、不登校の小中学生のうち15.2%に「学業の不振や頻繁な宿題の未提出が見られた」と報告されています。
学習がうまくいかない原因はさまざまです。例えば、基礎的な学力の不足、学習方法の未習得、注意集中の困難などが挙げられます。
また、発達障害や学習障害などの特性により、一般的な指導方法では学習内容が理解できない場合もあります。
学習面での支援では、子どもの学習状況や特性を正確に把握することが欠かせません。
どの教科のどの部分でつまずいているのか、どのような学習方法が効果的なのかを見極める必要があります。
出典:文部科学省|令和5年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果の概要
参考までに、弊校HR高等学院CEOの山本将裕と共同設立者の成田修造氏による「不登校児童と内申点」をテーマとしたYoutubeを紹介します。「そもそも内申点を本当に気にする必要があるのか?」について議論しており、興味深いです!こちらもぜひ視聴してみてください!
遊び・非行などの学校外でのトラブル
学校外での問題行動から、不登校に発展することもあります。
遊びや非行に関する問題には、ゲームやインターネットへの過度な依存、夜遊びによる生活リズムの乱れ、問題のある友人関係の存在などが挙げられます。
これらの問題行動は、学校生活への不適応や家庭での居場所のなさから逃避する手段として選択されているケースが少なくありません。
また、承認欲求や刺激への欲求が満たされない結果として現れる場合もあります。
このような学校外での問題行動を解決するには、背景にある心理的なニーズを理解することが大切です。
多くの場合、行動を厳しく制限するだけでは解決にならず、むしろ親子関係が悪化する可能性があります。
なお、文部科学省の調査では、不登校の小中学生のうち3.4%から「遊び・非行に関する情報・相談が合った」と報告されており、一定数の学生が学校外でのトラブルを抱えている事実が判明しています。
出典:文部科学省|令和5年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果の概要
「社会で生きていける力」を。
- 入学前不登校経験者8割。
入学後登校率89% - ぷよぷよ、モンスト開発者、
日本一になった起業家
から直接学べる - docomo、Lotte、Mixiなど
大企業と連携したプロジェクト型学習

子どもが不登校になってしまった場合の対応
子どもが不登校になってしまった場合に、保護者が取るべき対応は以下のとおりです。
- 無理やり学校に行かせようとしない
- 子どもと会話する時間を増やす
- 子どもの自己肯定感を高める
- 専門機関やカウンセラーに相談する
- 学校以外の場所を探す
子どもが不登校になってしまった場合、保護者はどうしても混乱や不安を感じてしまうでしょう。しかし、適切な対応を取ることで、状況を改善することは十分可能です。
不登校への対応で大切なのは、子どもを責めたり無理強いしたりするのではなく、ありのままの状況を受け入れた上で必要なサポートを行うことです。
短期間で不登校問題の解決を求めるのではなく、子どもの心身の回復と成長を第一に考えた支援を、長期的な視点で継続するのが大切です。
また、家庭内だけで抱え込まず、学校や専門機関と連携しながらサポートしていく意識を持ちましょう。
ここでは、子どもが不登校になってしまった場合に、保護者が取るべき対応を詳しく解説します。
無理やり学校に行かせようとしない
不登校になった子どもを無理やり学校に行かせようとするのは避けるべきです。
「学校に行かなければダメ」「みんなは行っているのに」といった言葉でプレッシャーをかけると、子どもの心をさらに追い詰めてしまいます。
また、登校を強制しても、不登校の背景にある根本的な問題が改善されるわけではありません。
むしろ、保護者から理解してもらえないと新たなストレスが加わり、子どもが家庭内での居場所まで失ってしまう危険性があります。
そのため、まずは子どもが学校に行けない状況を、そのまま受け入れてあげるのが大切です。
「学校に行かなくても大丈夫」という安心感があってこそ、子どもは自分自身と向き合い、前向きに行動できるものです。
子どもと会話する時間を増やす
子どもとの信頼関係を築くために、日常的な会話の時間を意識的に増やすのも大切です。
ただし、学校のことや将来のことばかりを話題にするのではなく、子どもの興味・関心に寄り添った自然な会話を心がけましょう。また、会話する際は、子どもの話をじっくりと聞いてあげてください。
保護者が一方的にアドバイスをしたり、問題を解決しようとしたりするのではなく、子どもの気持ちや考えを理解することに重点を置きましょう。
「そうなんだね」「よく話してくれたね」といった共感的な言葉をかけると、子どもは自分の気持ちを受け入れてもらえたと感じられます。
日常的な対話を通じて、子どもの心の変化や成長を感じ取ると、適切なタイミングで必要な支援を提供することが可能です。
子どもの自己肯定感を高める
不登校の学生の多くは、自己肯定感が低下しています。学校に行けない自分を責めたり、他の子どもと比較して劣等感を感じたりすることが、さらなる心の不調を招く悪循環を生み出します。
そのため、保護者は子どもが自己肯定感を回復し、自分らしさを取り戻せるようサポートをするべきです。
自己肯定感を高めるためには、子どものよいところや努力を認めている事実を、言葉で伝えるのが効果的です。
例えば、「今日は朝早く起きられたね」「お手伝いしてくれてありがとう」など、小さなことでも積極的に褒めることで、子どもは自分の価値を実感できます。
また、子どもが興味を持っていることや得意なことを見つけて、それらを伸ばす機会を提供するのも大切です。
絵を描くのが好きなら画材を揃えてあげる、音楽に興味があるなら楽器に触れる機会を作る、料理が得意なら一緒にキッチンに立つなど、子どもの個性を大切にしたサポートを通じて自信を育てていきましょう。
専門機関やカウンセラーに相談する
保護者だけで問題を抱え込むのではなく、専門的な知識と経験を持つ支援者の力を借りることで、より効果的に子どもをサポートできます。相談先の例は以下のとおりです。
- スクールカウンセラー
- 教育相談センター
- 教育支援センター
- 民間のカウンセリング機関
まずは、教育現場の実情に詳しいスクールカウンセラーに相談するのがよいでしょう。
各自治体が設置する教育相談センターでは、教育上の相談、就学相談、進路相談、養育相談など、子どもの教育に関するさまざまな問題を相談可能です。
教育委員会が設置する教育支援センターでは、不登校の学生への学習支援や集団活動の機会を提供しています。
民間のカウンセリング機関や不登校支援の専門団体に相談すれば、個々の状況に応じたきめ細かな支援に期待できます。
また、抑うつや不安障害、発達障害などが疑われる場合には、医療機関への相談が必要です。
相談先を選ぶ際は、子どもとの相性やアクセスのよさ、費用などを総合的に考慮しましょう。
出典:東京都教育委員会|不登校児童・生徒への効果的な支援事例について
出典:文部科学省|不登校に関する地元の相談窓口
学校以外の場所を探す
不登校であっても学校以外の居場所があれば、社会とのつながりを維持しながら、自分らしく生きていくことが可能です。
例えば、フリースクールでは、少人数制で個別のニーズに応じた学習支援を行っており、子どものペースにあわせた教育を受けられます。
また、同じような経験を持つ仲間と出会うことで、社会性の発達や自己肯定感の回復にもつながるでしょう。
その他にも、スポーツクラブや習い事の教室、通信制高校サポート校など、子どもが興味を持てる活動の場を見つけるのも有効です。
学校以外の居場所を見つける際も、子どもの意思を尊重し、無理強いしないことが大切です。
なお、弊校HR高等学院では、高校生の進路選択をもっと開かれた多様なものにできるよう、充実したサポート体制を整えています。
資料請求やHR高等学院についてのお問い合わせ等は、こちらのフォームからご連絡ください。
不登校の定義についてのよくある質問
不登校の定義についてのよくある質問は、以下のとおりです。
- 不登校の定義と認識は?
- 不登校はどこからが不登校ですか?
- 小学校を30日休むとどうなる?
- 不登校の7つのタイプは?
ここでは、不登校に関してよく寄せられる質問について、具体的に回答していきます。
不登校の定義と認識は?
不登校の定義と社会的な認識は、時代とともに変化しています。
現在の不登校の定義は「何らかの心理的、情緒的、身体的、あるいは社会的要因・背景により、児童生徒が登校しないあるいはしたくともできない状況にある者で、年間30日以上欠席した者のうち、病気や経済的な理由による者を除いたもの」とされています。
社会的な認識も一昔前と比べると大きく変化しており、かつては怠け・甘えとして捉えられがちでしたが、現在では複雑な要因があり登校できない状況であると認識され始めました。
また、不登校は決して恥ずかしいことではなく、個々が抱える問題に対して、適切な支援を提供すべきであるとの認識も広がりつつあります。
小中学校の不登校児童生徒数が346,482人、高等学校における不登校生徒数が68,770人に達している事実からも分かるように、不登校は決して珍しいことではありません。
多様な学習機会の確保や個別のニーズに応じた支援の重要性が社会的に認められ、さまざまな取り組みが進められています。
引用元:文部科学省|不登校の現状に関する認識
出典:文部科学省|令和5年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果の概要
不登校はどこからが不登校ですか?
文部科学省の定義では、年間30日以上の欠席が不登校の基準です。
法律上の定義では欠席日数の基準がないため、心理的・情緒的・身体的・社会的要因により登校困難な状況であれば、欠席日数に関わらず不登校として捉えられます。
また、欠席日数が15日以上30日未満の状態や、保健室登校や遅刻・早退を繰り返している状態が、準不登校と呼ばれる場合もあります。
出典:文部科学省|不登校の現状に関する認識
出典:e-GOV法令検索|義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律
小学校を30日休むとどうなる?
小学校で年間30日以上欠席した場合、統計上は不登校として分類されますが、何らかのペナルティが課せられるわけではありません。
義務教育段階では、出席日数が不足していても、進級や卒業が認められるのが一般的です。
ただし、授業を受けていない分の学習内容について、何らかの形で補う必要があるでしょう。
一般的には、担任教師に相談すれば、家庭学習の方法や補習の機会についてレクチャーしてもらえます。
また、教育支援センターやフリースクールでの学習も、学校復帰への準備に有効です。
なお、小学校での不登校は、早期に適切な対応を行うと復帰できる可能性が高いとされています。
不登校の7つのタイプは?
不登校は要因や特徴により、7つのタイプに分類できます。7つのタイプとそれぞれの特徴は、下表のとおりです。
まず、子どもがどのタイプに当てはまるかを冷静に観察しましょう。一律の対応ではなく、子どもの特性や状況に合わせた個別のアプローチや、長期的な視点を持って焦らずに伴走する姿勢が大切です。
通信制高校サポート校「HR高等学院」をご紹介
学校での偏差値よりも、社会での可能性を - HR高等学院 HR高等学院は従来の詰め込み型の教育ではなく、「探究・越境・共創」を掲げた独自のカリキュラムを採用している通信制高校サポート校です。
企業と連携したプロジェクト型学習や専門ゼミ、各界のトップランナーによるセッションなどを通じて、以下の能力を養います。
- 課題解決力
- 論理的思考力
- コミュニケーション力
HR高等学院の名物授業、「トップランナーセッション」にて、登録者148万人『ReHacQ』のプロデューサー高橋弘樹さんを講師にお呼びした際の講義です。HR高等学院では、様々な業界の第一線で活躍されている社会人を講師に迎え、多様な生き方、キャリアの築き方を学生と一緒に考えたり、学生たちからの等身大の質問に答え直接対話を行う授業を日々行っています。
HR高等学院ではハイブリッド型の学習環境が整えられており、自宅でのオンライン学習と校舎での通学学習を自由に組み合わせできるのが特徴です。
また、学生一人ひとりに寄り添う個別サポートが充実している点も本校の魅力です。
最後に
本記事では、不登校の定義や不登校になる理由、子どもが不登校になってしまった場合の対応などを解説しました。
不登校の原因は学生一人ひとり異なります。複数の要因が複雑に絡みあい、不登校につながっているケースも珍しくありません。
また、不登校の定義や基準はあくまで一つの目安です。大切なのは不登校の原因を正しく把握し、適切なサポートを受けることです。
不登校に悩んでいるのであれば、家庭内で抱え込まず、スクールカウンセラーや専門機関に相談してください。
専門的な知識と経験を持つ支援者の力を借りることで、不登校状態を解消し、子どもが前向きに行動できる可能性を高められます。
もし、「自分らしく学びたい」「学校以外の居場所を見つけたい」という場合は、通信制高校サポート校への入学も検討しましょう。
通信制高校サポート校の「HR高等学院」では、学生一人ひとりの希望や個性に合わせた学習サポートやコーチングを提供しています。
資料請求やHR高等学院についてのお問い合わせ等は、こちらのフォームからご連絡ください。HR高等学院は「日本でいちばん自由で面白い学校」を目指しています!