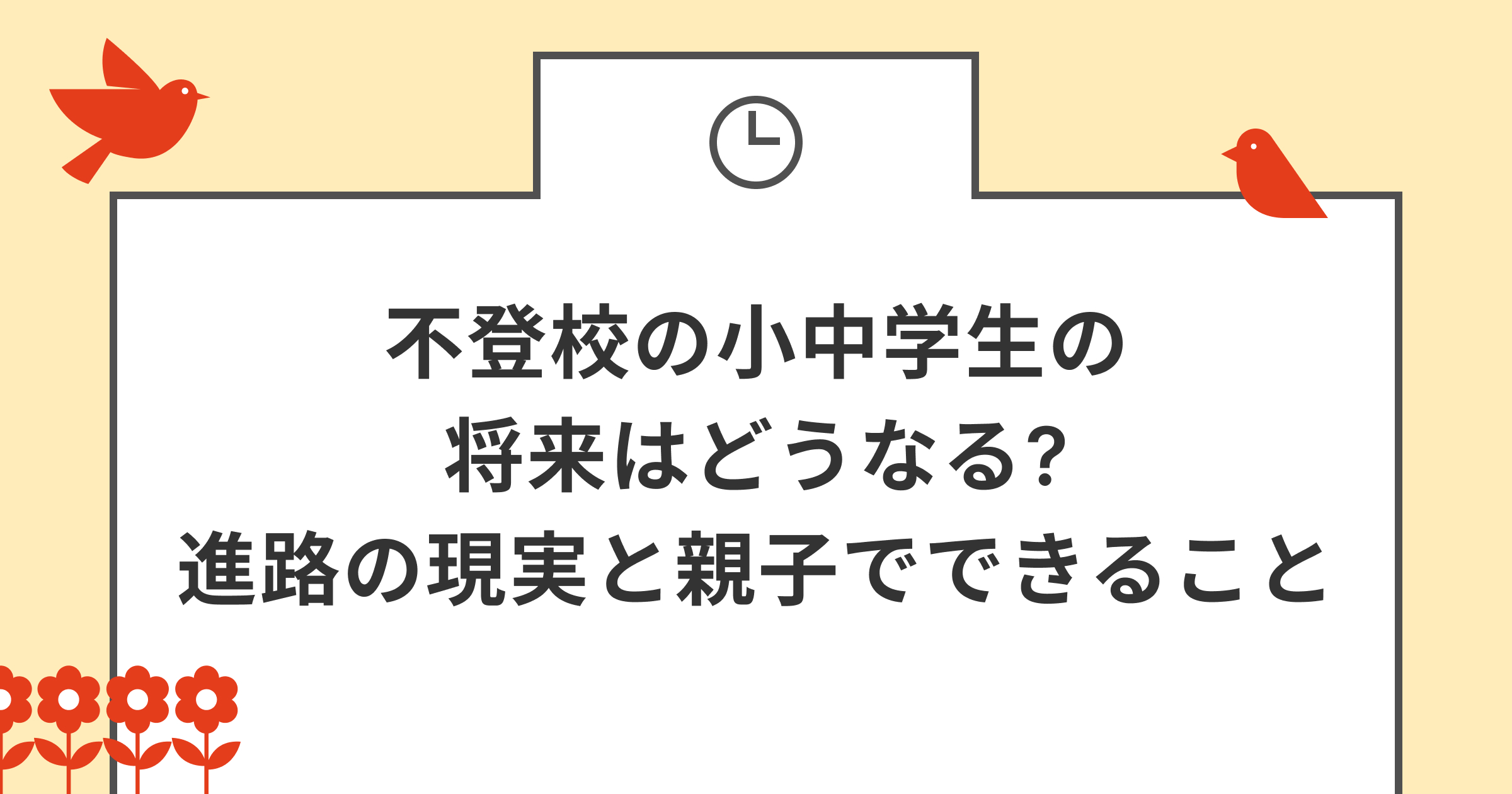小学生や中学生で不登校になると、「将来どうなるのだろうか」と不安になるのは当然です。進学や就職、社会に出てからのことを考えて、心が重くなることもあるでしょう。
しかし、悲観的になりすぎる必要はありません。不登校を経験しても自分に合った学び方や環境を見つけ、大学進学や就職を果たして活躍している人は多くいます。
この記事では、不登校の小中学生が直面しやすい現実をデータや体験談をもとにわかりやすく説明します。さらに、本人と保護者それぞれの立場から「今できること」を具体的に紹介します。
焦らず、自分のペースで一歩ずつ進めばきっと未来は開けます。まずは、今できることに目を向けて、小さな一歩を踏み出してみましょう。
この記事を読むことで、不安が少し軽くなり前向きな気持ちになれるはずです。
不登校の小中学生の将来の現実
不登校が続くと、現実として次のような課題が生じやすくなります。
- 就職先が少なくなる
- 対面でのコミュニケーションが苦手になる
- 引きこもりになりやすくなる
順に説明します。
就職先が少なくなる
文部科学省や総務省の調査によると、不登校だった中学生の20歳時点での「非就学・非就業」割合は18.1%と、同年代(15~19歳)の全国平均2.3%(総務省「就業構造基本調査」)に比べて高い水準です。
ただし、不登校の期間があっても高校を卒業すれば就職先に困ることはほとんどありません。一方で、中学卒業後すぐに就職する場合は、体力が求められる仕事や単純作業が中心となり、選べる職種やキャリアアップの幅が限られる傾向があります。
引用:文部科学省 平成18年度不登校生徒に関する追跡調査報告書(平成26年)
引用:総務省「就業構造基本調査」
対面でのコミュニケーションが苦手になる
不登校の子どもは、学校生活でのコミュニケーションの機会が減ることで、対人関係や会話に苦手意識を持ちやすくなる傾向があると複数の調査や研究で指摘されています。
SNSやチャットなどオンラインでのやり取りが主流の今は、もともと対面が苦手な人も多く、不登校の子どもには特にその傾向が強まりやすいとされています。
その結果、初対面の人と話すことに不安を感じたり、気持ちをうまく伝えられず悩むことが増え、対面での会話を避ける悪循環に陥りやすくなります。
引用:「中学進学に伴う不登校傾向の変化と学校生活スキルとの関連」(五十嵐哲也, 2011)
引きこもりになりやすくなる
不登校が長期化すると、引きこもりになるリスクが高まります。内閣府「こども・若者の意識と生活に関する調査」(令和4年度)では、15~39歳の約2.05%(約146万人)が「広義のひきこもり」とされています。
また、令和元年度調査では、不登校経験者の約48.2%がひきこもりを経験しており、不登校が引きこもりの大きな要因となることが示されています。
社会との関わりが減ることで外出や対人関係への不安が強まり、自室にこもりがちになるケースも少なくありません。
引用:内閣府:こども・若者の意識と生活に関する調査(令和4年度)
引用:内閣府:子供・若者の意識に関する調査(令和元年度)
データから見る不登校の中学生の将来の現実
不登校を経験した中学生は、その後どのような進路を歩んでいるのでしょうか。文部科学省などの調査で以下のことが明らかになっています。
- 進学・就職の際に苦労した
- 就職して働いている
- パートやアルバイトをしている
- そのまま引きこもりになっている人もいる
進学・就職の際に苦労した
以下は、不登校を経験した人の20歳時点における進学・就職状況に関する調査結果です。
- 高校へ進学・・・85.1%
- 高校中退・・・14.0%
- 学校にも通わず、仕事もしていない・・・18.1%
出典:「不登校に関する実態調査」 ~平成18年度不登校生徒に関する追跡調査報告書~
多くの人が高校に進学していますが、中退や進学も就職もしていないケースも見られます。環境や周りのサポートの有無によって、進路に差が出てしまうのが現実です。
就職して働いている
一方で、社会に出て働いている人も多くいます。
以下は、不登校を経験した人の20歳時点における就職状況の調査結果です。
- 就業している・・・34.5%
- 働きながら学校に通っている人(就学・就業)・・・19.6%
出典:「不登校に関する実態調査」 ~平成18年度不登校生徒に関する追跡調査報告書~
この結果から、不登校を経験していても就職の道が十分にあることが分かります。
パートやアルバイトをしている
また、パートやアルバイトとして働く人も多く、全体の32.2%を占めています。これは、正社員よりも多い割合です。不登校を経験した人にとって社会と関わる最初の一歩として選ばれやすい働き方だと言えます。
少しずつ働く中で経験を積み、自信を取り戻していくことで、将来的にキャリアアップを目指すことも可能です。
出典:「不登校に関する実態調査」 ~平成18年度不登校生徒に関する追跡調査報告書~
そのまま引きこもりになっている人もいる
調査によると、15〜39歳の引きこもり状態にある人のうち約18%が「不登校がきっかけだった」と回答しています。
この結果から、不登校の経験が引きこもりの要因の一つであることが分かります。不登校によって社会との関わりが減ることで対人関係や外出への不安が強まり、そのまま引きこもり状態につながる場合があるといえるでしょう。
「社会で生きていける力」を。
- 入学前不登校経験者8割。
入学後登校率89% - ぷよぷよ、モンスト開発者、
日本一になった起業家
から直接学べる - docomo、Lotte、Mixiなど
大企業と連携したプロジェクト型学習

不登校だった小中学生のその後の将来と経験談
調査の結果を数値で見ても、まだ不安は解消されないかもしれません。ここでは不登校だった人のその後の経験談を状況別に要約して紹介します。
- 大人になって社会で働けている
- 学校復帰した
- 中退または退学した
- 転校や編入した
大人になって社会で働けている
下記は、小学校で5年間不登校を経験しながらも、その後社会で働いている方の経験談です。
小学2年から6年まで不登校だったが、中学入学を機に復学を決意した。乗り越えるべき課題が多く葛藤したが、兄の「中学に行けば将来の選択肢が広がる」という言葉が後押しとなった。 復学後も不安はあったが、友人と過ごす時間が支えとなり、徐々に学校生活に慣れていった。努力を重ね大学で臨床心理学を学び、現在はキャリアアドバイザーや研修講師として活躍している。
出典:みらぴか(不登校5年から再登校のきっかけは?復帰への道のりと復帰後のリアルな葛藤)
学校復帰した
下記は、不登校を乗り越え学校に復帰できた例です。
中学2年生の時、いじめが原因で不登校になったが中学3年でクラス替えがあり再び登校できるようになった。支えてくれた心理士との出会いをきっかけに、自分も心理士になりたいという夢を持つようになった。
その後も嫌がらせを受けることがあったが、夢を持つことで前向きに乗り越えられた。高校進学後は心理学科に進み、今も目標に向かって努力を続けている。
出典:不登校サポートblog(不登校の経験を活かした生き方 3つの体験談)
中退または退学した
下記は、子どもが高校を退学してしまった母親の手記です。
娘は中学3年生から不登校になったが、高校受験も自分で進学先を決め、なんとか全日制の公立高校に入学を果たした。しかし入学後も週1回の登校がやっとで、何度も頑張ろうとしたが体調や気持ちが追いつかず、最終的に高1の夏に退学を決断した。
家族も娘の意志を尊重し、本人のペースを大切に見守った。退学という選択は簡単ではなかったが、自分で決めて行動した経験は、今後の人生にもきっと意味があると感じている。
転校や編入した
下記は、全日制高校から通信制高校へ編入した人の経験談です。
中学2年で不登校になり、なんとか全日制高校へ進学したものの再び通えなくなった。出席日数が足りず、退学か留年かの選択を迫られる中、相談室の先生を通じて通信制高校の存在を知り、転校を決意した。
通信制高校は、毎日クラス全員と顔を合わせる必要がなく、大学の講義のように自分で授業を選べる方式が自分に合っていた。年齢や背景の異なる仲間とも出会い、楽しく学校生活を送りながら無事に卒業できた。
通信制高校への転校は正解だったと感じている。
出典:みちはいろいろ(全日制高校で不登校となり通信制高校に転入、編入(転校)した体験談)
不登校の小中学生が将来のためにできること
不登校になると、将来への不安を抱えたり、学校に行けない自分を責めてしまったりすることもあるでしょう。しかし、そんな状況でも「今できること」は多くあります。
ここでは、不登校の期間でもできることを紹介します。
- 焦らず休息をとる
- 進学や高卒認定取得のために勉強しておく
- 登校に慣れるために少しずつ準備をする
焦らず休息を取る
学校に行くのがつらいと感じる時は、それだけ心や体に負担がかかっている状態です。無理に登校しようとせず、まずはしっかり休むことが大切です。「行きたくない」という気持ちを否定せず、受け入れることも回復の第一歩です。
十分な休息をとることで少しずつ気力が戻り、また前向きになれる日が来るかもしれません。途中で「やっぱり今日は無理」と感じる日があってもそれは自然なことです。
回復にかかる時間は人それぞれです。他の人と比べず、自分のペースで少しずつ進んでいきましょう。大切なのは、ストレスのない安心できる環境で無理せず心と体を整えていくことです。
進学や高卒認定取得のために勉強しておく
不登校の期間でも、学校に通えるようになった時や、進学や高卒認定取得のために勉強を続けていくことが大切です。
自主学習を積み重ねておくことは「いつでも学校に戻れる」という安心感にもつながります。
今は自宅や学校以外の場所でも学べる環境が多くあります。たとえば、オンライン教材や学習動画・タブレット学習・家庭教師・フリースクール・塾など、さまざまな方法があります。
自分に合った方法を取り入れ学習を続けることで、将来の進学や就職などの選択肢が広がります。
登校に慣れるために少しずつ準備をする
不登校からの復帰は、いきなり毎日登校を目指さず、段階的に進めることが大切です。まずは生活リズムを整えましょう。「毎朝同じ時間に起床する」「着替える」「運動する」「同じ時間に就寝する」など、登校日と同じような生活習慣に近づけていきます。
次の段階では、「通学路を歩く」「保健室など教室以外の場所に短時間滞在する」など、無理のない範囲で学校に慣れていきます。
途中でつらくなったら、前の段階に戻っても大丈夫です。自分のペースで小さな成功体験を重ねながら、少しずつ自信を取り戻していきましょう。
不登校の小中学生の将来のために親ができる対応
子どもが不登校になると、保護者は「このままで本当に大丈夫なのか」「どう対応すればいいのか」といった強い不安を抱えるものです。
しかし、今できることは多くあります。
- 不登校の罪悪感を軽減してあげる
- 専門機関に相談する
- 転校や通信制の学校への転入を検討する
まず、できることをやってみましょう。
不登校の罪悪感を軽減してあげる
不登校の子どもは「学校に行けない自分はダメだ」と思い込み、自分を責めてしまいがちです。
子どもの罪悪感を軽減してあげるために、親が心掛けるべきことは、まず子どもの気持ちを受け止め、安心感を与えることです。
子どもの話をじっくり聞き、「行きたくないよね」「辛かったね」と気持ちや悩みに寄り添いましょう。また、「よくあることだから今は無理しないで大丈夫」と明るく声をかけることも大切です。
感情を言葉にできる場をつくることで、子どもは心の重荷や罪悪感を少しずつ和らげていくことができます。
専門機関に相談する
一人で悩まず、ぜひ専門機関や支援団体の力を借りてみてください。専門家は、これまでさまざまな不登校のケースに対応してきた経験と知識があり、個々の状況に寄り添った支援をしてくれます。
相談できる場所は、公的機関や民間団体など多くあります。下記は一例です。
- 教育支援センター
- 子ども家庭支援センター
- 教育相談所
- 不登校カウンセラー
- 不登校の親の会
- ひきこもり地域支援センター
これらの機関では、学習の遅れや心のケア、子どもへの対応方法まで幅広く相談できます。状況に応じた具体的なアドバイスを受け、今後の方向性を一緒に考えられます。
また、不登校の親の会などのコミュニティに参加することで「悩んでいるのは自分だけではない」と感じられたり、情報交換を通して解決のヒントが見つかるかもしれません。
「どうしてうちの子だけ・・・」と感じてしまう時こそ、誰かと悩みを共有してください。きっと不安が軽くなり、前向きな一歩が踏み出せます。
転校や通信制の学校への転入を検討する
※HR高等学院CEOである山本将裕と共同設立者の成田修造氏による教育や通信制高校をテーマとしたYoutubeチャンネル
今の学校が合わない場合、思い切って新しい環境に移ることで気持ちを切り替え、自信を取り戻せることがあります。その1つが転校や通信制高校への転入です。
特に、通信制高校の大きなメリットは自分のペースで学べることです。また、不登校経験者や専門スタッフがいるため悩みを共有しやすくサポートも充実しています。
通信制高校に転入してから楽しく通えるようになったという人も多くいます。
さらに、小中学校の学び直しや専門的な学習もできるため、自分の得意な分野を伸ばせるでしょう。進学や就職など、卒業後の進路も幅広く選べることも魅力です。
通信制高校サポート校「HR高等学院」をご紹介
HR高等学院は、2025年4月に開校した通信制高校サポート校です。所定の条件を満たすことで高校卒業資格を取得できます。
- 学生主体の学びを実現
- 社会で活躍する大人が伴走者となりサポート
- 不登校など多様な背景を持つ学生にも柔軟に対応
- 協賛企業との連携による実践的な授業
- 海外71大学への推薦枠
不登校経験者を含む多様な背景の学生が安心して通えるよう、学習スタイルには柔軟性を持たせています。オンラインのみの選択も可能で、全国から入学できます。通学日数は半年ごとに変更可能です。全日制高校のように時間割に縛られず、自分のペースや関心に合わせて学べる点が特長です。
起立性調節障害などの持病を持つ学生にも丁寧に対応し、状況に合った無理のない学び方を一緒に見つけていくため、安心して通えます。
学びの中心にあるのは学生の主体性です。「何をどう学ぶか」を自ら考えて行動することを通じて、挑戦する意欲や自己肯定感を育みます。
また、社会で活躍する大人が「伴走者」として寄り添い、1対1のコーチングや学習支援を行っています。
カリキュラムには、docomo、LOTTE、CHINTAI、mixiなど名だたる企業と連携した課題解決型学習(PBL)や専門ゼミ、次世代教養など革新的な手法を採用しています。実社会で求められるスキルを、社会の変革に挑むトップランナー講師による実践的な授業で身につけられるのが特長です。
進路は国内外の大学進学や就職・起業など幅広く対応しており、専任サポーターが手厚く支援します。世界大学ランキング上位校への推薦枠もあり、グローバルな進路も目指せます。
体験会に参加した不登校経験者からは、「ワークショップ形式での対話が楽しかった」「学校名や学力を聞かれず、安心して参加できた」との声が寄せられています。
下記は、学生のインタビューです。リアルな声が聴けますのでぜひご覧ください。
ぜひ体験会に参加して実際の雰囲気を体感してください。まずは行動してみることが大切です。
「日本でいちばん自由で面白い学校」を目指しています。 - HR高等学院
最後に
この記事では、子どもの不登校に悩む保護者や本人に向けて、不登校の将来の現実やリスク、体験談、そして今できることを解説しました。
不登校の状態が続けば、進路や就職に不安を感じるのは当然ですが、乗り越える選択肢やサポートは数多くあります。
実際に不登校を経験した多くの人が、自分に合う進路を見つけ、大学進学や就職を果たし社会で活躍しています。
今は多様な価値観が受け入れられる時代です。世間の当たり前に縛られたり他の人と比較せず、自分に合った道を見つけ前向きに進みましょう。