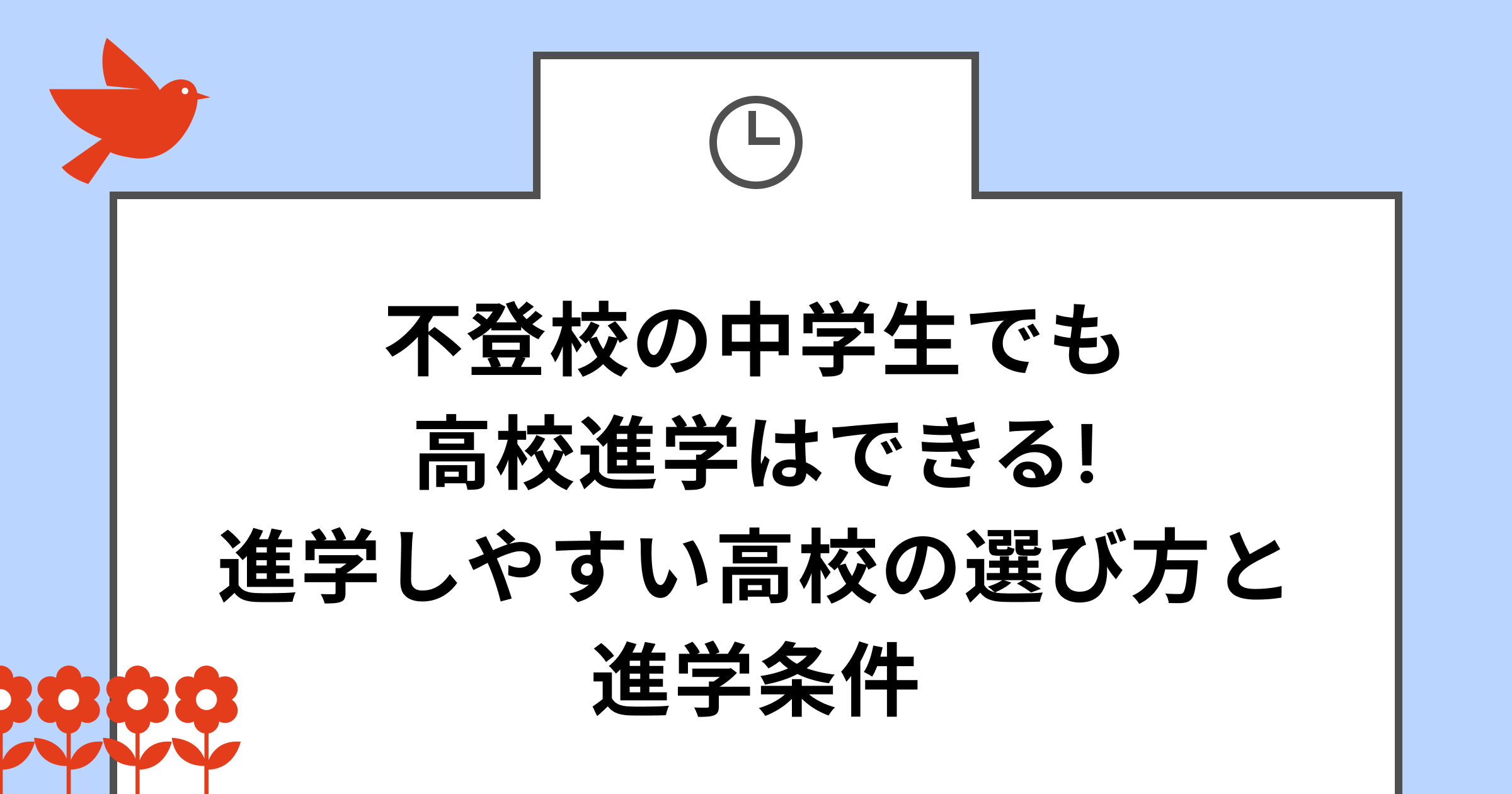「欠席が多くても高校に進学できるのか」「無理なく通える学校はあるのか」不登校の経験がある中学生や保護者の方にとって、進路の悩みはとても大きなものです。
「不登校」と一言でまとめられがちですが、その背景や理由は一人ひとり異なります。人間関係・学習への不安・体調の問題など原因はさまざまですし、「何となく行けなくなった」という理由が明確でないケースも少なくありません。
だからこそ、高校進学を考えるときには、「無理なく通える」ということを最優先に、自分に合う高校を探すことが大切です。
今は、通信制高校や定時制高校など学び方の選択肢が豊富にあります。
この記事では、不登校経験者が進学できる高校のそれぞれの特徴や入学の条件、選び方と注意するポイントも解説します。
読めばきっと、不安な気持ちが少し軽くなり、前向きに高校進学を考えられるようになるはずです。
不登校でも高校進学はできる?
「不登校だから高校進学は無理かも…」と不安に思っている方も多いかもしれません。しかし、実際には不登校経験のある中学生の多くが高校へ進学しています。
文部科学省が平成18年度に実施した調査によれば、中学校を卒業してすぐに高校へ進学した不登校の学生は、全体の約80%にのぼります。この調査はやや古いデータであるため、不登校への理解がある学校が増えた現在では、さらに多くの学生が進学していると考えられます。
不登校になるとどうしても出席日数が少なくなり、内申点も悪くなりがちです。しかし、高校には全日制だけではなく、定時制や通信制といった選択肢もあります。
特に通信制高校は、学力試験を実施しない学校が大半で、出席日数や内申点が合否に影響するケースはほとんどありません。そのため、不登校経験者であっても進学しやすいというメリットがあります。
また、全日制高校でも、「不登校枠」と呼ばれる特別な入試制度を導入する学校も徐々に増えてきています。
まずは「不登校でも高校に進学できる選択肢がある」という事実を知ることで、不安を少しでも和らげていただけたらうれしいです。
参考までに、弊校HR高等学院CEOの山本将裕と共同設立者の成田修造氏による「不登校児童と内申点」をテーマとしたYoutubeを紹介します。「そもそも内申点を本当に気にする必要があるのか?」について議論しており、興味深いです!こちらもぜひ視聴してみてください!
不登校からでも高校進学するために必要な条件
不登校からでも高校に進学するための必要な条件を、「出席日数」「内申点」「学力」に分け解説します。
出席日数
高校に進学するために必要な出席日数は、学校の種類や都道府県によっても異なります。
全日制の高校の場合
全日制高校の多くは、中学3年間の出欠席日数を調査書(内申書)で評価します。一般的には「欠席が年間10日以内」であれば大きな不利にならないとされていますが、基準は地域や学校によって異なります。
特に、私立高校の推薦入試では「3年間の欠席合計20日以内」など、欠席日数の条件が設けられていることがあります。
通信高校の場合
通信制高校は中学での出席日数に関しては原則問われません。出席日数より、意欲や目標を重視します。
定時制高校の場合
定時制高校も全日制高校と同様に、中学校の内申書や出席状況を参考資料とするのが一般的です。
しかし、不登校の学生に受け入れに理解のある学校が多く、出席日数が少なくても柔軟に対応する学校が多くなっています。
内申点
内申点とは、中学校で学んだ9教科の成績を点数化したもので、志望校に提出する調査書(内申書)に記載され進学時の参考資料として使われます。
高校入試では、この内申点が合否の判断材料として用いられるケースが多く、公立高校では特に重視される傾向があります。
一方で、私立高校では内申点よりも学力検査を重視する学校が多い傾向です。
定時制高校や通信制高校では、内申点は評価の対象にせず、面接や作文を中心とした選考を行うケースが多く見られます。
受験のための学力
高校受験では「学力」が問われる場面が多く、どのような入試方式を選ぶかによって、求められる学力や試験内容が大きく異なります。ここでは、公立高校と私立高校、さらに一般入試と推薦入試の違いに注目して整理します。
一般入試では筆記試験が重視され、公立高校の場合は内申点と5教科の学力試験の合計で選抜されるのが一般的です。一方で、私立高校では当日の学力試験の結果が重視される傾向が強く、主に英語・数学・国語の3教科で実施されます。
推薦入試では、面接や書類審査が中心となり、学力試験は原則としてありませんが、一部の学校では独自の学力検査や作文が行われる場合もあります。
このように、公立か私立かや入試方式によって学力の問われ方や筆記試験の有無が異なるため、学校を選ぶ際は、どの程度学力が問われるか、筆記試験があるかどうかを確認しましょう。
定時制高校の場合
定時制高校の入試では、簡単な基礎学力試験(国語・数学・英語など)と面接が行われるのが一般的です。
学校によっては、理科や社会、作文が加わることもありますが、基本的な内容が中心で、試験の難易度はそれほど高くないとされています。
また、学校によっては学力試験を行わず、面接や作文のみで選考する場合もあります。
通信制高校の場合
通信制高校では、面接や作文、書類審査が中心で、筆記試験は実施しない学校がほとんどです。実施される場合でも国語・数学・英語の3教科が一般的で、基礎的な内容となっており、学力試験の結果だけで合否が決まることはほとんどありません。
学力よりも本人の意思や適性が重視される傾向があります。
「社会で生きていける力」を。
- 入学前不登校経験者8割。
入学後登校率89% - ぷよぷよ、モンスト開発者、
日本一になった起業家
から直接学べる - docomo、Lotte、Mixiなど
大企業と連携したプロジェクト型学習

不登校でも進学できる高校の選択肢と種類
不登校で中学校に通えていなかったとしても、高校進学の選択肢は多くありますので安心してください。
以下に主要な5種類の高校の特徴を比較表にまとめました。
順に詳しく解説します。
公立高校
公立高校は、週5日間の通学を基本とし、午前から午後まで時間割に沿って授業が行われます。学費が安く、地元から通いやすい点は大きなメリットです。また、部活動や学校行事などにも積極的に参加したい人には適した環境といえるでしょう。
一方で、入試では内申点や出席日数が重視されるのが一般的です。そのため、中学校での欠席が多い場合は、選抜において不利になるため、不登校経験者にとっては進学の難易度がやや高めとされています。
また、全日制高校の生活スタイルに適応できるかどうかをしっかり見極めることが大切です。
不登校枠について
近年、不登校の学生を対象とした「不登校枠」や特別な入試制度を設ける全日制高校が増えてきました。ただし、これは不登校専用の募集枠というより、入試で欠席日数や内申点に一定の配慮がなされる選抜方法を指します。
たとえば、欠席日数を評価対象としなかったり、欠席が多い場合でもその理由や背景を考慮し、不利にならないよう配慮されるケースがあります。
ただし、こうした制度はすべての高校で実施されているわけではなく、導入状況は自治体や各学校の方針によって異なります。
受験を考える際は、志望校や自治体の最新情報を事前に確認しておくことが大切です。
出典:愛知県義務教育課「長期欠席者にかかる選抜方法について」
私立高校
私立高校も基本的に週5日通学で、午前から午後までの授業を行う全日制の学校が中心です。公立高校に比べてカリキュラムの自由度が高く、学校ごとの教育方針に沿った特色ある教育が受けられるのが特徴です。 また、最新の設備や学習支援体制が整っている学校も多く、進学指導にも力を入れている傾向があります。
公立高校に比べて出席日数や内申点をそれほど重視しない学校も多いため、不登校経験者も比較的受験しやすい場合があります。ただし、入試の傾向が学校ごとに大きく異なるため、事前に出願条件や選抜方法をしっかり確認しておく必要があります。
学費は公立よりも高額で、施設費や寄付金などが別途かかるケースもあります。
定時制高校
定時制高校は、午前・昼間・夜間など授業時間が分かれており、自分のライフスタイルに合わせて通学できるのがメリットです。働きながら通う学生も多く、週5日制でも授業時間が短いため、体力的・精神的な負担が少なく、不登校経験者にも通いやすい環境です。
また、学び直しを支援する体制が整っている学校も多く、入学のハードルは高くありません。年齢や背景の異なる学生が多く、多様な雰囲気の中で自分のペースで高校生活を送れます。
ただし、多くの定時制高校は卒業までに4年かかるカリキュラムのため、3年での卒業を希望する場合は注意が必要です。また、進学サポートが手薄な場合もあるので、大学進学を目指す場合は自主的な学習や塾の活用も検討しましょう。
通信制高校
通信制高校は、レポート提出やスクーリング(登校)、試験などで単位を修得し、卒業を目指します。卒業要件を満たせば高校卒業資格が得られ、最終学歴は「高卒」となります。
登校頻度は学校によって異なり、週1日から5日まで選べる場合や、完全オンライン対応の学校もあります。自由度が高いため、自分のペースで学べる点が大きな特徴です。
また、入試は面接や作文のみで調査書を重視しない学校が多いため、不登校経験者にも進学しやすい選択肢です。
ただし、自己管理能力が求められるため、計画的に学習を進める意識が必要です。大学進学を目指す場合は、通信制高校のカリキュラムに加え、受験対策を別途行う工夫も大切です。
不登校から高校進学する際の注意点と選び方
不登校経験者が高校を選ぶ際は以下の項目をしっかり確認して選ぶことが大切です。
- 子どもが充実した学校生活を送れるのかどうか
- 卒業後の進学や進路
- 通学時間・通学距離
- 学費
- 就活サポート
学校の教育方針や環境はもちろん、将来の進路や通いやすさなど、複数の観点から慎重に検討しましょう。
子どもが充実した学校生活を送れるのかどうか
まず大切なのは、「無理なく通い続けられるかどうか」と、子ども自身が「この学校なら通ってみたい」と前向きに思えるかどうかです。どんなに評判の良い学校でも、本人が安心して過ごせなければ意味がありません。
学習面だけでなく、学校の雰囲気や通学スタイルが自分に合っているか、楽しさや安心感を持てるかをしっかり確認しましょう。また、パンフレットやインターネットの情報だけで判断せず、保護者と本人が一緒に学校見学に行き、自分の目で体感することが大切です。
卒業後の進学や進路
高校卒業はゴールではなく、その先の進路への大切な一歩です。大学や専門学校への進学、就職など、どんな未来を描いているかによって、必要なサポートも変わってきます。
進学率や進学先、就職先の実績、進路指導の内容などを確認し、自分の希望する進路が実現しそうかを見極めましょう。学校説明会では、進路指導の担当者に直接質問してみるのもおすすめです。
通学時間・通学距離
通学時間や通学距離は、高校生活を送るうえでとても大切なポイントです。「自宅から無理なく通える距離か」は最も重要になります。特に不登校経験者の場合、通学時間が長いと体力的にも精神的にも大きな負担となることがあります。
早朝に家を出る必要があったり、満員電車やバスでの移動が続くと、心身ともに疲れやすくなり、学校に行く意欲が下がってしまうことも考えられます。
無理のない範囲で通える距離かどうか、通学ルートと交通手段や所要時間の確認はもちろん、実際に学校まで行ってみることが大切です。自宅から近い学校やアクセスの良い学校を選ぶことで、毎日の負担を減らし、学校生活により集中することができるでしょう。
学費
多くの保護者が気になるのが「学費はどれくらいかかるのか」という点でしょう。
下記に、それぞれの高校ごとの学費の目安をまとめました。
ただし、学費は、学校や通学スタイルによっても異なります。
また、授業料以外にも通学にかかる交通費、部活などの課外活動に参加するかどうかによっても大きく変動します。そのため、個々の状況や希望に合わせて授業料以外にかかる費用も含めてしっかり見積もることが大切です。
文部科学省の調査によると、学年制の全日制高校3年間でかかる学費の平均は、公立高校で約154万円、私立高校では約316万円とされています。
通信制高校や定時制高校は、公立と私立で学費に大きな差があります。特に、私立は学校により金額の幅が広く、選ぶコースや通学頻度によっても費用が大きく変わります。
たとえば、通信制高校の場合、週1回の通学コースと週5回の通学コースでは年間で数十万円の差が生じることもあります。また、定時制高校でも、公立は年間約3万円、私立は年間約35万円が平均ですが、私立では教材費や施設費などの諸経費によってさらに差が広がる場合があります。
出典:東京都教育委員会「都立高等学校、中等教育学校(後期課程)の授業料・入学料及び特別支援学校高等部の授業料について」)
ただし、高等学校等就学支援金制度や各地方自治体による支援によっては実際にかかる学費は変わるため、世帯ごとに状況が変わることを念頭に置いておきましょう。
高等学校等就学支援金制度について
高等学校等就学支援金制度は、高校などに通う学生の授業料負担を軽減するため、国が支給する返済不要の支援金制度です。2025年度からは、この制度が拡充され、公立・私立を問わず高等学校(全日制・定時制・通信制を含む)すべてが対象となります。
特に公立高校では所得制限が撤廃され、すべての世帯で授業料が実質無償化されます。また、私立高校や通信制高校でも、世帯収入などの条件を満たせば支援金が支給され、費用負担を大きく軽減できる場合があります。
進学先によって支援内容や条件が異なるため、最新情報や詳細は文部科学省の公式サイトなどで必ず確認しましょう。
学費について特に心配なポイントかもしれません。ですが、就学支援金や学校独自の奨学金などの制度を利用する事で費用が大幅に軽減される場合もあります。経済的な理由で進学を諦める前に、各種支援制度についてしっかり調べてみましょう。
就活サポート
高校卒業後に就職を考えている場合は、学校の就職サポートの確認も大切です。どんな求人があるのか、企業見学の機会はあるか、面接練習や履歴書の添削など、実践的な指導が受けられるかを事前に確認しておきましょう。
さらに、卒業生の就職実績や内定率なども調べましょう。本人の適性や希望に応じて就職先を一緒に探してくれるような、親身なサポートが受けられるかもチェックポイントになります。
通信制高校サポート校「HR高等学院」をご紹介
HR高等学院は、2025年4月に開校した通信制高校サポート校です。卒業の条件を満たすことで、高校卒業資格を修得できます。
- 不登校経験があっても通いやすい柔軟な学習環境
- 学力や出席日数を問わない入学選考
- オンラインのみや週5通学まで選べる自由な学習スタイル
- 実社会を生き抜く力を養う企業と連携した授業
- 学びの伴走者による手厚い学習サポート
- 海外大学推薦枠を含む多様な進路対応
入学時に中学校での出席状況は問われず、筆記試験もありません。そのため、不登校経験のある中学生でも安心して新たな一歩に挑戦できるのが特徴です。
通学スタイルは完全オンラインから週5日の通学まで自由に選択可能で、ライフスタイルや体調に合わせて自分のペースで学びを進められます。 さらに、先生ではなく実社会で活躍する大人が「伴走者」として寄り添い、学びを支える独自の教育体制を取り入れています。受け身の学習ではなく、自分で考え行動する力を自然と身につけられる環境です。
カリキュラムには企業と連携したPBL(プロジェクト型学習)を導入し、実社会の課題に挑みながら、実践的なスキルや、起業に必要な思考力・行動力も身につけられます。
将来の進路も広くサポートしており、国内外の大学進学や就職、起業など多様な進路選択に対応しています。中でも、世界大学ランキング18位のシドニー大学を含む71校の海外大学推薦枠を持っていることが強みです。
HR高等学院の特色ある教育や学生への手厚いサポートは、教育専門メディア「東洋経済education」でも大きく取り上げられています。記事内では、ホームページ上に掲載されていない、学生のリアルな声や学校開設の秘話などが詳しく紹介されていますのでぜひご覧ください。
出典:東洋経済education(企業や起業家と連携、興味を探究してキャリアにつなげる「通信制サポート校」ができた訳)
HR高等学院なら、主体性を大切にして、自由なスタイルで、自分のペースで学ぶことができます。
まず、資料請求や説明会でHR高等学院の他校との違いや雰囲気を体感してみてください。
最後に
この記事では、不登校経験者が進学できる高校のそれぞれの特徴や条件、選び方から注意するポイントを詳しく解説しました。
不登校の経験があっても、高校進学は十分に可能です。そして、その選択肢は一つではありません。全日制高校だけでなく、通信制高校やサポート校など、自分に合うスタイルで学べる場がたくさんあります。
「不登校だった時間」を否定する必要はありません。その経験を通じて学んだことや得たものもきっとあるはずです。そのうえで、「これからどう学びたいか」「どんな自分でいたいか」と、過去よりも未来に目を向けて進んでほしいと願っています。
まずは気になる学校の資料請求や授業見学・説明会への参加から、第一歩を踏み出してみてください。自分に合う道がきっと見つかります。